�A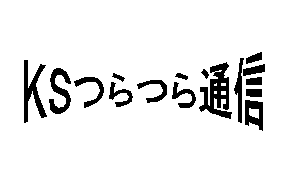
�o������26
�u�j�r���ʐM�E�W�������ʃe�[�}�ꗗ�v��
���[���͂�����ցFkatagiri@kansai-u.ac.jp
![]()
���ڎ���
��1077���@�u�����v���삾�I�i�Q�O�Q�T�D�P�Q�D�Q�U�j
��1076���@��ՓI�ȏo��i�Q�O�Q�T�D�P�Q�D�Q�S�j
��1075���@12����2�y�j���i�Q�O�Q�T�D�P�Q�D�P�R�j
��1074���@���_��AI�Ȃ̂��ȁH�i�Q�O�Q�T�D�P�Q�D�P�Q�j
��1073���@�Ⴂ�����̑O���̎��Ӗ��i�Q�O�Q�T�D�P�Q�D�W�j
��1072���@�ۑ背�|�[�g�Ƃ`�h���p�i�Q�O�Q�T�D�P�Q�D�P�j
��1071���@���тƃE�N���C�i�i�Q�O�Q�T�D�P�P�D�Q�S�j
��1070���@���h���u�����v���ʔ����i�Q�O�Q�T�D�P�P�D�T�j
��1069���@���炵���킢�ł����i�Q�O�Q�T�D�P�P�D�R�j
��1068���@�Â���10��31���ł������i�Q�O�Q�T�D�P�P�D�P�j
��1067���@��Օێ�w�ł͂Ȃ��u�����ێ�w�v�ɒ��ڂ��ׂ��i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�R�O�j
��1066���@26�N�O�̎咣�����߂Ă������i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�P�W�j
��1065���@�g������A�����������i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�P�R�j
��1064���@�����}�̘A�����E���獡��̐��ǂ�\�������i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�P�P�j�y�NjL�i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�P�T�j�z
��1063���@�ԍ��̎Љ�w�i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�U�j
��1062���@���s���c�����}�V����!!�i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�S�j
��1061���@��㒁�����������i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�R�j
��1060���@���ǂ��̊w�������i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�P�j
��1059���@�u���肪�Ƃ��v�̓|���g�K���ꂪ�ꌹ�H�i�Q�O�Q�T�D�X�D�Q�W�j
��1058���@�������܂�͂���4�l�i�Q�O�Q�T�D�X�D�Q�O�j
��1057���@��㖜���T�K�L�i���̂R�j�i�Q�O�Q�T�D�X�D�P�W�j
��1056���@�����}���̈ӌ��͐��_�f���Ă��邩�H�i�Q�O�Q�T�D�X�D�P�P�j
��1055���@���{�x�x���́u�p�p���v�����i�Q�O�Q�T�D�W�D�R�O�j
��1054���@�w���ƃ����w���x�i�Q�O�Q�T�D�W�D�Q�X�j
��1053���@������M���āA���������l�������̂����i�Q�O�Q�T�D�W�D�Q�U�j
��1052���@�������u�n���E�m�[�g�v�����������A�A�A�i�Q�O�Q�T�D�W�D�P�W�j
��1051���@�^�Ɠw�́A���邢�͋��R�ƑI���i�Q�O�Q�T�D�W�D�P�T�j
��1050���@�u���{���p�̍z���W�v���ʔ����i�Q�O�Q�T�D�W�D�P�R�j
��1049���@�l���ɂ͒����ڕW���K�v�i�Q�O�Q�T�D�W�D�P�O�j
��1048���@�G�b�`�i�Q�O�Q�T�D�W�D�R�j
��1047���@���߂Ȃ��g�b�v�i�Q�O�Q�T�D�W�D�P�j
��1046���@�P�A�n�E�ƂɏA�������̍������͍����̂ł́H�i�Q�O�Q�T�D�V�D�Q�U�j
��1045���@��w���������玟�̑I���ŋN���邱�Ƃ��������i�Q�O�Q�T�D�V�D�Q�T�j
��1044���@���}�}�b�`���O�������Ă݂��i�Q�O�Q�T�D�V�D�P�U�j
��1043���@�Q���}�̐L���͂����i�Q�O�Q�T�D�V�D�P�T�j
��1042���@���������A����Ȋ����Ȃ̂����i�Q�O�Q�T.�V�D�P�R�j
��1041���@����̍u�`�����Ƃ������i�Q�O�Q�T�D�U�D�Q�W�j
��1040���@��㖜���T�K�L�i���̂Q�j�i�Q�O�Q�T�D�U�D�Q�Q�j
��1039���@�V�u�����������v�i�Q�O�Q�T�D�U�D�P�W�j
��1038���@�������胉�e�����������Ă��܂����i�Q�O�Q�T�D�U�D�P�S�j
��1037���@�������u�ׂ�ڂ��v�i�Q�O�Q�T�D�U�D�P�S�j
��1036���@���{��`�ɂ����i�Q�O�Q�T�D�U�D�X�j
��1035���@�����ΗY�������i�Q�O�Q�T�D�U�D�R�j�y�NjL�i�Q�O�Q�T�D�U�D�W�j�z
��1034���@�����̕������Ȃ�i��ł���A�A�A�i�Q�O�Q�T�D�U�D�Q�j
��1033���@�����̓ǂݕ����Ēʏ̂������̂��ȁH�i�Q�O�Q�T�D�T�D�R�O�j
��1032���@�l���̐ߖڂ̃C�x���g�͑���i�Q�O�Q�T�D�T�D�Q�P�j
��1031���@����ȕ��Ɏv���Ă��炦�Ċ������Ȃ��i�Q�O�Q�T�D�T�D�P�U�j
��1030���@�����̍ۂɕv�w�̖���������荇���邩�H�i�Q�O�Q�T�D�T�D�U�j
��1029���@��㖜���T�K�L�i�Q�O�Q�T�D�S�D�Q�V�j
��1028���@���i�Q�O�Q�T�D�S�D�P�R�j
��1027���@�u�g�����v�E�V���b�N�v�͂��܂ő������H�i�Q�O�Q�T�D�S�D�S�j
��1026���@�H���N�̉̎����āA�A�A�i�Q�O�Q�T�D�S�D�Q�j
��1025���@�V�N�x�X�^�[�g�i�Q�O�Q�T�D�S�D�P�j
��1024���@��̓h���}�u�ׂ�ڂ��v�i�Q�O�Q�T�D�R�D�R�O�j
��1023���@�z�[���ɖ߂����C���i�Q�O�Q�T�D�R�D�Q�V�j
��1022���@�䓰���Ă������痈�Ă����̂����i�Q�O�Q�T�D�R�D�V�j
��1021���@�u81���ˁI�v�i�Q�O�Q�T�D�R�D�T�j
��1020���@���h��18�����ǁA�A�A�i�Q�O�Q�T�D�R�D�S�j
��1019���@�A���t�B�[�Ƌ˓����i�Q�O�Q�T�D�Q�D�Q�T�j
��1018���@�V�c�a�����i�Q�O�Q�T�D�Q�D�Q�P�j
��1017���@�������Ă��Ȃ����낤���H�i�Q�O�Q�T�D�Q�D�P�V�j
��1016���@���Z���Ɨ��������ւ̋^���i�Q�O�Q�T�D�Q�D�P�P�j
��1015���@�ł��グ�ē�������̂͒N�Ȃ̂��낤�H�i�Q�O�Q�T�D�Q�D�P�O�j
��1014���@���[��A�A�A�t�̎v���o��148�~�I�i�Q�O�Q�T�D�Q�D�R�j
��1013���@�u�펯�̊v���v�i�Q�O�Q�T�D�P�D�Q�P�j
��1012���@���ǂ��̐��l���i�Q�O�Q�T�D�P�D�P�T�j
��1011���@���a100�N�i�Q�O�Q�T�D�P�D�R�j
![]()
��1077���i�Q�O�Q�T�D�P�Q�D�Q�U�j�u�����v���삾�I
�@�����̒��h���v�u�����v�����܂������B�������ł��ˁA���̍�i�́B���h���Ƃ������肫����̘g���Ė���h���}�ł��ˁB�������ŏI��ł����Ȃ��Ƃ����ō��̏o���ł����B15���ԑg�Ȃ̂ɁA�I�[�v�j���O�e�[�}�Ȃ����ꂾ�����̂�12��30�b�߂��ŁA�����Ƃ܂������Ⴄ�����w�i�ɏo���҂̖��O���������o�邾���A�����Ă��̃I�[�v�j���O�ȁu������]��v�̍Ō�̉̎��u�N�ׁ̗@��������^������@�U�����܂��傤���v�����T�̃e�[�}�ɂȂ��Ă���Ȃ�āA�������ł��B���̉̎��ɍ��킹�ċr�{���������̂ł��傤���H�U�����āA�[���̋P���C�ӂ��S�O���Ȃ���D��������Ȃ��B���ꂾ���œ�l�̎v�����d�Ȃ荇�������Ƃ������ɕ\������܂����B���y�A�r�{�A���o�A���Z�A�p�[�t�F�N�g�ł����B���̃V�[���́A���N�o���Ă����h���j��Ɏc�閼�V�[���ƌ����邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
![]()
��1076���i�Q�O�Q�T�D�P�Q�D�Q�S�j��ՓI�ȏo�
�@�ꕔ�̐l�ɂ������m�点���܂���ł������A���NHKBS�ŕ������ꂽ�u29�A���B��`���v�Ƃ����~�j�h�L�������^���[�ɁA�����o�ƂƂ��ɂ�����Ɠo�ꂵ�܂����B�����|�p��w�̑�w�@���ł���ÊG���z����Ƃ���29�̎Ⴋ��Ƃ������B�̕��i��`���Ă���̂ł����A�Ȃ��ނ����B��`���悤�ɂȂ����̂��A�ǂ̂悤�Ȏ�@�ŕ`���Ă���̂��J�ɏЉ���h�L�������^���[�ԑg�ł��B��@�ƌ����Ă��G����L�̎�@�̘b�Ƃ����ȏ�ɁA�ÊG���������̖��B�Ɋւ��鎑����O��I�ɒT�����ׂĕ`���Ƃ�����@������Ă���̂ŁA���̖Ȗ��Ȏ�@���Љ��Ă��܂��B���̒��ׂ́A���傻����̗��j�����҂�D�ɗ��킷�钲���͂ŁA���̂܂ܗ��j�����̘_����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���قǂł��B
�@���āA����ȉ�Ƃ����ǂ����h�L�������^���[�ԑg�ɂȂ������o�ꂷ�邩�ł����A���͍��ނ��͂����ĕ`���Ă����ނ��A�\�A����S���Ƃ̍����߂��ɂ������n�C�����Ƃ����X�̂Ȃ��ɂ������u�ėσz�e���v�Ƃ�����������������ł��B�ƌ����Ă��܂��Ȃ���Ȃ��ł���ˁB���́A���̃z�e�������Ă��\�\�I�[�i�[�ł͂Ȃ��A�v���z�����\�\�̂����̑c���E�Ћˌc���Y�������̂ł��B�����āA����͒ÊG�������ׂ����Ƃł͂Ȃ��A�ق�̏����Ȑړ_�łȂ���킩�������ƂȂ̂ł��B
�@���������̃t�@�~���[�q�X�g���[���ׂ�10���N�O���炩�Ȃ肵�Ă���Ƃ����̂́A����HP���܂߂ɓǂ�ł���Ă�����Ȃ炲�������Ǝv���܂����A��r�I���ԓI�]�T�̂��������̉ĂɁA�c���E�c���Y�̈��L���܂Ƃ߂Ă݂悤�Ǝv���A���낢�뎑�������Ĉꉞ�ȗ��I�Ȉ��L���܂Ƃ߂܂����B������o���ɂ��ǂ�ł��炨���Ǝv���������Ƃ���A�o�������������Ă���āA�����ɏo�Ă���c���Y�����B�Ō��Ă��u�ėσz�e���v�ɂ��ĉ���������Ȃ����ƃl�b�g�����������Ƃ���A���܂��ܒ��茧�ݏZ�̂�����̃t�F�C�X�u�b�N�Ɂu�ėσz�e���Ŏg���Ă�����v�̎ʐ^���o�Ă��āA�u����ȏ��������v�ƒm�点�Ă��ꂽ�̂ŁA�������̕��̃t�F�C�X�u�b�N�ɘA���������Ƃ���A���̌ėσz�e���ɂ��ẮA�ÊG���z����Ƃ�����Ƃ��ڂ������ׂĂ�����Ƌ����Ă��炢�A���x�͒ÊG���ɘA�������A�ړ_���ł����킯�ł��B
�@�ÊG�����܂�����������ނƂ��Ă���z�e���{�H�҂̑�����A��������Ƃ͑z�������Ă��Ȃ����������ŁA�������ɋ����A����9���ȍ~�p�ɂɘA������荇���A11���ɂ͂�����邱�ƂɂȂ����킯�ł��B���Ȃ݂ɁA�h�L�������^���[�ԑg�ɂȂ����̂́A���̏o�������������ł͂Ȃ��A�ԑg�f�B���N�^�[�̕����ÊG���̎d���ɋ������������łɔނ�ǂ������Ă��܂����B�ėσz�e���̃I�[�i�[�̖��������ł����݂ŁA�����ɒÊG�����Ăɉ�ɍs���ꂽ���̗l�q���f���ɂȂ��Ă��܂�������A�������̍��ɂ͂��̃h�L�������^���[�̊��͎n�܂��Ă����킯�ł��B���Ȃ݂ɁA�����͉䂪�ꑰ�̏o�g�n�ł��B�c���Y�����B�Ōėσz�e�������Ă邱�ƂɂȂ����̂��A���̒n���q����̂������ł��B������ɂ���A���łɎn�܂��Ă����h�L�������^���[���ɁA�r�������X�o��̓o��Ƃ������ƂɂȂ����킯�ł��B�܂��������R�������킯�ł����A�h�L�������^���[�Ƃ��Ă͂��Ԃ���ʔ����Ȃ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�ԑg�ł��Љ�Ă��������܂������A�c���E�c���Y���S���Ȃ���25�N�قǂ��Ă���A�e�����c���Y�̎v���o�������A��������̕������ׂĎ菑���Ő��������w�����`�x�Ƃ������q���c����Ă������ƂŁA����������ՓI�ȏo������܂ꂽ�킯�ł��B�c���͏��a22�N�ɖS���Ȃ��Ă��܂��̂ŁA�����o����������Ƃ��Ȃ��c���������̂ł����A����̊�Ղ̏o��̂������ŁA���O�����m��Ȃ������ėσz�e���̑S�i�ʐ^��A�����̎ʐ^�Ȃǂ������Ă��炢�A�c�������������Ɗ��Ă����p���ڂɕ�����ł���C�ɂȂ�܂����B��͂�L�^���c���̂͑f���炵�����Ƃł��B����A���X��ւƎ����q���Ă����Ȃ���Ɖ��߂ċ����v���܂����B
![]()
��1075���i�Q�O�Q�T�D�P�Q�D�P�R�j12����2�y�j��
�@�����́A12���̑�2�y�j���ł��B��N��������A�u�Ћ˃[�~�̏W���v���J�Â��Ă�����ł����B���N�̂悤�ɎQ�����Ă���Ă����l�����́A������Ǝ₵���v���Ă���Ă��邩������܂���ˁB�i���ɂ́A���N�蒠������A�ŏ���12����2�y�j���̓[�~�̏W���Ə����Ƃ������҂����܂��B�j���܂ɁA��3�y�j���ɂȂ�����������܂������A��{�I�ɂ���12����2�y�j�����u�Ћ˃[�~�W���v�̓��Ƃ��āA1992�N����C�M���X�ɍs���Ă������������ă[�~�̏W�܂������Ă��܂����B2004�N����͖��N100������[�~�����W�܂�A�V�[�~���̊��}�����˂āA�Ћ˃[�~���L�̃^�e�Ȃ���̏������Ă������̂ł����B��N���łɐV�[�~���͂��܂���ł������A3�[�~�������Ċ撣���Ă��ꂽ�̂ŁA�R���i�БO�ȗ�5�N�Ԃ�ɕ������������H�p�[�e�B�������ɉ^�c���Ă���܂����B���̎��ɁA�u�܂����N�����܂��傤�B��肽���I�v�ƌ������͂������Ă��܂������A���̑�K�͂ȏW�܂���^�c����̂͗e�Ղł͂Ȃ��A����ɍ��N�x�́A5���Ɂu�Ê�̏W���v�A������3���ɂ͍ŏI�u�`���u�ɂ��މ�v�ƏW�܂�@�����̂ŁA12���͂Ȃ��̕����������낤�Ɣ��f���܂����B�ł��A��������12����2�y�j�����}���Ă݂�ƁA�ꖕ�̕�����Ȃ��������Ă��܂��Ă��܂��B�u������A���܂��傤���Č���������Ȃ��ł����v�Ƃ��������������Ă������ł����A�܂��d���Ȃ����ƂƎ����Ŏ�����[�������Ă��܂��B
�@���N���炢�O�܂ŁA�ސE��������A12����2�y�j���́A�Ћ˃[�~�����W�܂�������čs�������ƌ����Ă����悤�ȋC�����܂����A�܂��߂ɍl����Ɠ�����ȂƂ����C�����Ă��܂��B����15�N�قǂ�120������͓̂�����O�ŁA140������N�������������킯�ł����A������Ƃ������Ȃ��ɁA���N���̐l����3���Ԋy���܂���͓̂���Ǝv���܂��B���܂łł��Ă����̂́A��͂�V�[�~�������āA��������}���邽�߂Ɍ���3�������w�N�ƂȂ��Ċ撣���Ċ������Ƃ����p�^�[��������������ł��B�ސE��A�����[�~�������Ȃ����ŁA100�l����l�������y���܂���͍̂���ł��B�܂��ł����N�͖����ł����܂ɂ͂�肽���ȂƂ͎v���܂��B�u�Ê�̏W���v�����Ɛ������������c�Ƃ��Č����ɉ^�c���Ă���āA150�����̋����q���W�܂��Ă��ꂽ�̂ł�����A�����l�^������ΏW�܂�邩�ȂƂ������҂͂��Ă��܂��B�Ƃ肠�����́A���N3���̍ŏI�u�`�Ɓu�ɂ��މ�v�ł��B�ߋ��ꂽ������̋����q�������W�܂��Ă����̂ł͂Ɗy���݂ɂ��Ă��܂��B
![]()
��1074���i�Q�O�Q�T�D�P�Q�D�P�Q�j���_��AI�Ȃ̂��ȁH
�@���̎����͕Ћ˃[�~�ł́A�[�~�����_��o�����ŁA��T���点�����Ƒ��_�ɐԂ����Ă��܂����A���̉ߒ��łȂ��N�܂łƈႤ�ȂƊ����Ă��邱�Ƃ�����܂��B����́A���_�̏o�����\�z�ȏ�ɂ悢���Ƃł��B�������A�Ō�̃[�~���ł���31�������D�G���Ƃ������߂����肦�Ȃ��͂Ȃ��ł����A�ǂ����ǂ�ł���ƁA���ꂾ���̗��j�I���ۂɊւ��鐳�m�Ȕc���E�Љ��A����Ȍ�b�́E�\���͂������Ă���Ƃ͓����̌������猩�Ă�����ƐM�����Ȃ��Ƃ������_�����{������܂��B�������A����܂ł��T�C�g����̃R�s�y�Ƃ��͂�����ł��������̂ł����A�����͂����ɂ��R�s�y���܂����Ƃ������������肠��o�Ă��āA�܂��g���Ȃ�g���Ă���������ǁA����������Ə��Ɏg��Ȃ��Ƃ��߂���Ƃ����A�h�o�C�X�����Ă������̂ł����A���N�̑��_�̏ꍇ�͂������Y��ɂł��Ă���̂ł��B������r���ߒ��ŁA�����A�h�o�C�X�����悤�ȓ��e�����܂����荞�܂�Ă����肷��̂ŁA�����܂ł҂����肵���T�C�g���͂Ȃ��̂ł͂Ǝv�킴������܂���B
�@�ƂȂ�ƁA��͂肱����AI����g���Ă���̂��ȂƂ����Ƃ���Ɏv�l���s�������܂��B����AI���g���Ę_�����������肵�����Ƃ͂Ȃ����A���̎g�������悭�킩��Ȃ��̂ł����A�l�X�ȏ���������AI�𗘗p����A���Ȃ莿�̍����_���܂ŏ����Ă��܂��Ƃ������Ƃł��傤���B�Ћ˃[�~�̑��_��24000���ȏ㏑���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł����A���̂��炢�̕��ʂł�AI�͍���Ă��܂��̂ł��傤���B
�@AI���g�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���鑲�_�͕��͂����Ȃ̂ŁA�Ԃ�����Ƃ��낪���Ȃ��ł��B�ȂN���w�����Ă���̂��낤�Ɗ�ȋC�����ɂȂ�܂��B�����Œ�����������A�����Ȃ�ɍl���ď��������_�͐^���ԂɂȂ����肵�Ă��܂����A�����������_�̕����D�������Ă܂��B�������͂���ōŌ�̑��_�w���ł����炢���ł����A���ꂩ���܂��܂����_�w�������Ă����搶���́A����AI���_����������ǂނ��ƂɂȂ�̂ł��傤�ˁB�ނȂ����ł��ˁB
���������A������w���̖������鋳���q���畷�����b�ł́A������̒ʂ��w�Z�ł͓Ǐ����z���̏h�肪�Ȃ��Ȃ��������ł��B�݂��AI���g���ď����Ă��܂�����Ӗ����Ȃ��̂Ŕp�~�ɂȂ����Ƃ̂��Ƃł����B���̂����A���_�������Ȃ��Ă��܂��̂ł��傤���B���_�́A�P�ʂ����炤���߂ɏ������̂ł͂Ȃ��A��w�����Ŏ������g�ɒ������A��蔭���\�́A�f�[�^���W�\�́A�_���I�v�l�́A���͗́A�Љ�w�I�v�l�͂ȂǁA�ǂ��܂łł���悤�ɂȂ��������m�F�����w�w�т̏W�听�Ƃ��ď������̂ł��B��w�Ŋw�Ԃ��Ƃ̈Ӌ`���A�����߂Ė₢�����C�����܂��B
![]()
��1073���i�Q�O�Q�T�D�P�Q�D�W�j�Ⴂ�����̑O���̎��Ӗ�
�@��w������Ă��Ă��A�e���r�����Ă��Ă��A�Ⴂ���������͉����O��������Ă��܂��B�ꌩ����ƁA�ӂ���Ƃ��Ă���悤�Ɍ����܂����A������Ƃ��炢�����Ă��A�قƂ�ǑO���̌`������Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA��������ł߂Ă����ł��傤�ˁB�����Z�b�g����̂͌��\��ςȂ�ł��傤�ˁB30�Α�A40�Α�ł��A�O��������Ă���l����������悤�ł����A��{�I�ɂ͎q��Ă�d���ŖZ�����Ȃ�ƁA�Ȃ��Ȃ��O���Z�b�g�Ɏ��Ԃ����Ȃ��Ȃ�̂��A�������Ɍ���܂��ˁB�܂��A�O���̌��ʂ́u���������邱�Ɓv�ł��傤����A�u�����v�Ƃ�������ɓ����ꂽ���Ȃ��l�́A�O�����͂��Ȃ��̂ł��傤�ˁB
�@�l�b�g��Ńf�[�^��T���Ă݂�ƁA��͂�10�Α�㔼����20�Α�̏��������ɂƂ��āA���C�N�ȏ�ɋC�ɂ��Ă���̂��O�����Ƃ����������ʂ��o�Ă��܂��B���₻����������Ȃ�ł��ˁB�����A���̑O�����ւ̎����͓��{�̎Ⴂ�����ɓ��ɑ����̂ł͂Ȃ����Ƃ����C������̂ł����A�ǂ��ł��傤���B�؍���K-POP�A�C�h���̏��������͂��܂�O��������Ă���Ƃ�����ۂ�����܂���B������K-POP�A�C�h���̏��������͒��������T�C�h��Z���^�[�ŕ����ė����Ă����ۂ�����A���Z�����炢�̔N��̎q�����ł���l���ۂ������܂��B����A���{�̃A�C�h���O���[�v�̏����w�͈��|�I�������O��������Ă���悤�Ɏv���܂��B20�Α�㔼�ł�������O�ɑO��������Ă���悤�Ɏv���܂��B�O���̔��Ɏ��Ă���͂��̓��ł̂��̎Ⴂ���������̔��^�̈Ⴂ�́A��͂蕶���E���l�ς̈Ⴂ�Ȃ̂ł��傤�B
�@�؍��̂��Ƃ͂��܂�悭�m��Ȃ��̂Œu���Ă����Ƃ��āA���{�̎Ⴂ���������͂�͂�u���������邱�Ɓv�������ɂƂ��Ĕ��ɏd�v�ȗv�f���Ǝv���Ă���Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B�������A���������邱�Ƃ́u�c�������邱�Ɓv�ɂ��Ȃ���܂��B�u�������肵�Ă���v�u�d�����ł������v�Ƃ����C���[�W���������锯�^�ł͂Ȃ��ł��B�ߋ��������U��Ԃ��Ă݂�ƁA���{�����Ȃ�L���ɂȂ��Ă��Ĕ��ւ̊S���ǂ�ǂ܂�n�߂�1980�N��͂��߂ɂ́A�u���q�����J�b�g�v��u�Ԃ���q�v�Ƃ������t���A���q�吶�u�[���ƂƂ��ɐ��܂�Ă���A���̍���������O������肽���Ƃ����Ⴂ���������̊�]�����m�ɕ\���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�������A����ɂ���Ắu�����v�ȊO�̂��̂����߂��Ă�����������܂����B1980�N��㔼�̃o�u�����ɂ́A���������O�X�Ƃ��\�o�[�W���Ƃ������s��������������A1990�N��㔼�ɂ̓A�����[��M���������s��A�����̎���́u�����v���u�Z�N�V�[���v�̂悤�Ȃ��̂��O�ʂɏo�Ă����C�����܂��B
�@������������������A�܂��Љ�S�̂Ƃ��Ắu���炵���v�Ƃ���ے肷�鎞��ɂǂ�ǂ�Ȃ��Ă��Ă���ɂ�������炸�A����ɋ߂Â��قǁA���������͉��������锯�^�i�O�����j�ɃG�l���M�[�������Ă����肷��킯�ł��B�u���炵���v�͔ے肷�邯��ǁu�����v�͍m�肷��A����ȎႢ�����������C�����܂����A�����ɂ͂܂����������͂Ȃ��̂ł��傤���B�u���炵���v�ƌ�����ƒP���Ɋ������Ȃ��\�\����2022�N�̑�w�������ł́A�u���炵���v�ƌ����Ċ������Ǝv���l�́A3���������܂���\�\����ǁA�u�����v�ƌ���ꂽ��f���Ɋ������v���̂ł��傤���B���������A�u�J���C�C�v�͐��E�ł����̂܂ܒʗp���錾�t�ɂȂ��Ă���Ƃ����b�����������Ƃ�����܂��B���{�̕����͍���Ⴂ���������Ɍ��������u�J���C�C�v�|�b�v�J���`���[�ő�\����Ă���̂�������܂���B�������A����ȓ��{�͐��E�ł����ƈ�ڒu����鍑�Ȃ̂ł��傤���B�u�J���C�C�v���͂т�����{�̂܂܂ł����̂ł��傤���B
![]()
��1072���i�Q�O�Q�T�D�P�Q�D�P�j�ۑ背�|�[�g���`�h���p
�@����܂ŒS���������ׂĂ̍u�`�ȖڂŊw���̍Ō�Ɏ��������āA��������C���ɐ��ѕ]�������Ă��܂������A���������ŏI�w���ɗB��S�����Ă��闝�_�Љ�w�U�ł͍Ōオ�����Ƃ����̂͂�����ƌ����ȂƎv���A�����������ɖ���̎��Ƃ̊��z�ƃ��|�[�g��2��ۂ��āA����ŕ]�����邱�Ƃɂ��܂����B�ŁA���11��30����o����1��ڂ̃��|�[�g�ۑ���o���܂����B���ꂪ�A���L�̉ۑ�ł��B
�p�D�ЋːV����u���z���v��S�ғǂ�ŁA���̒��ɏo�Ă���o��l������1�l�I�сA���̐l��1972�N����Z�N��̕��������Ă��������B��������ۂɁA����Ƃ̊ւ����������߂ɁA�e�L�X�g�w���a�E�����E�ߘa�̑�w���x�̊����N�\�́y���s��E�u�[���z����1�ȏ�̃L�[���[�h��K���g���č���Ă��������B�Ȃ��A����1�Łi40���~30�s�j�ȓ��ł܂Ƃ߂Ă��������B
�@��300�������Ă���܂������A�ǂ�ł�����A�قƂ�ǂ̊w�����`�h���g�����ȂƂ������Ƃ��悭�킩��܂����B�`�h�͕�����Ȃ��Ȃ����ɍ���Ă���܂����A�܂�������������ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�ł��B���̏�A���̎���̗��s���u�[���ɂ��Ă����ɓI�m�Ɏg�p���Ă���܂��B�����t�ɁA���܂�ɂ����s��Ȃǂ�I�m�Ɏg���Ă���̂ŁA���̎���ɐ��܂�Ă��Ȃ���w���������܂ŗ������Ă���͂��͂Ȃ��̂ŁA�`�h�쐬���ȂƂ킩���Ă��܂��܂��B�܂��A����̎d�����Â������̂ł��傤���A����ł��܂����o��l���̖����̕�����������A�܂������o�ꂵ�Ȃ��l���̕�����o�����l�����āA�ǂ���玄�̍��������͂܂������ǂ܂��ɁA���S�ɂ`�h�Ɋۓ��������ȂƂ킩���Ă��܂��܂��B
�@�����Ɠo��l���������őI�сA���N��ɂ��邩�����߂āA���̎����̗��s���u�[�����܂݂���ŕ�������悤�Ɏw�����o���ƁA���Ȃ肢�����܂ōs���܂����A������`�h�ɑS���ǂݍ��܂��Ă��A�e�o��l���̔c���̓p�[�t�F�N�g�ɂ͍s���Ȃ��悤�ł��B�N�����Ă�����A�������N���������̔c�����s���m��������A���̏�ɒN�������̂��ȂǁA���Ȃ�s���m�ȔF���̂��Ƃɕ��������Ă��܂��B�������g�ł����ƕ����ǂ�ł��āAAI�̃~�X�������Ē����o������A�`�h���g�������Ƃ����Ȃ�B���܂����A�����܂ł����Ƃł��Ă���l�͏��Ȃ������ł����B
�@�����܂ł`�h���i�����Ă�����A�g���ȂƂ����̂����͂△���Ȋ���������̂ŁA�����ɏ��Ɏg�����Ƃ����i�K�Ȃ̂ł��傤�ˁB���l���A���ɖʔ������������Ă��ꂽ�l������̂ł����A�����炭�`�h���g���Ă��A�����Ȃ�ɃA�����W�������Ƃł����l�����ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����A�ǂ��ł��傤���B���́u���ʐM�v��ǂ�ł��ꂽ���ŁA�������N������A���Џ�L�̉ۑ������Ă݂āA���̌��ʂ������Ă��������B�`�h���g������ǂ��܂ł��炵�����ꂪ�ł���̂��A�������ɊS������܂��̂ŁB
![]()
��1071���i�Q�O�Q�T�D�P�P�D�Q�S�j���тƃE�N���C�i
�@��B�ꏊ�͈��т̗D���ŏI���܂����B��֏��i���m���ƂȂ�A���ꂩ��܂��܂��l�C���o�Ă��邱�Ƃł��傤�B�֑�Ƃ̂Ȃ��������A���͓���O���炻�̑��݂�m���Ă���A���m���D��������2�N�O�̋�B�ꏊ��ɂ��łɈ��тɂ��Ă͐G��Ă��܂��i�Q�ƁF��931���@�ߘa5�N��B�ꏊ�����i�Q�O�Q�R�D�P�P�D�Q�U�j�j�B���̌�������ƒ��ڂ��Ă��܂������A���̗\�z���͂邩�ɒ����鏸�i�Ԃ�ŁA�܂������m���D������킸��2�N��ɑ�ւ����ނƂ͑z�������Ă��܂���ł����B���������܂��B�����Ƃ��̂܂����Ɏ��͂����ĉ��j�ɂ��Ȃ��Ă����̂ł��傤�B
�@���āA�������т̑��o�̘b�����������Ȃ��u�Ђ̕x�m�R�����v�ŏ����������ƂȂ̂ŁA�v���Ԃ�Ɂu���ʐM�v�̕��ɏ������Ǝv�����̂́A���т̗D�����E�N���C�i���{�⍑���͂ǂ������Ă���̂��낤���Ƃ������Ƃ��C�ɂȂ�������ł��B�告�o�ŃE�N���C�i����D���͎m���o���̂͏��߂ĂȂ̂ł�����A�ʏ�Ȃ�E�N���C�i��g�Ƃ�����т̐���`����Ƃ������Ă��ǂ������ȂƂ���ł����A�����_�ł̓E�N���C�i��g�ق́A��ؔ������Ă��܂���B���т̕����D���C���^�r���[�₻�̌�̃C���^�r���[�ł��A�ꍑ�E�E�N���C�i�̂��Ƃɂ͈�ؐG��Ă��܂���B�����e�ɂ͘A�������悤�ł����A�A�A
�@�Ȃ�����Ȃɗ₽���W�ɂȂ��Ă��邩�ƌ����A��͂荡�E�N���C�i���푈�����Ƃ������Ƃł��傤�B���т́A���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U���n�܂���2022�N4���ɃE�N���C�i���o�����{�ɂ���Ă��܂����B�E�N���C�i�ł͐푈�J�n���2022�N2���ɁA18����60�̒j���̏o�����֎~���܂����B���т��E�N���C�i��E�o�����̂�4���ł�����A���̋֎~�߂����ē��{�ɗ������ƂɂȂ�܂��B�ނ�2004�N3�����܂�Ȃ̂ł��傤��18�ɂȂ�������ł����B�}�ɐ푈���n�܂�A18�Βj�q�͍����o��Ȃƌ����Ă��f���ɏ]�������͂Ȃ������ł��傤�B���ɁA�q�ǂ��̎�������{�̑告�o�̐��E�Ŋ��邱�Ƃ��Ă������тɂƂ��āA�����߉��̏o���֎~�͂Ƃ��Ă��]������̂ł͂Ȃ������ł��傤�B����͌����Ĉ��т����̘b�ł͂Ȃ��A�E�N���C�i���獑�O�ɒE�o������҂͉����l������悤�ł��B�Ȃ��A���т�18�ɂȂ钼�O�ɏo�������Ƃ�����������悤�ł��B3��23�����܂�ʼnƑ��̓h�C�c�ɂ���悤�ł��̂ŁA18�ɂȂ�O�ɂ�������h�C�c�ɍs���A���̌���{�ɗ����̂�������܂���B�������A������ɂ���푈�ɃE�N���C�i����E�o�����Ƃ���������߂����̂悤�Ȃ��̂́A�ǂ���ɂ��날��ł��傤�B
�@���������o�܂�����̂ŁA���т��E�N���C�i�̂��Ƃ����Ȃ����A�E�N���C�i���{����g�ق������������Ȃ��킯�ł��B�E�N���C�i�������]���͗l�X�ł��傤�B�E�C�Â���ꂽ�Ǝv���l�����邩������܂��A�v���A���l���A���q�����̂��߂ɐ킢���𗎂Ƃ����Ƃ����o�������Ă���l�����ł���A�u���͍����o���čD���Ȑ��E�Ŋ���ł��āA�S�͒ɂ܂Ȃ��̂����H�v�ƌ��������l�����Ȃ��Ȃ��C�����܂��B���Ȃ݂ɁA�E�N���C�i�͍��������x���̗p���Ă���A�j����25�ɂȂ�Ɠ�������邻���ł��B�����3�N4�J���قǃ��V�A�Ƃ̐푈�������Ă�����A���т͒�������邱�ƂɂȂ邩������܂���B�i�����A�����E�N���C�i�o�g�ł��鎂�q�͂��ł�28�ł����A���̂܂ܑ��o����葱���Ă���̂ŁA���v�Ȃ̂�������܂��B�j���̍��A���j�ɂȂ��Ă���\���͂������ɂ���܂����A���j������������ɑ�����Ȃ�Ă��Ƃ��\���Ƃ��Ă͂��肤��킯�ł��B���đ�2�����E��풆�ɁA�����̖��X�|�[�c�I�肪���ɎU�����Ƃ�������������܂����A���тɂ͐����Ȃ��ƂɂȂ��Ăق�������܂���B�����Ȃ�Ȃ����߂ɂ́A�푈���I���̂���Ԃł����A�����I���悤�Ƃ���Ȃ�A�E�N���C�i�͓���̗̓y�����V�A�ɂ��Ȃ�D���邱�ƂɂȂ�ł��傤�B��������ۂ���Ȃ�A�푈�͒������܂��B���т������Ă���Ȃ��̂������Ƃ����l���������܂����A���������E�N���C�i�̏��l����Ȃ�A���̔ނ͐S�������C�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B���ׂėǂ��`�Ŕ[�܂��āA���т��S��������������Ƃ����ȂƎv���Ă��܂��B
![]()
��1070���i�Q�O�Q�T�D�P�P�D�T�j���h���u�����v���ʔ���
�@�����̒��h���u�����v�ɂǂ�ǂ�͂܂��Ă��Ă��܂��B�n�܂�O�́A�剉���D�̍������肳��Ƃ����l�����܂�悭�m�炸�A����قǖ��͂������Ȃ����������N���Ȃ��Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B���j��̎��݂̐l�������f���ɂ������h���͊�{�I�ɊS������̂ł����A����̏��_�Ƃ��̍Ȃ����f���ɂ����b�Ȃ�A��NHK�h���}�Łu���{�̖ʉe�v�Ƃ������삪����A���̎��ɔ��_�̍Ȃ��������h�ӂ݂���̑^�X�Ƃ�����������������ۂɎc���Ă���A�������肳��ł͂��̕��͋C�̑����ɂ��y�Ȃ����낤�Ǝv���A�܂��������҂��Ă��܂���ł����B�������A�܂��Ƃ肠����������ƌ��Ă݂悤���Ǝv�����n�߂���A�u���{�̖ʉe�v�Ƃ͂܂������Ⴄ��ۂ̃h���}�ɂȂ��Ă��āA�ǂ�ǂ��������Ă��܂����B
�@��l���̃g�L�����͏���Ƃ̎��q�ł͂Ȃ��������Ƃ�A��v���������ƂȂǂ͎j���̂悤�ł����A�ׂ����Ƃ���͋r�{�ƂƐ��쑤�ő��k���ĕ��������Ă���̂ł��傤�B���ɂ��܂��ł��B����A�����͂ǂ��Ȃ�̂��낤�ƋC�ɂȂ���ɂȂ��Ă��܂��B����́A���Y���̂Ȃ݂��w�u���̏����ɂ���Ȃ茈�܂�Ȃ������悤���Ƃ����I�����ŁA�Ȃ�ł��낤�Ǝv�킹�A�����̓g�L�̎���Ŗ��Ƃ̂���l�������k��i�q������J�����^�G������ɂȂ��Ă���Ƃ�����ʂŏI���܂����B�u���[�[�A���ꂩ��ǂ��Ȃ�́H�v�ƁA�܂������������Ȃ��ȂƂ����C�����ɂȂ�܂����B���g�L�����ۂ��Ă���w�u���̏����ɂȂ�b���A���̉J�����Ƃ̋ꋫ���~�����߂Ƃ������W�J������̂��ȂƁA���낢��l�������Ȃ�܂��B�v���Ԃ�ɂ��Ȃ�͂܂肻���Ȓ��h���ł��B
![]()
��1069���i�Q�O�Q�T�D�P�P�D�R�j���炵���킢�ł���
�@�h�W���[�X�����[���h�V���[�Y�A�e���܂����ˁB����̎������������ł������A7�����������̂��鎎������ł����B����Ȃɖ싅��^���Ɍ����̂́A�����ē���̋��l��ȗ��Ȃ̂ŁA25�N�Ԃ肭�炢�ł����B���[���h�V���[�Y�����łȂ��A�n��V���[�Y��[�O�`�����s�I���V���[�Y���܂߂āA�h�W���[�X�̃|�X�g�V�[�Y���̎����͖{���ɖʔ��������ł��B
�u�����[�Y�Ƃ̑�4��̑�J�̓���Ƃ���10�O�U�A�Ŏ҂Ƃ���3�{�ۑłȂ�Ă������Ȃ��Ǝv���Ă�����A���[���h�V���[�Y�̑�3��ł͉���18��܂Ō����������A��J��2�{�ۑŁA2��ۑł̌�́A5�l���Ə������Ă��炦�Ȃ��Ƃ����M�����Ȃ��L�^���o���A��͂��J��������Ǝv���܂������A�R�{�̃V���[�Y�ɂȂ�܂����ˁB3���͂��������܂��B���ɍ���̎����́A���̃|�X�g�V�[�Y���̖��͂����ׂċl�܂��Ă��܂����ˁB
��3���ő�J�攭�ł������A��ꂪ���܂��Ă����̂��A�����ɃR���g���[�������肹���A�X���[�����z�[��������ł���A3�_�̃r�n�C���h��w�����A1�_���܂Ŕ�����5��ɂ܂�1�_���Ԃ���A2�_���̂܂�8����}���A��5��ōU��������Ȃ������C�F�T�y�[�W�������Ă����̂ŁA2�_����ǂ����̂͌��������ȂƎv���Ȃ��猩�Ă��܂������A�}���V�[���\���z�[��������ł���1�_���ɂȂ�A�ǂ����ΎR�{�̓o�����邩���Ǝv���Č��Ă��܂����B�����āA����9��\�Ƀ��n�X�ɓ��_�z�[����������яo���A���̗��ɃX�l�����s���`�����������߂ɁA���ɎR�{�̓o��ƂȂ�܂����B
�R�{�́A�������P�l�ڂ̃o�b�^�[�Ɏ�����^��1�����ۂƂȂ�A���̃o�b�^�[�̋����Z�J���h�S�������n�X�����܂��������A����ǂ������ł����A�{�ۂŃz�[�X�A�E�g�B���̑ŋ��͔����Ă�����A�����~�X���N���Ă����������Ȃ��s��������ł����̂ŁA���n�X�̉B�ꂽ�t�@�C���v���[�ł����B�����āA���������̎��̃o�b�^�[�̍����Ԃ̑傫�ȓ���������t�g�ƌ������Ȃ���A���̉�Z���^�[�̎���ł߂ɓ����Ă����p�w�X���M���M���ŕߋ�����Ƃ����r�b�O�v���[�ł����B��������ʂȂ甲���Ă��Ă����������Ȃ�������ł����B
11��\�A�X�~�X�̃\���z�[�������ł��Ƀh�W���[�X�����[�h���A11���R�{���}�����킯�ł����A������擪�̃Q���[���E�W���j�A����ۑł�����A���̌�P���P�C�R�ۂ̃s���`�ɂȂ�A�ǂ��Ȃ�̂��낤�ƃn���n��������ꂽ��ŁA�Ō�̓_�u���v���[�Ŏ����I���ƂȂ����킯�ł��B�܂��Ɏ�Ɋ����鎎���ł����B
�R�{�̓V���[�Y3���ł����瓖�RMVP�ɒl���܂����A�l�I�ɂ̓Z�J���h�E���n�X�̎���ł̊��傫�������ȂƎv���܂����B����̑�7�킾���łȂ��A�����̑�6��̍Ō�̃Z�J���h�_�u���v���[���A�L�P�E�w���i���f�X�̑����̓V���[�g�o�E���h�������̂ŁA�ߋ��̓���v���[�ł����B���n�X���V���[�Y�őł����q�b�g�́A��7���9��̓��_�z�[������1�{�����������悤�ł����A������܂߂�A���n�X�̊���Ȃ����Ă͏������Ȃ������h���������Ƃ����C�����܂��B���ɂ��A�}���V�[�A�L�P�E�w���i���f�X�A�X�~�X�Ȃǂ��Ԃ���̊���������I�肪�������āA���̃V���[�Y�Ŋo���Ă��܂��܂����B���{�ł́A��J�A�R�{�A���X���肪���ڂ���Ă��܂����A�|�X�g�V�[�Y���̃h�W���[�X�̎������قڂ��ׂČ��Ă����l�ԂƂ��ẮA�h�W���[�X�͍D�I�肪�����������`�[�����ȂƂ��݂��ݎv���܂����B
![]()
��1068���i�Q�O�Q�T�D�P�P�D�P�j�Â���10��31���ł�����
�@���10��31���̓n���E�B���̓��ŁA��N�a�J�Ȃǂ̔ɉ؊X�ŁA�������������̎�҂�����A���낢�뎖�����N�����肷��̂ŁA���N�������N���邩�ȂƎv���āA�j���[�X�������낢��T���Č��Ă��܂������A����͂���Ƃ����������͋N���Ȃ����������łȂ��A�������ĊX�������҂����ɏ��Ȃ������悤�ł��ˁB�ő�̌����́A��s�s���𒆐S�ɗ₽���J�����Ȃ�{�i�I�ɍ~���Ă������Ƃł��傤�B�n���E�B�������ɏa�J�ʼnJ���~��̂́A30���N�Ԃ�Ƃǂ����̃j���[�X�ł���Ă��܂����B�m���ɁA�J�ł͉����ł͂��Ⴎ�C�ɂ͂Ȃ�Ȃ������ł��傤�ˁB�j���[�X�ł́A�����^�����[������āA����3�l�Ńn���E�B�����߂����Ƃ����l�������C���^�r���[���Ă��܂����B���͌x�@��n�����X�X�Ȃǂ̊Ď����������Ȃ��Ă��Ă��܂����A������Ƃ͂��Ⴌ�������肵����A���̓����SNS�ɃA�b�v����āA�����Ƃ������Ƃ������N����̂ŁA���̗ǂ��F�B�Ƃ����W�܂��Ċy�������Ƃ����C�ɂȂ�l������̂�������܂���ˁB�����A�n���E�B���̖��͂́A����퐫������ԂŊy���ނƂ���ɂ���̂ł��傤����A�����^�����[���łƂ����̂͊y���ݕ��Ƃ��Ă͒n�������āA���������`�����܂蕁�y���Ȃ������ł��B���N�V�C���悢10��31�����}������A�܂��X�ɂ͂���Ȃ�ɉ���������҂������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���Ȃ݂ɁA���ł͑O����10��30���ɍ�_�̓��{�V���[�Y�s�ނ����܂�A������e���V�����������Ă����C�����܂��B�������g�́A�n���E�B���ɂ���_�̏��s�ɂ��قƂ�Nj����S�͂Ȃ��̂ł����A�Ȃ��N�͖��ɐÂ���10��31���������Ȃ��Ƃ����C�������̂ŁA�Y��Ȃ����߂ɋL�^���Ă������Ƃɂ��܂����B
![]()
��1067���i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�R�O�j��Օێ�w�ł͂Ȃ��u�����ێ�w�v�ɒ��ڂ��ׂ�
�@���s���t�����ɍ����x�����Ă��܂��B�ǂ̐���ł��x�����������ł����A���ɍ����̂�30�Α�ȉ��̎Ⴂ�w�ł��B���s�����ɂȂ�A��Օێ�w�̎x�����߂��Ă���ƌ����Ă��܂������A����ȏ�ɖ߂��Ă����̂́A���{���t���ォ�炻�̑��݂����X�ɖ��m�ɂȂ��Ă����u�����ێ�w�v�Ȃ̂��Ǝv���܂��B���̑w�̓����́A���{���L���ɂȂ��Ă�������␢�E���玹�i���ꂽ�����m�炸�A��؋C���̓��{�����m�炸�A���剻���Ă���������|�ꌙ�����A���{�l�Ƃ��Ẵv���C�h�����������ƐS�Ђ����ɂ������v���Ă���w�ł��B��Օێ�w�̂悤�ɁA���匛�@����A�j�n�V�c���ێ��A�`���I�Ƒ��ςȂǂ̉��l�ς��������莝���Ă���킯�ł͂���܂���B�܂��A��Օێ�w���V����}�X���f�B�A����̏����d�����Ă���̂ɑ��A�����ێ�w��SNS����̏��ɉe�������w�ł��B�ÏL�����_�T���Ǝv���A�V�N�ȕ��͋C�Ɏ䂩��郀�[�h�ɗ�����₷���w�ł��B����́A���̏��������ł���܂łɌ����Ȃ������悤�Ȗ��邢��C����g�����v�Ƃ����܂�����_����������V�N�ȑ�����b�Ƃ�����ۂŁA���̑w�̎x���Ă��܂����A�ÏL���V�N���̂Ȃ�������b�ł���A��������}��Q���}�Ɏx�����ڂ��w�ł��B���s���c�����́A�p�t�H�[�}���X���łȂ��Ȃ������̂ŁA���炭�͍��s���t�̍��x�����ƁA���̍��s���ق������鎩���}�ɑ���x�����߂��Ă������ł��B�����炭���N�ɂ͍s����ł��낤�O�c�@�I���ł́A���̕����ێ�w�̍��s�����[�������������Ǝv���܂��̂ŁA�����}���P�Ɖߔ��������߂����낤�Ǝv���܂��B����̑I���́A���̕����ێ�w�̎x��������Ƃ��낪���Ƃ������Ƃ����������ł��B
![]()
��1066���i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�P�W�j26�N�O�̎咣�����߂Ă�����
�@�ېV�̉�����}�Ƃ̘A�������ɁA�ˑR�A����c���̒萔�팸���Ώ������ƌ����n�߂܂����B�������Ƃ��ƍ���c���͖��ʂɑ�������Ǝv���Ă��܂����̂ŁA�萔�팸�͑�g�Ƃ��Ă͎^���ł����A���̈ېV�̈ẮA�O�c�@�̔���\��50�c�ȍ팸����Ƃ����Ăł��̂ŁA����ɂ͎^�����������ł��B����26�N�O�ɒ�Ă������́i�u�j�r���ʐM�v��11���@���{�c��x���v�����i�P�X�X�X�D�P�Q�D�P�X�j�j�̕����A���{�̐����ɂ͍����Ă���͂��ł��B�킴�킴�N���b�N���ēǂ�ł����l�����Ȃ���������܂���A���̗v�|���������ɏ����Ă����܂��B
�@�O�c�@�Ɋւ��Ă͏��I��������ׂĂȂ����āA�S��1��300�c�Ȃ̔���\�݂̂Ƃ��܂��B���̂悤�ɑ��l�Ȏ���ɂ����ẮA���̕������낢��Ȉӌ����z���グ����͂��ł��B���Ԃ�A�ߔ����̋c�Ȃ����鐭�}�͂Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA�A�����K�v�ɂȂ�܂����A���͂��������`�̕��������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ЂƂA�����Œ�Ă��Ă���̂́A���I�����������n���̐��͂ǂ�����ďE���̂��Ƃ��������o��Ǝv���̂ŁA�Q�c�@��p�~���Ēn����\�҉�c�Ƃ������̂�ݒu�����炢���Ƃ����Ăł��B���̉��v���i�߂A���݂̏O�c�@465���{�Q�c�@248����713������킸��300���ɍ���c�������点�܂��B�܂�����v�Ȃ̂ŁA���ۂɂ͎����͓���Ǝv���܂����A���̈ېV�̈��Ղȍ��N�̔N���܂łɍ팸����ƌ����Ă�����A����\�̒萔�팸�����Ȃ��A����͍��̗L���҂̖]�ތ`�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�Ƃ肠�����ېV����荞�݂��������}�͎����Ƃ����|�[�Y��������̂�������Ȃ��ł����A��}���݂�Ȕ�����̂ŁA�T�d�Ɍ������܂��傤�Ƃ������ƂɂȂ��āA���lj����ς��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��������10�c�Ȃ��炢��������̒萔�����炷�Ƃ��������x�̂Ƃ���ł�����������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�c�������炷�̂����ʂȂ������g�킹�Ȃ��L���ȕ��@���Ƌg�����͌����Ă��܂����A����Ȃ琭�}�������̔p�~�̕������킩��₷���Ă����ł��B���͊�ƁE�c�̌����Ȃ���ɂ������Ǝv���Ă��܂��B�ނ���A�ŋ��𐭓}�ɔz��ȂƎv���Ă��܂��B�L�\�Ȑ����Ƃ�}�ɓ����������Ƃ����l��c�̂�����͎̂��{��`�Љ�ł͓�����O�̂��Ƃł��傤�B�o��������������A����ł����Ǝv���Ă��܂��̂ŁA���̓_�ł͎����}�Ăł��ˁB�������A���}�������̔p�~���O��ł��̂ŁA�����}�Ƃ͂������傫���Ⴂ�܂����B
![]()
��1065���i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�P�R�j�g������A����������
�@�{���ő�㖜�����I���ł��B���̃e���r�ǂ͂ǂ��̋ǂ��A�i�E���T�[��X�^�b�t�����ɑ���A���ꂩ��̒��p������Ă��܂����B����Ȓ��ŁA�m�g�j�͌ߌ�ɍs��ꂽ�n���ȕ�̗l�q��������Ă��܂����B�ŁA���̕�̋g�����{�m�������Ɋi�D�ǂ������ł��B�H�{�a���A�Δj�������͂��߉��l���̐l���X�s�[�`�����܂������A�݂�Ȍ��e��ǂރX�s�[�`�������̂ł����A�Ȃ�Ƌg������͂�����l�A5���قǂ̃X�s�[�`����،��e�������ɓ��X�ƃX�s�[�`���܂����B�H�{�a���v�Ȃ̂��ՐȂɑ��銴�ӂ��܂��q�ׂ���A1���l�̑�ォ��n�܂�A�Ă̓��̃u���[�C���p���X�A�剮������̗[���ƁA��ۂɎc����i���Ă���l�̔]���ɑh�点����A�l�X�Ȍ`�Ŗ����^�c�Ɋւ�����l�X�ւ̊��ӂ�6�O���[�v�ɕ����ďq�ׁA�Ō�́u�܂��������{�Ŗ��������܂��傤�I�v�ƒ��߂�����܂����B���Ɍ����ł����B���������q�̌������ł̃X�s�[�`�͌��e�������ɒ��邱�Ƃ������̒��ł̑厖�ȃ��[���Ɖۂ��Ă��܂��̂ŁA�u�g������A�悭�킩���B���̕����X�s�[�`���͂���ˁv�ƌ��������Ȃ�܂����B�������A�����������͂邩�ɑ傫�ȍ��ۓI����ł�����A�ْ������A�Ԉ�����茾���Y�ꂽ�肵�����ςȂ̂ŁA���̐l���������e��p�ӂ��ǂ͓̂��R�̑I�����Ǝv���܂��B�g������͂���������Ă����A���Ɏ������������著��Ȃ���̓��X����X�s�[�`�ł����B
�j���[�X���Ŕނ̃X�s�[�`��S���Љ�邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤���A�m�g�j�{��������l�͂��Е�����Ă݂Ă��������B�v�킸�A�g������A����������b�ɂȂ��Ă���Ȃ����ȂƎv���܂���B�܂��ł������炭�͂��������͖K��Ȃ��Ƃ͎v���܂����B�����͂Ƃ������A��㖜���̐����Ƌg����\�̑u�₩�����������A���̑I���͈ېV�̉����������ł��傤�B���܉������������O�A�����Y��������A�g������̕������������ېV�̉�͋����ł��B�S����ł͂Ȃ��̂ŁA�������}�E�ېV�̉�Ƃ��Ă̐L�т͌������ł����A�g���m�����́A���A���{�ň�ԗǎ��Ȑ����ƂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ł��A���s�\�z�͂�߂����������ł��B�������{�Ƒ��s�ƍ�s���ېV�̎ʼn������Ĉӎv�a�ʂ��}��₷���Ȃ��Ă��āA���̌��ʂƂ��đ�㖜���Ƃ����r�b�O�C�x���g���ł����̂ł�����A���s���߂����Ӗ����܂����������ł��܂���B���ʂ�3�x�ڂ̓s�\�z���߂����Z�����[�Ƃ�����ĕ�������A�܂��ӔC����ċg������߂�Ƃ������ƂɂȂ肩�˂܂���B���s�ɂȂ��ĉ����ǂ��Ȃ�̂��A���s���̒N�������ł��Ă��܂���B����s�ɂȂ邽�߂ɂ͓s�ɂ���K�v������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��g������A�ǂ����Ō����Ă����悤�ȋC�����܂����A����s�Ƃ����̂���̂ǂ�قǂ̈Ӗ�������̂����悭�킩��܂���B���O��������s�ɂȂ��Ă��A��s�@�\�ړ]�����ۂɍs���Ȃ�����̑��s�ƂقƂ�lj����ς��Ȃ��ł��傤�B��s�@�\�͂ǂ�ǂ�ړ]���ׂ��ł����A��ゾ���łȂ��l�X�Ȓn���ɕ��U������ׂ��ł��B���{�̑�s�s�\�\���ɓ����\�\�̉ߖ��ƒn���̉ߑa�����P���邽�߂ɂ́A����s�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�e�n�ɍ������ɏW�����Ă��銯�������ړ]���A�����ꏊ�����A���y�̗L�����p���l����ׂ��Ȃ̂ł��B
�啪�b���L����߂��܂����ˁB�������A�g���m���Ƃ����D�ꂽ�����Ƃ��������Ă������߂ɂ͖��ʂȎd���͂��Ă����Ȃ����������̂ŁA���q�ׂ����Ȃ��Ă��܂��܂����B
![]()
��1064���i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�P�P�j�����}�̘A�����E���獡��̐��ǂ�\������
�@�����}��26�N�p�����������}�Ƃ̋��͊W�𔒎��ɖ߂��܂����B���́A���Ƃ��Ǝ����A���͐����I�ɍ����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����A���̂܂܂ł͌����}�̑��݈Ӌ`�͂Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����ƁA���́u���ʐM�v�ɂ����������Ƃ�����܂��i��628���@�����}�̑��݈Ӌ`��₤�i�Q�O�P�V�D�U�D�P�U�j�j�̂ŁA�悤�₭���̓����������Ǝv���܂������A�����Ɍ����}�����̖�}�Ǝ��g�ނ��Ƃ��ł��Ȃ��ł��傤����A�����̂ǂ̂悤�Ȑ����̐��ɂȂ��Ă����̂������ׂƂ��������ł��B�������A���ɋ����[���ł�����܂����A����̐��ǂ�\�����Ă݂����Ǝv���܂��B
�@�����Ƀg�����v���K�����邱�Ƃ����܂��Ă��܂����A�����}���قłȂ��Ȃ����Δj�����܂ł������ɂ��Ă����킯�ɂ������Ȃ��̂ł�����A�x���Ƃ��ė��T�̂͂��߂ɂ́A������b�w���̂��߂̍���J�����͂��ł��B�����܂ł̎��Ԃ͖�1�T�Ԃقǂł��B���̊ԐV���ȘA�����������߂����āA�����}�����̐��}���F�X�ȓ���������ł��傤���A���Ԃ��Z�����āA�����w���I���܂łɐV���ȘA���̑g�ݍ��킹���o���オ��Ƃ͎v���܂���B�ƂȂ�ƁA���Ǎ��s���c�����I���[�ő��ΓI1�ʂő����Ɍ��܂�Ƃ������ƂɂȂ�̂��Ǝv���܂��B
�@�ߔ����ɑ傫������Ȃ������}�P�Ə����^�}�Ƃ��ē��t����邱�ƂɂȂ�܂����A���܂ł����̏�Ԃł͂������Ȃ��͂��ł�����A���������Ȃ������ɉ��U���I�������s�����͑I�Ԃ��ƂɂȂ�ł��傤�B�K�\�����ł̌��łƕ�\�Z��ʂ�������U�ł��傤�B�N���ɑ��I���Ƃ����\���͂��Ȃ肠�肻���ł��B���������̎����ɏO�c�@�I���ƂȂ�A��}�̑I�����͑̐��͏\���ɂ͂ł��オ��Ȃ��̂ŁA���ׂĂ̐��}�����ꂼ�ꎩ�}�̌����o���키���ƂɂȂ�ł��傤�B�ł��̌��ʂ͂Ƃ����ƁA�����}�̑叟���A�O�c�@�ŒP�Ɖߔ���������Ƃ������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ɨ\�����܂��B�Δj���t����ɑ��̕ێ�I��}�ɕ[�����Ă����w�����Ȃ莩���}�ɖ߂��Ă��܂����A���܂�[�������̂��Ƃ��l�����C���[�W�ŕ[������l�������A�ꋫ�ɒǂ����܂�Ȃ�����撣���Đ���Ă���Ƃ�����ۂ̏��������E���s���c���������Ă����悤�ƕ[�𓊂���͂��ł��̂ŁA�n���w��̕[���Ȃ��Ă����I����͂��Ȃ莩���}�����Ǝv���܂��B��}�������}���܂߂Č���ł���Ώ��Ă�\���͂���܂����A�Z���Ԃł��������I���撲�����ł���Ƃ͎v���܂���B�Ȃ̂ŁA���s�����}�̈����A�����}�P�Ɖߔ����̊m�ۂƂȂ�Ǝv���܂��B��ʗL���҂͌����}��}�X���f�B�A�������قǁu�����ƃJ�l�v�̖��ȂC�ɂ��Ă��܂���B��N�A���N�̍����I���ɕ������̂́A���v�h��W�Ԃ���������������ł��Ȃ����A���ǂǂ��������������Δj�����̖��͂̂Ȃ����傫�������ł��B
�@�������A�O�c�@�����ߔ������m�ۂ��Ă��Q�c�@���ߔ����Ȃ��̂ŁA�V���ȘA��������肪��������{�i�I�Ɏn�܂�Ǝv���܂��B�Q�c�@�̉ߔ����ɓ��B���邽�߂ɂ͎����}��8�c�ȑ���Ȃ������Ȃ̂ŁA�ېV�ł���������ł��ǂ���Ƒg��ł������܂��B���s���c�͈ېV��荑���̕��ɐe�ߊ��������Ă���悤�ł����A�����͐������肷��ƗL���҂̕]���͉�����ł��傤�B�ېV�̕����������肵�Ă��L���҂̕]���͉�����Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA�ېV�̕����A������̉\�����������ȂƂ��v���܂����A�O�c�@�I���̌��ʎ���ł́A�������A������Ƃ����I��������\���͂��肻���ł��B�܂��ł��A���̂�����܂œǂނ̂͂�����Ƒ������܂��ˁB���N���܂łɂǂ�ȓ���������̂����ڂ������Ǝv���܂��B
�y�NjL�i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�P�T�j�z�Ō�̒i���̎����}�̋c�Ȑ��ł����A�Ԉ���Ă��܂����B���݂܂���B�����}�P�Ƃł́A�Q�c�@��101�c�Ȃ����Ȃ��̂ŁA�ߔ����܂�24�c�Ȃ�����܂���ˁB���A�ېV�Ƃ̘A���b���}���ɐi��ł��܂����A�ېV�ƘA�����Ă��O�c�@�ł�2�c�ȁA�Q�c�@�ł�5�c�ȑ���Ȃ��ł��ˁB�����A���s���c�͎Q���}�ɋ��͂��Ăъ|�����悤�ł����A�Q���}�́A�O�c�@3�c�ȁA�Q�c�@16�c�Ȏ����Ă��܂�����A�Q���}���t�O���͂ł����Ă��ꂽ��A�O�Q�Ƃ��Ɏ����A�ېV�A�Q���ʼnߔ��������邱�ƂɂȂ�܂��B�����}�̐헪�I�ɂ͂������낤�ȂƎv���܂��B�����A�Q���}�������}�ɋ��͂��Ă��܂��ƁA���̑I���ł͐L�тȂ��Ȃ肻���ł��̂ŁA���X��X���炢�̑Ή����x�^�[�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂��܂��ǂ��Ȃ邩�ǂݐ�Ȃ��ł��ˁB
![]()
��1063���i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�U�j�ԍ��̎Љ�w
�@4�����̂r�N���畷�����b�ŁA�������ʔ����v�����̂ł����A�{�l�����܂肱���������Ƃ͉����Ȃ��l�Ȃ̂ŁA�����Ď��������Ă݂܂��B�ނ��܂ߐ��l�ň���ł������ɁA�ނ��u�����I�^�N���v�Ƃ����̂ŁA�u�ȂA����́H�v�Ǝv�����̂ł����A�����Ă�����A�Ȃ�قǁA�ʔ����A�ԍ��ɂ͂߂��Ⴍ����Љ�I�Ӗ�������ȂƎv�킳��܂����B
�ŏ��́A��s�̔ԍ��̘b�ł����B�݂��ً�s��1�ԁA�O�HUFJ��s��5�ԁA�O��Z�F��s��9�ԁA�肻�ȋ�s��10�ԁA��ʂ肻�ȋ�s��17�ԂŁA����PayPay��s��33�Ԃł��B�ȉ�41�Ԃ܂ŐV���ȃ^�C�v�̋�s�����сA�n����s��116�Ԉȍ~�Ŗk���犄��U���Ă��܂��B���ɂ��M����s��O����s�Ȃǂ�����܂����A�Ƃ肠����17�Ԃ܂ł�5�����Ȃ��s�s��s���������Ă݂܂��B�܂��A�r���̔ԍ����Ȃ��Ƃ���͌��݊Y����s���Ȃ��ł��B����Ȃɔ����Ă���̂́A��s�̍������i����ł��B���Ƃ��Ɣԍ��͂ǂ����̋�s�Ɋ���U���Ă��܂����B�E�B�L�y�f�B�A�Ɍf�ڂ���Ă������̂��ƁA1�Ԃ͑�ꊩ�Ƌ�s�\�\�����ƑO�͑���s�\�\�A2�Ԃ͎O���s�A3�Ԃ͕x�m��s�A5�Ԃ͎O�H��s�A6�Ԃ͂����Ћ�s�\�\�����ƑO�͋��a��s�\�\�A7�Ԃ͓��{���Ƌ�s�A8�Ԃ͎O�a��s�A9�Ԃ͏Z�F��s�A10�Ԃ͑�a��s�A11�ԓ��C��s�A12�Ԗk�C����B��s�A14�Ԑ_�ˋ�s�A15�ԓ�����s�A16�Ԃ݂��كR�[�|���[�V������s�A17�ԍ�ʂ肻�ȋ�s�A21�ԑ��z��s�A32�ԍ�ʋ�s�ł����B�o�u�������̋�s�������������ŁA�̖̂��O�ł��̂܂ܔԍ��������p���ł���̂́A2002�N�Ƃ����o�u�������ɐݗ����ꂽ��ʂ肻�ȋ�s�����ł��B�܂�20���I�܂ł̓s�s��s�͂��ׂĖ��O���ς���Ă��܂��Ă���Ƃ������Ƃł��B���̒��Ŗʔ����̂́A�O��Z�F��s����9�ԂɂȂ��Ă��邱�Ƃł��B�ԍ��������������j�̌Â��`�������s�ŁA���������ꍇ�͂�菬���Ȕԍ����g���̂���ʓI�ł����A�O��Z�F��s�͂��Ƃ��ƎO���s��2�ԂƂ����`������ԍ��������Ă����̂ɁA�������Ă���͂��Ƃ��ƏZ�F��s�̔ԍ�������9�Ԃ��g���Ă���킯�ł��B���ꂪ�Ӗ����邱�Ƃ́A���̍����͏Z�F�̃C�j�V�A�`�u�Ői�̂��낤�Ƃ������Ƃł��B���Ȃ݂ɁA�O��Z�F��s�̓A���t�@�x�b�g�̏ȗ��`�́ASMBC�ŏZ�F���O�ɗ��Ă��܂��B�Z�F�D�ʂ͂����ɂ��\��Ă���悤�ł��B�܂������[���l�������Ƃ��Ȃ�������s�̔ԍ��ł������A�ԍ���������낢��Ȃ��Ƃ��m���̂��ƋC�Â�����܂����B
�@�n�}�D���̔ނ������Ƃ��M��������̂́A�����̔ԍ��ł������A����̎��ł͂Ƃ��Ă��\�������͂ł��Ȃ��̂ŁA�ڂ����͂�߂Ă����܂����A�����C���Ƃقڈ�v���鍑��1���A���R�z���Ƃقڈ�v���鍑��2���A��B���c�f���鍑��3���œ������玭�����܂ł��܂�����A4���͓�������X�A5���͔��ق���D�y�ƂȂ��Ă��܂��B�����ԍ���58���܂ł�1����2���ŁA���̌��3���ԍ��ɂȂ�܂��B�ԍ��������������Â��Ɍ��߂�ꂽ��v���H�ƌ����܂����A58���͎������s���N�_�œߔe�s���I�_�ł��̋���881.9km�ł����Ƃ����������ɂȂ��Ă��܂��B�������A���̖�7���͊C�̏�Ŏ��ۂ̓��H�͂���܂���B�ł��n�}��ł͂����Ɛ���������Ă��܂��B���ꂪ���{�ɕԊ҂��ꂽ���ɉ���ɂ��s���鍑�������Ȃ���ƒn�}��ň����ꂽ�����������̂ł��傤�B�ԍ����ɍ��������Ă����ƁA�����������ō��y�����W�����Ă������Ǝv�����̂��ȂƂ������Ƃ��Ȃ�ƂȂ��`����Ă��܂��B
���ɂ��A�d�b�ԍ��̌����̑����A�s�O�ǔԂ̕ύX�⊄��U�����ATV�ǂ̃`�����l���ԍ��A�Ԃ̃i���o�[�ɂ��Ă�AJAL123�ւ����ԂɂȂ��Ă��邱�ƂȂǂ��b��ɏo�āA�������ɐ���オ��܂����B�ԍ��Ȃ�ē��������ƍl�������Ƃ��Ȃ������ł����A�ԍ��ɂ͎Љ�I�Ӗ�������A���̔ԍ��ł��邪�䂦�̎Љ�I�e�������낢�날��ƋC�Â�����A����͏\���Љ�w�I�����ΏۂɂȂ�̂ł͂Ƌ����[���v��������ł��B
![]()
��1062���i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�S�j���s���c�����}�V����!!
�@�����}�̐V���قɍ��s���c�����܂�܂����B���������ė\�z�O�ŋ����܂����B���I���[�ɂ͎c�邾�낤�Ǝv���Ă��܂������A�����Ŕs���Ƃ����V�i���I��z�肵�Ă��܂������A�����Ă��܂��܂����B����̏���i���Y�̌o���s���⏬�������A�c���������s���Ɏv�����̂ł��傤�ˁB���I���[�Ɏc���Ă����̂��A����ł͂Ȃ��іF���Ȃ�A���Ԃ�т������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����A�܂������if���l���Ă��d���Ȃ��ł��ˁB
�@���̂܂����ɍs���A���{���̏���������b�ɂ��Ȃ�킯�ł��B���̓���������������������邾�낤�Ƃ͎v���Ă��܂������A���̎����ɍ��s���c�ł��ꂪ��������Ƃ͑z�肵�Ă��܂���ł����B�ǂ�ȓ��t��}�l�����s���̂ł��傤���B���Ƃ��Ɩ��h���̐����Ƃň��{�W�O�Ƃ͋߂�����ǁA���ɂǂ�Ȑ����ƂƋ߂������A���͂悭�m��܂���B���{�W�O�Ǝv�z���߂��Ȃ�A�����{�h�̗����c�������Ƃ��߂��̂�������܂���B����Ӗ��A�ނ�͐����ƂƂ��Ă͗͂̂���l�������̂ŁA���̂������}�l���ł͂��Ȃ�ϋɓI�Ɏg���Ă��邩������܂���B�������͂��ߓ}�O����N�ɂ���̂��ŁA�����͕������������Ă��邩������܂���B
�@�A���̊g����}���ƍ��s���c�͑��ّI�����Ɍ����Ă��܂������A��ԘA���ɓ���C���X���������{�ېV�̉�Ƃ͊��łԂ��荇���W�Ȃ̂ŁA�ېV�̉�̘A������͂��炭�Ȃ��ł��傤�B���̌��ʂ���Ԋ��ł���̂́A��������}�ł��傤�B�ېV���A�����肵�Ă��܂�����A��������}�̑��݊���������Ƃ���ł������A���s�ɑ��ق����܂�A�ېV�Ƃ̋��͂��X���[�Y�ɐi�܂Ȃ���A��������̑��݊��������܂��B�����I�ɂ��A���s���c�ƍ�������}�͐ϋɍ����h�ŁA�Ԏ����̔��s�������Ȃ��l���ň�v���Ă���̂ŁA�������傪���s�����Ƃ悢�W��z���Ƃ����p�^�[������Ԃ��肻���ł��B
�@����ɂ��Ă��A����Ȃɂ��̌�ǂ��Ȃ邩���킩��Ȃ��V���ٌ���͏��߂Ăł��B���U�E���I���ɂ͑ł��ďo��̂ł��傤���B�������I���������ꍇ�A���s�����}�͏��Ă�̂ł��傤���H�����I�ɂ͕ێ狭�d�h�ŏ��������̎x�������܂蓾���Ȃ������Ƃł����A���������Ƃ����V�N���Ō��\�����[�����邩������܂���B�O�c�@�ʼnߔ��������߂�����A���������Ƃ������Ƃ�����̂�������܂���B�ł��A�����Ȃ邩�ǂ����܂������ǂ߂܂���B�Ƃ肠����1�����قǂ͌�����Ă݂����Ǝv���܂��B
�@���Ȃ݂ɁA����i���Y��10�N�ʂ͑��ّI�ɂ͗������ɁA�}������d�v�t�����o�����ďd�݂��������������ł��B���̂܂܂ŁA���ّI�ɏo��������A����������C�����܂��B�Ⴓ�����͂��o���̐A�[�݂̂Ȃ��Ƃ�������ۂɂȂ����Ă��܂��Ă��܂��B���������啨�����o�Ȃ��ƁA���قւ̓��͉����̂�������܂���B
![]()
��1061���i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�R�j��㒁����������
�@�ŋ߂̍��ۏ��e���̐�������Ȃǂ����Ă���ƁA���������Ȃ������ɁA�傫�Ȋ�@���P���ė���̂ł͂Ȃ����Ƃ����v���܂���B���̂������吨�̐l���S���Ȃ����ߎS�ȑ���E��킪�I�������A���E�͂�����x�Ƃ���ȑ�푈���N�����Ȃ��悤�ɂ��悤�Ǝv���A������\�ɂ���悤�Ȏd�g�݂Ɖ��l�ς���낤�Ƃ��Ă��܂����B�������A����͊ȒP�ł͂Ȃ��A�������̎��オ����������G�����̎��Ԃ��N�����肵�܂������A�Ȃ�Ƃ������āA1990�N��ɓ���Ɠ��̗Y�������\�A�����邱�ƂŁA��푈�̊댯�͋������Ƒ����̐l���v�����킯�ł����A���̌�̍��ۏ������ƁA�����ď��ǂ��Ȃ����Ƃ͎v���܂���B�ނ���A�ŋ߂́A�V���Ȑ�O�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ��������オ��n�߂Ă��܂��B
�@���̕|���́A���E�����O���[�v�ɂ܂Ƃ܂����Ƃ����ȏ�ɁA�X�̍����������S��`��ł��o���悤�ɂȂ�A�����̓����ɕ��f��������ނƂ�����d�A�O�d�̑Η��\��������Ă��邱�Ƃł��B���ɁA���E�ŋ����E�A�����J���댯�̑傫�Ȍ���������Ă���̂��|���ł��B����E���O����ŋ����ɂȂ��Ă����A�����J�ł����A�푈�ł���ɑ��ΓI��������߁A�\�A���ɂ݂����Ȃ�����A���E�̌x�@�Ƃ����������ʂ����Ă��܂����B���̖����͋��a�}������������Ă��A����}������������Ă��A�ς�炸�ɂȂ���Ă��܂����B�������A�g�����v���哝�̂ɂȂ��Ă���́u�A�����J�E�t�@�[�X�g�v��ł��o���A�A�����J�̓��ɂȂ�Ȃ����Ƃ͈���Ȃ��Ɛ錾���A����܂ł̃A�����J�̍��ۓI�����ς��܂����B2020�N�̑哝�̑I���ōđI���Ȃ�Ȃ��������́A�A�����J�������ǎ������Ă��ꂽ�Ǝv���܂������A�܂�����2024�N�̈��������͏Ռ��ł����B��x�ڂ�肳��ɂ킪�܂���ɑ哝�̗߂��o���܂����Ă��܂��B���͂�u�A�����J�E�t�@�[�X�g�v�����u�g�����v�E�t�@�[�X�g�v�ɂȂ��Ă���C�����܂��B����ȂɁA��������u�m�[�x�����a�܂������ɗ^����v�Ȃ�Ă����l�Ԃ͌������Ƃ���܂���B����Ȑl�Ƃ��čň��݂����Ȑl�Ԃ��ߔ�����傫��������A�����J�������x������̂ł�����|�����܂��B�܂����a�܂�~������o�ϐl�ł��̂ŁA�g�����v���g�������ɐ��E�����n�߂邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤���A�ނ��g�債���A�����J�����ł̕��f�͔��Ɋ댯�ł��B
�@����E����̋ߑ�Љ�́A�u���R�E�����E�����v�̐��_�ŁA���ۊW�������������^�c���悤�Ƃ��Ă����͂��ł��B�������A����u���R�v���肪��剻���A�u�����v�͌y������A�u�����v�͎�̉����Ă��܂��B�v�z�E�M���̈Ⴂ�ɑ��闝���͐������`�Ői�߂悩�����̂ł����A��剻�������R����𗝉����悤�Ƃ����`�ɂȂ�A���ʂƂ��ĕW�������㉻���Ă��܂��A���̔����Ƃ��Ăǂ��̐�i���ł����d�ȕێ�̎咣����e�����₷�����Ă��܂��B���ɁA���͎�����₷���r�O��`�I�咣�Ƃ��čL�܂����܂��B����͑����Ƃ̐푈���x�����鍑���ӎ����A�ǂ��̐�i���ł����܂���邱�Ƃ��Ӗ����܂��B
�@�����`�̗��z�Ƃ��ꂽ��吭�}���́A�ǂ��̍��ł�������܂��B�L���҂��`�}���a�}��I�ׂāA������オ�N���Ă��x��Ȃ��������s���邽�߂ɂ́A��吭�}�͏d�_�̒u�����͈Ⴄ�ɂ��Ă��A���Ƃ̍������Ȃ��悤�Ȋ�{����͋��L�ł��Ă���K�v������܂��B���f�ł͂Ȃ��A���݊�肪�K�v�ł��B�������A�ŋ߂̊e�����������Ƃ����Ȃ��Ă��܂���B�A�����J�̏ꍇ�͓�吭�}���ǂ�ǂ�Ă����A���̃��[���b�p��������{�ł͓`���I�ȑ吭�}����A�r�O��`��ł��o���悤�ȐV���Ȑ��}���o�Ă��Ďx���҂��}���Ɋg�債�Ă��܂��B�ǂ��̍��̍��������݊����u�������������悯������v�Ƃ����v�l�𑝂�����܂��B
�@�������������������钆�ŁA�ƍٓI�Ȑ����Ƃ��g�b�v�ɗ����Ďw���_��U�邤�킯�ł�����A���邢�����͂Ƃ��Ă��z���ł��܂���B�ɂ�������炸�A�����I���`�Ŋ�@���̔������{�����́u�������v�u�f�����v�Ƃ������ĕ�炵�Ă����ł���ˁB�������N������A�Ƃ肠�����A�����J�ɂ������Ă��悤�Ƃ����l���Ă��Ȃ��̂ł��傤�ˁB�ǂ��Ȃ��ł��傤�ˁA���{�Ɛ��E�̖����́B
![]()
��1060���i�Q�O�Q�T�D�P�O�D�P�j���ǂ��̊w������
�@��w�����Ƃ��Ă̐l�������ɂ��Ɣ��N�ƂȂ�܂����B���Ƃ�������Ԃ����ōl����ƁA����3���������炢�ł��B���̏H�w���̍u�`�́A1���ɃI���j�o�X�̎Љ�w���_��1������2��s���Ƃ����̂͂���܂����A���T�s���̂͗��_�Љ�w�U��1�R�}��������܂���B����ŁA���̎��Ƃ���@����Ōゾ��ƌ��\�G��܂����Ă����������A�Ȃ�Ǝ�u�҂�300�����Ă��܂��܂����B300��������2002�N�x�ȗ��ł��̂ŁA23�N�Ԃ�ł��B�܂��A�Ō�̍u�`�Ȃ̂ŏo�Ȃ����Ȃ����A�e�X�g�����Ȃ��ƊÂ����Ƃ��������̂��A���C�ґ����̍ő�̗��R���Ƃ͎v���܂����A���\�Ȑ��̎Љ�w��U�̊w���������u�Ћː搶�̍Ō�̍u�`�ƕ������̂ŗ��C���悤�Ǝv���܂����v�Ɨ��C���R�������Ă���Ă��܂����̂ŁA�����͂��������ӎ����������w�������������悤�ł��B�Ƃ肠�����A��u���ɂ́u�o�Ȃ͎��Ȃ����A���Ǝ����͑O����LMS�ɃA�b�v����̂ŁA��������邾���ł�����Ƃ����l�͖����ɗ��Ȃ��Ă�����B�{���ɕ����ɗ������l�������Ă��������v�Ɠ`�����̂ŁA�����Ɩ������x�̐l����ɒ��邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ǝv���Ă��܂��B������300���������Ă���ŏ��̍u�`���ł����A���Ă��Ăǂ̂��炢�w������͗���ł��傤���B�ŋ߂̊w�������͂Ƃ肠�������Ƃ͏o����̂Ǝv���Ă���l�������̂ŁA�ӊO�ɑ�����������܂���B
�@�u�`�ƂƂ��Ɉ�������߂Ă���Ă����[�~���c�蔼�N�ł��B������O�ł����A�Ō�̃[�~����4�����ŁA�H�w���͑��_���M�̉����ɓ����Ă��܂��B�Ō�̃[�~�������i31�����j�́A�ʓ|�Ȏq��1�l�����܂���B���Ȃ����Ƃ������ۑ�͂����Ƃ�邵�A���_�ɂ����������Ȃ�ɂ���������g��ł��܂��B9���̘Z�b�ł̑��_���P���h��1�l�̌��Ȏ҂��Ȃ��A���͂�����Ƃ��A�ӂ͍��e����y���݁A�����̒��H�͂����ƑS���H�ׂ܂����B���܂ł̘Z�b�ł́A���݉߂��ċN�����Ȃ��A�����ߑO���̃[�~�͕p�ɂɃg�C���ɋ삯���ސl�����l��������ƁA���낢�날��܂������A31�����͂���ȍ������w����1�l�����܂���ł����B���Ƃ̐S���I�����������Ȃ��Ǝv���l�����ɂ��܂���B�݂�ȁA�������Ă����ɋْ����邱�ƂȂ��A�����b�N�X�����C���ŁA�[�~���ɋ��S�n�ǂ������ɋ��銴�������܂��B��N���l���͂��̂��炢�̎����ɂȂ��Ă����������܂�Ȃ��Ȃ��A�����藧�Ă��l���Ȃ�������Ȃ��Ȃ��Ǝv���āA���l���̐H�����������Ƃ��A���炩�̎��łK�v�����邱�Ƃ����������ł����A���N�͓��ɂ���ȕK�v���������܂���B���t�ɂƂ��āA���肪�����D��������ł��B
�@�ł��Ȃ��A�A�A�ƌ��������Ȃ��Ă��܂���ł���ˁB���ʂ̃[�~��������A����łȂ�̖����Ȃ��ǂ��납�A���炵���[�~���Ƃ������ƂɂȂ�̂�������܂��A�Ћ˃[�~���Ă���ȃ[�~���������Ȃ��ƂȂ₵���v���Ă��܂���ł���ˁB�܂���N�܂ł́A3�A4��2�w�N���āA3��vs.4�̕Ћ˔t�X�|�[�c���Ƃ��[�~�̏W���Ƃ����낢��C�x���g���������̂ŁA���ƈȊO�̏����ꂽ�킯�ł����A���N�͉����Ȃ��ł�����ˁB���̂܂܂��ƁA31�����̏H�w���͂����������_���M�����̃[�~�ɂȂ�܂��B���ƂƂ��Ă͂���ł����̂ł��傤���A�����̃[�~���������āA���ȊO�̂Ƃ���ł����ς��w��ŁA�݂�Ȉ������Ȃ��Ǝv���Ă����̂ŁA���̂܂܂ł́A31�����͕Ћ˃[�~���Ƃ��Ă͕�����Ȃ��o���������Ȃ��܂ܑ��Ƃ��邱�ƂɂȂ肻���ł��B
�@�Ȃw�������̕����炢�낢���悵���肵�Ȃ��̂��ȂƎv���Č�����Ă��܂����A����������C�͐��܂ꂻ�����Ȃ��ł��ˁB5���Ɏ��̒a�������j���Ă��ꂽ���́A�݂�Ȋy�������ɎQ�����Ă���Ă��āA���̎��́A���̐�����31�����͂���1�N���낢��Ȃ��Ƃ���悵�Ă����̂ł͂Ǝv�����̂ł����A����ȗ������Ȃ��ł��ˁB�u�Ê�̏j���v�����ǂ��̊w�N�͒N���Q�����Ă���Ȃ��������A��y�ƈ��܂Ȃ������Ɛ��������Ă��N1�l�Q�������A���T�̃[�~�ł́u���N3���ɍs���ŏI�u�`�͌����w���Ɏ�`���Ăق������Ƃ����邯�ǁA�݂�ȗ��Ă����Ɗ��҂��Ă������̂��ȁv�Ƙb��U���Ă݂��̂ł����A�N1�l�u�s���܂��v�ƌ����Ă���܂���ł����B�Ȃ����������ڗ�������A�����q�ɂȂ��Ă͂܂����݂����Ɏv���Ă��镵�͋C���`����Ă��܂��B����Ȃ��̂Ȃ�ł����˂��B����ꂽ���Ƃ͂�邯��ǁA����Ă����Ȃ��Ă��������ƂȂ���Ȃ��ōς܂��Ă��܂����Ƃ����̂��u��ƃX�}����v���Ƃ����̂͂悭�m���Ă������ł����A�Ћ˃[�~���͂���Ȑl����ł͂Ȃ��Ǝv���āA�u��ƃX�}����v�������Ďw��������Ȃ��Ă�������10�N�قǂ��A�Ȃ�Ƃ�����Ă��āA���ۂ��������l�����N���l���͋��āA����ς�܂��܂����������w���̎d���͂��肾��ȂƎv���Ă��܂������A���N�͂��Ȃ�₵���v���Ă��܂��B���܂�D���ł͂Ȃ���g���g���Ȃ�A��莙�[���̗D���������ɂ���āA���̃[�~�^�c�̎d���͐^�ȂŎ���i�߂���悤�ɖ����s����̂��Ȃ��A�܂����傤�ǍŌ�̔N�����A��������ɍ����Ă��܂����ƈ�����n���ꂽ�����ŁA�c��3�����قǂ��߂������ƂɂȂ�̂�������Ȃ��Ȃ��Ǝv���n�߂Ă��܂��B
�@31�����́A���\���̂g�o��ǂ�ł���Ă���l���������Ȃ̂ŁA�����Ƃ��̕��͂��u����I�v�Ƃ��v���Ȃ���ǂ�ł���Ă���l�����Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂��B�ł����ԂT�ȍ~����Ă��A�݂�ȓǂƂ������ƂɐG�ꂸ�ɍς܂���낤�ȂƎv���܂��B�ł��A���̂g�o���悭�ǂ�ł���Ȃ�A���̎Љ�w���炪�ǂ���ڎw���Ă���̂����킩���Ă���Ă������͂��ł��B�킩��Ȃ���A�w�Љ�w����̈Ӌ`�Ǝ��H�\�\�l����Ă�Љ�w�\�\�x�������Ɠǂ�ł݂Ăق����ł��B
![]()
��1059���i�Q�O�Q�T�D�X�D�Q�W�j�u���肪�Ƃ��v�̓|���g�K���ꂪ�ꌹ�H
�@���TV�����Ă�����A���E����̒j�q�����ŗD�������u���W���̑I�肪�����Ă���Œ��ɋ��̌����w�ւ𗎂Ƃ������A���̂��Ƃ��C���^�r���[�̍ۂɓ`���ĒT���Ă��������Ɨ����猩�����Ĕނ̌��ɖ߂����Ƃ����j���[�X������Ă��܂����B��ނ����{�̐l�����Ɋ��ӂ�`���Ă����̂ł����A�|���g�K����Łu���肪�Ƃ��v���Ӗ�����u�I�u���K�[�h�iobrigado�j�v�ƌ����Ă����̂ł����A�ځ[���ƕ����Ă�����u���肪�Ƃ��v���Č������̂��ȂƎv���قǁA�C���g�l�[�V���������Ă��܂����B�ȂW������̂��ȂƎv�������Ȃ�قǂŁA������ƋC�ɂȂ��Ē��ׂĂ݂���A�u���肪�Ƃ��v�̓|���g�K���ꂪ�ꌹ�ł͂Ȃ����Ƃ���������͂肠��悤�ł��B
�@�u�I�u���K�[�h�iobrigado�j�v�́A���e����́uobligatus�v�i�`���ɂ���Ĕ�����j����h���������t�������ł��B�u���肪�Ƃ��v�́u�L��v�Ƃ������{�ꂩ�琶�܂ꂽ�͂��Ȃ̂ł��Ƃ��Ƃ��������{�ꂾ�Ƃ͎v���̂ł����A�W������̂ł͂Ȃ����Ƃ�������ǂނƁA�Ȃ�قlj\���̓[���ł͂Ȃ��ȂƎv���Ă��܂��B�ǂ�Ȑ������܂��ɂ܂Ƃ߂�ƁA�퍑����Ƀ|���g�K���l�i��ؐl�j�����{�ɗ���悤�ɂȂ�A�ނ炪�g�����ӂ̌��t�u�I�u���K�[�h�iobrigado�j�v�\�\���̎���u���v�͔��������A�u�I���K�[�h�v�Ɣ�������Ă����Ƃ����������邻���ł��\�\���u���肪�����v�ƍ��̂��āu���肪�Ƃ��v�Ƃ����������Ƃ��Ĉ�ʉ������Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B���ۂɁu���肪�Ƃ��v�Ƃ������������L�܂�̂́A�]�ˎ���ȍ~�������ł��B�m���ɁA���̎���ɓ����Ă����|���g�K���ꂪ�ꌹ�ƂȂ��Ă�����{��́A�p���A�J�X�e���A�J���^�A�V���{���A�^�o�R�A����ԁA�ȂǁA��������܂��B�u���肪�Ƃ��v���|���g�K���ꂩ�炻�̂܂ܗ����킯�ł͂Ȃ��Ƃ��A�C���g�l�[�V�����̕����Ȃǂ̖͕킪�|���g�K���ꂩ�炠�����Ƃ������ƂȂ�A�\�����肤��悤�ȋC�����܂��B
![]()
��1058���i�Q�O�Q�T�D�X�D�Q�O�j�������܂�͂���4�l
�@���NHK�́u�N���[�X�A�b�v����v�Ōh�V�̓�����݂̓��W���g�܂�Ă��܂����B����͖������܂�̐l���C���^�r���[����ԑg�ł����B�u�������܂�Ō��5�l�v�Ƃ����^�C�g���ł������A�ԑg���f�O�ɂ���l�S���Ȃ��Ă��܂��A�ԑg���f���_�ł͖������܂�̐l�͂�������4�l�������Ȃ��Ȃ��Ă��������ł��B�ŔN���̉�쎠�q����i114�j�͂܂��L���͂��������肵�Ă��Đ̂̑z���o�������������Ă��܂����B�吳���N��1912�N7��30������ł�����A�������܂�̕��͑S��112�Έȏ�ł��iNHK�Œ��ׂ��l�����͑S��113�Έȏ�ł����j�B���������Ȃ������ɁA����l�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��͎̂c�O�ł����m���ł��B���͑c����4�l���������܂�ł����̂ŁA�������܂�̐l���m�荇���ɂ��܂����B�����S�N�̏j�������w�Z6�N�����w1�N�̎��ɂ������͂��ł��B�܂��܂��������\�\�l���l�������\�\�����Ă����C�����܂��B�����g�͉�������Ƃ͂Ȃ������ł����A���Ԃ�]�ˎ���̐��܂�̐l�����̍��͑����͂����͂��ł��B�ł��A������O�ł����A�������玞�Ԃ��o������ł���ˁB�܂��A����70�ł�����A���ꂾ���̗��j�����������Ă����킯�ł��B�����ȍ~�̋L�������Ȃ��l���猩����A�����g�����͂���j�̌�蕔�̈�l�ł���ˁB���������łȂ��A�吳���܂������100�߂��ɂȂ��Ă��܂��B����10���N�o������A���x�́u�Ō�̑吳�l�v�Ȃ�Ęb���o�Ă���̂ł��傤�ˁB���͂��̎�����̂��ȁi�j
�@���̂܂ɂ����͗���܂��˂Ƃ��������ɂ�����ƐZ���Ă��܂��܂����B�������A�����ɐZ�邾���łȂ��A�Ō�ɂ�����Ƃ܂Ƃ��Ȃ��Ƃ������Ă����Ȃ�A�������j��ςݏグ�Ă����҂́A������L�^���c���Ă����Ăق����ȂƎv���܂��B�݂�ȁu�����̐l���Ȃ�āA���悤�ȁA�L�^����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł���v�ƌ����܂����A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł���B���Ђ݂�Ȏ����j�������Ăق������̂ł��B�e��������ꂼ��ǂ�ȕ��ɐ����Ă����̂������c���Ăق������̂ł��B����͎Љ�ɂƂ��Ă̋M�d�ȋL�^�ɂȂ�܂��B���{�l�ɂ��������C�͂��Ȃ���A�q�⑷���b���ċL�^���c���Ăق����ł��B�Ⴂ�l�����́A���Ђ����݂̑c���ꂪ������Ȃ�A��������b���ď������߂Ă��������B����́A�����ɂƂ��đf���炵���w�тɂȂ�܂���B���Ѓ`�������W�����Ă��������B
![]()
��1057���i�Q�O�Q�T�D�X�D�P�W�j��㖜���T�K�L�i���̂R�j
�@���5��ڂ̑�㖜���ɍs���Ă��܂����B9�����̕����ł����A���Ɍ����ė���҂������Ă���ƕ����Ă��܂����̂ŁA�ǂ�ȏ�Ԃ����ۂɌ��Ă݂����čs���܂����B����܂ōs����4����m���ɐl�o�͑��������ł��B����12�����߂��ɖ��F�w�ɒ������炢�̑�チ�g���������ɏ���Ă��܂������A�ٓV���w�łǂ��Ɛl����荞��ł��܂����BJR�Ƃ̐ڑ�������w�ł��̂ŁA�V���w����JR�����p���Œ������ɏ�荞��ł����l�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��荞��ł������̉�b�ł��A�Ƃ�7���ɏo���Ƃ�����b���������Ă��܂����̂ŁA�������ʂ��痈���̂ł͂Ȃ����Ɛ����ł��܂����B
�@���F�w�ɒ������̂�12��40���B�����̃G���g�����X�͍��܂Ō������Ƃ��Ȃ��قǐl���������āA���V���ɍs��ɕ��сA���ǃQ�[�g����ꂽ�̂�14���߂��ł����B���܂ł͒����Ă�15�����炢�œ���Ă����̂ŁA����ς葽���Ȃ��Ǝv�킳��܂����B��{�I�ɂ͍���ґw�������A���{�͍���Љ���炱���Ȃ��Ȃ��Ƃ�����ۂł����B70�Α�ȏ�Ǝv���邲�v�w�ƁA���̖�����Ǝv����40�Αキ�炢�̏����Ƃ����悤��3�l�g�����\�ڗ����܂����B�܂��A�w�Z�̂�����̂͂��ł����A���w���炵���q�ǂ���������������A�w�Z�͋x�܂��ė��Ă���̂��ȂƋC�ɂȂ�܂����B�������������̂́A�x�r�[�J�[�̐Ԃ����ł����B�^���ԂȊ�����ċ��������Ă��܂����B�C���͌����L�^��34�x���炢�ł������A�R���N���[�g�̒n�ʂ���̏Ƃ�Ԃ�������܂����̂ŁA���ۂ͂����Ə��������ł��傤�B0�Ύ��̎q�ǂ��ɂ́A��㖜���͊y�������Ȃ��Ǝv���̂ł����A�A��Ă��Ă��܂���ł��ˁB
�@���͂ǂ����������������s�ł��Ă��܂����B������Ɖ���ʂ����h�C�c�ق�240���҂��Ə����Ă���܂����B�u���Ȃ������v�Ƃ����L���b�`�t���[�Y�͂��͂�ǂ����ɍs���Ă��܂����悤�ł��B��{�I�ɕ��Ԃ̂������Ȏ��͂��炽��Ƒ剮�������O�̉��Ŏ��Ԃ�ׂ��A7���O���I�œ��I���Ă������{�ق������Ă��܂����B�i���Ȃ݂ɁA5�ꂵ������4���7���O���I���������Ă���̂ł����A���Ȃ胉�b�L�[�݂����ł��B�j���{�ق̂��Ƃ͉������ׂĂ��炸�A������70�NEXPO�̎��̂悤�ɁA���{�̕�݂����Ȃ��̂���ׂČ����Ă���낤�ȂƎv������A�܂������Ⴂ�܂����B���݂���n�܂��Đ��A�f�ށA���́A�����[�Y�Ƃ������W���ŁA���ۂ�̗͂Ƃ��������̗͂����悤�ȓW�������S�ł����B������A���ۂ͐����ԉ̌`�ɖ͕킵�A���̓L�e�B�����̔�蕨�ɂȂ�A�����[�Y�̓h�������Љ��Ƃ����ɂ��W���̎d���ł����B�ł��A�Ȃ���͂���Ŗ�����銴���ň����Ȃ������ł��B�O�Ɂu�� �㖜���T�K�L�i����2�j�v�ŏЉ�������قȂƂ͂܂������Ⴄ�W���ŁA���ʂ���R����C�͂Ȃ���Ɛ錾���Ă���悤�Ȋ����ł����B����̓��{�̐i�ނׂ��������Î����Ă���悤�Ɋ����܂����B
�㖜���T�K�L�i����2�j�v�ŏЉ�������قȂƂ͂܂������Ⴄ�W���ŁA���ʂ���R����C�͂Ȃ���Ɛ錾���Ă���悤�Ȋ����ł����B����̓��{�̐i�ނׂ��������Î����Ă���悤�Ɋ����܂����B
�@70�NEXPO�̎��́A�A�����J�ƃ\�A���F���J���͎������g�b�v�����i�[���Ƌ��������A���{���l�X�ȓ`����V�����Z�p���֎�����Ƃ������W���ł������A����͒����͗͂̌֎��Ƃ������������܂������A���{�Ɋւ��Ă͏��Ȃ��Ƃ��Ⴄ�悤�ł��B�A�����J�ق͌��Ă��Ȃ����A���V�A�͎Q�����Ă��܂���A�悭�킩��܂��A55�N�o���āA�Y�ƁE�Z�p�̋��������̎���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���悤�ł��B�������A�푈�̊댯��70�N����葝���Ă���C�����ĕ|���ł����B�����A���Ɠ��{�قɉΐ��̐��T���b�ƓW�����Ă������̂ł����A�{���Ȃ�ł��傤���H���Ắu���̐v�̂悤�ɒ������Ď����Ă������̂ł͂Ȃ��A�ΐ��R����覐Ȃ����ł����A�ΐ��̈ꕔ���������覐ƂȂ��Ēn���ɔ��ł����̂ł��傤���B����ȓs���̂������Ƃ���̂��Ȃ��B������ƒ��ׂĂ݂܂������A�u�Ӂ[��A�����Ȃ̂����v�Ƃ��������ł��B�Ƃ肠�����A70�NEXPO�́u���̐v�̂悤�Șb��ɂ͑S�R�Ȃ��ĂȂ��ł��ˁB���ɗ��Ă����l�������Ƃ肠�����ʐ^���B���Ė������Ă��̏�����銴���ł����B�����ʐ^�����B��܂����̂ŁA�f�ڂ��Ă����܂��B��܂ŋ�����A�A�肪��ςȂ��ƂɂȂ肻���������̂ŁA�ߌ�6���O�ɓ����Q�[�g���o�܂������A���̎��ԂɋA��Ƒ��肹���ɁA�����Ɩ��F�w�ɍs�����Ă��炦�Ċy�ł����B
��㖜�����c��1�������܂����B����`�P�b�g�����t�œ���\�ł��Ȃ������قƂ�ǂ̂悤�ł��̂ŁA���̖����T�K������ŏI���̉\���������ł��B�܂�5��s���܂����̂ŁA����Ȃ�ɖ����ł��B
![]()
��1056���i�Q�O�Q�T�D�X�D�P�P�j�����}���̈ӌ��͐��_�f���Ă��邩�H
�@�悤�₭�Δj�����C��\�����A�Վ��̎����}���ّI�����s���邱�ƂɂȂ�܂����B�V���ٌ���A����ɂ͂��̌�̑�����b�w���A�g�t���I��܂ł́A�����͎~�܂�����Ԃł��B����Ȑ������Ԃ͂Ȃ�ׂ��Z�����ׂ��Ȃ̂ɁA�}���I�����s���t���X�y�b�N�̑��ّI���ɂ��邱�Ƃɂ������߂ɁA10�������炢�܂œ��{�̐����͎~�܂葱���܂��B�ȂȈՌ^�̑��ّI���͐����������łȂ��A�}�����S���Q������������������������ƌ�������̕��Ȃ���Ă��܂����A���́A����ȕ��������߂Ă���̂́A���̓}�X���f�B�A�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�}�X���f�B�A�ɂƂ��đI���͂����Ƃ��������̉҂���l�^�ł��B�ȈՌ^�ł�������I����̂ł͂Ȃ�1�������炢�����đ��ّI��������Ă����ƁA����l�^���ł���̂ő劽�}�Ȃ̂ł��傤�B�������A1�N�O�̑��ّI���ɗ���₵���l���肪�܂�����₷��悤�ł��̂ŁA�����c�_������邩�Ǝv����焈Ղ��܂��B���������A��N�ƈႤ�̂́A�^�}���O�Q�ǂ���ł��ߔ����������Ă��Ȃ��̂ŁA�A���̑g�ݑւ��Ɋւ��鎿�₪����邭�炢�ł��傤�B���߂Ďv���o���ƁA�Δj�͍�N�̑��ّI���̎��ɂ́A�v�w�ʐ��̖@������i�߂�A�����U�͂����ɗ\�Z�ψ�����J���ƌ����Ă�����ł���ˁB���فA�����ɂȂ�����A�܂�ł���Ȃ��Ƃ͌����ĂȂ��������̂悤�ȑ�E�\���ɂȂ����킯�ł��B�܂��A�����R���蕷�������̂��Ǝv���ƁA�����Ƃ��܂��B
�@�t���X�y�b�N�̑��ّI���悢�Ƃ��������́A�}���̈ӌ��͐��_�ɋ߂��I���ɏ��Ă�炪�N����I�ׂ邩��ƌ����܂����A����͊ԈႢ���Ǝv���܂��B�I���ɏ����߂ɂ́A���}�h�̕����[�����܂Ȃ��Ƃ����܂���B�Q���}�Ȃǂ̕ێ�h���䓪���Ă����̂ŁA��Օێ�w�����߂��Ȃ��Ƃ����Ȃ��A���̂��߂ɂ͍��s���c�������Ƃ������Ă���l�����܂����A���s���c���g�b�v�ɂ��Ă��A�������̑w�͖߂��Ă��܂���B�����S�����}�ł������A������x�o�����X�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł�����A�g�b�v���ێ�I�ȍl���̐l�ɂȂ����Ƃ��Ă��A�����}�S�̂��K�`�K�`�̕ێ琭�}�ɂȂǂȂ�܂��A����Ȃ��Ƃ�������A���x�͉����ێ�⒆���I�v�l�̋������}�h�w�������Ă����܂��B�ێ�h�̈��{�W�O��������b���������ɑI���ɋ���������A���{��p��W�Ԃ��鍂�s���c�������Ƃ����l�����܂����A���{�ƍ��s�͍����l�C���S�R�Ⴂ�܂��B���{�W�O�̎��Ɏ����}�����������̂́A���̕ێ�I�Ȑ��L���x�����ꂽ����ł͂Ȃ��A���{�̂��V�����I���͋C�Ɛ����I�o�����X�̗ǂ��ɂ����̂ł��B2006�N�̑�1�������̎��́A���Ȃ�ێ�I�Ȑ����ł��o���A2007�N�̎Q�c�@�I���ŕ����đސw���邱�ƂɂȂ����킯�ł����A2012�N�̑�2�������Ȍ�͂��̔��Ȃ������Ă��A�ނ͂����܂ŕێ�I����������͑ł��o�����A�o�ϐ���𒆐S�ɑł��o���A�����̑O�̖���}�������Ђǂ������䂦�ɁA���芴�����߂�L���҂��x�����邱�ƂőI���ɏ���������ꂽ�̂ł��B�{���Ȃ�A�ނ͎��q�����u���h�R�v�Ƃ������O�ɂ������Ƃ��A���@�������������Ƌ����v���Ă���l�ł������A���ǂ��Ȃ������킯�ł��B
�@���A�����}��������x�c�Ȃ�傫���߂��Ĉ���I�Ȑ�������肽���Ǝv���Ȃ�A���}�h�w����荞�܂Ȃ��Ƃ����܂���B���̖��}�h�w�̏��Ȃ��Ȃ��l�������}��̃C���[�W��1�[�𓊂��܂��B�\�ʓI�ȕ��͋C�̗ǂ��l�������}�̃g�b�v�Ȃ�A�����}�̌��҂�1�[����Ă����悤�Ǝv���l���������܂��B���̕[�悤�Ǝv���Ȃ�A����i���Y�����|�I�ɗL���ɂȂ�͂��ł����A1�N�O�̑��ّI���̎��ɂ͓}���[���L�т��A�ނ͌��I���[�Ɏc�ꂸ�ɑ��قɂȂ�Ȃ������킯�ł��B�����������}�������_�f���Ă���Ȃ�A����i���Y�ɕ[���W�܂�ׂ��ł����A�����͂Ȃ�Ȃ������킯�ł��B�����}���ɂȂ��Ă���l�́A���ɐ����ɏڂ����l�����ŁA�I�����ʂ�傫����p���鐭���̂��Ƃ��悭�킩���Ă��Ȃ��A���ɗ�����₷����ʗL���҂ƑS�R�Ⴄ���݂ł��B�����ɏڂ����ނ�́A�u����i���Y�͎Ⴗ����B�o���s�����B���{�̐�����C�����Ȃ��v�ƒႭ�]�������̂ł��B�}���̈ӌ��͐��_��S�R���f�Ȃǂ��Ă��Ȃ��̂ł��B�ނ��뎟�̑I���ɂȂ�Ƃ����I�������ƍl���Ă���c�������̕����A���_������ł���Ǝv���܂��B�ނ�́A�~�[�n�[�ȗL���҂̕[��������̂͒N������ɍl���Ă��܂��B����䂦�A�O��̑��ّI���ł��A�c���[�͏���i���Y���g�b�v�ł����B�c�������̕����}�������ǂ������l���g�b�v�ɂ����玩���}�ɕ[���W�߂��邩���l���Ă��܂��B������ȈՌ^�Ȃ�A����i���Y�������������ł��傤���A�t���X�y�b�N�ɂȂ�܂����̂ŁA���ɐ����ڂ�����������A�������������A�u����i���Y�ő��v���H�v�Ƃ��܂������n�߂�ł��傤�ˁB�O���̗ǂ��ƓK�x�ȕێ琫�ŁA���ۂɑ��قɂȂ�����l�C���o�����Ȃ̂́A���ё�V���ƌl�I�ɂ͎v���܂����A������Ⴗ����A�o���s�����Ƃ������āA��������}������̕[�͐L�тȂ��ł��傤�ˁB
�@�����ŏ��z�肵�Ă����̂́A�ȈՌ^�A������������ŏ����ɂ��邽�߂ɁA�Δj���قɂ���p�w���̂悤�Ȃ��Ƃ�����̂ł͂Ǝv���Ă��āA���ꂾ�ƃs���`�q�b�^�[�̃x�e�����іF�����[�������Ȃ�Ƃ����\���ł������A�t���X�y�b�N�ɂȂ����̂ŁA�ъ��[�����̖ڂ͂قڂȂ��Ȃ�܂����B�Ζؕq�[�������̑��݂��Y����Ȃ����߂̗����ɉ߂��Ȃ��̂ŁA�������Ȃ��ł��ˁB���ǃ}�X���f�B�A�����Ă���悤�ɁA���sVS����ɂȂ�̂ł��傤���B���قɂȂ�����A�ېV���A���ɓ���A�����ۂŏO�Q�ߔ����������A�������^�c���邱�ƂɂȂ�̂ł��傤�B�������A�g�����v��v�[�`����K�ߕ��ƑΛ����鏬��i���Y���C���[�W����ƁA�����}���̂��������Ɠ����悤�Ɉꖕ�����s���͊����܂��ˁB���Ă��āA�ǂ��Ȃ邱�Ƃ��B
![]()
��1055���i�Q�O�Q�T�D�W�D�R�O�j���{�x�x���́u�p�p���v����
�@�����A���{�x�̌x���Ƃ������Ȃ�̒n�ʂɂ���50��̒j�����A16�Ζ����̏����̑̂�G�����Ƃ������ƂŁA�s���ӂ킢���e�^�őߕ߂���܂����B�܂��A������ƕ�������A�ǂ����悤���Ȃ��x�@���������Ȃ��ŏI���ł����A��������l����ƁA�ǂ�����Ԗ��Ȃ낤�Ƃ悭�킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�@�I�ɂ́u16�Ζ����v�Ɛ��I�s�ׂ��s����5�Έȏ�N��̐l�Ԃ́A���R�̔@���Ɋւ�炸�A�u�s���ӂ킢���v�ɂȂ邻���ł��B���̍����́A�Љ�I�ȗ͊W�Ƃ��ŁA���������W���ɍ���Ă��܂����Ƃ���������Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B�������A����̏ꍇ�A�u�p�p���v�������Ə������F�߂Ă��邻���ł�����A����퍇�ӂ͐��藧���Ă����킯�ł��B���������o�����̂́A�����̐e���Əo��Ԃ���������T���o���A�x�@�ɒ��悳��钆�ŁA�������Əo���ɂ��������Ƃ����̂ł킩�����悤�ł��B���̏����̕��́A���̍߂ɂ�����Ȃ��̂ł��傤���B�u�p�p���v�������Ȃ��Ȃ�A�����������������������Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����A�A�A
�@���ɂ����낢��C�ɂȂ邱�Ƃ͂���܂��B������������16���Ă�����A���̌x���͑ߕ߂���邱�Ƃ͂Ȃ������̂ł��傤���B��ʓI�ɂ́A50���߂����j�����A16�Ζ����ɐ��~��������Ȃ�ċC�����������߂ɖ���Ă�������O���ƃj���[�X�����Ďv�����l�́A������17�ł�18�ł������ƋC���������Ǝv���͂��ł���ˁB�ł��A�@�I�ɂ͑Ή����ς�肻���ł��B�N��Ƃ������Ƃł����20�Α�̏����ł��C���������Ǝv����̂ł��傤���B�ł��A���̒��ɂ͂��Ȃ�N�̗��ꂽ�J�b�v�������܂���ˁB���l�����F�߂��鎞��Ȃ�A�����N�̗��ꂽ�j���ԂŐ��I�Ɉ�������������܂ꂽ�Ƃ��Ă��A���ꂾ���ł͖�莋�͂ł��Ȃ��͂��ł��B�������A���̃P�[�X�͗����ł͂Ȃ��A���K�Ɛg�̐ڐG�̌����Ƃ����o�ϓI�s�ׂł����A���ӂ����藧���Ă���Ƃ����_�ł́A�����Ɠ��l�ɔے�͂ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂��B
�@���ƁA�C���������Ƃ����Ȃ�A����͐g�̓I�ȐڐG���܂ޏꍇ�����Ȃ̂ł��傤���B50�Αオ10��̃A�C�h���̐����Ƃ��ɂȂ��Ă���̂́A�C�����͈����Ȃ��̂ł��傤���B�܂��A�����͗�������Ƃ͈Ⴂ���������猒�S���Ǝ咣����l������Ǝv���܂����A�ٗl�Ȃ܂ł̋��K�Ǝ��Ԃ̎g�����A�C�����̓��ꍞ�ݕ��Ȃǂ����Ă���ƁA��������ɋ߂����̂��������肷��̂ł́A�Ǝv���Ă��܂��܂��B�����̏ꍇ�́A���ʂ��t�̃p�^�[���������ł���ˁB50�Α�̏�����10��̒j���A�C�h���ɓ��ꍞ�ނ̂́A�C�����͈����Ȃ��̂ł��傤���B�S���C���������Ȃ��Ƃ���Ȃ�A����̌x�@����10�㏗���ɐ��I�S�������Ă��܂������Ƃ��A�C�������������ł͔��ł��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�@�����ЂƂl�����邱�ƂƂ��ẮA���̒j�����x�@���A������x���Ƃ�����������ɂ��������Ƃł��B�{������M�����A�l�X����闧��ɂ���x�@���\�\���������Ȃ�̃G���[�g�\�\���A����ȕs�����Ȃ��Ƃ��N�����Ȃ�āA�Ƃ����v���������̐l�ɕ������낤�Ǝv���܂��B�x�@���A�����A�Ȃǂ̋N�����������́A��ʂ̉�Ј����N�������������Z���Z�[�V���i���Ɏ��グ���܂��B����̎������A���������Q�j����20�Α㔼���炢�̉�Ј���������A����Ȃɕ���Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����������u�p�p���v�̑���Ƃ��āA20�Α㔼�̒j���ƃJ���I�P�{�b�N�X�ɍs���A���K�I���ӂ̏�ŁA�̂�G�点�Ă����Ƃ������Ƃ�������A�ʂ����Ă��̒j���͑ߕ߂�����Ă����ł��傤���B�@�I�ɂ͏�Ŏ������u�s���ӂ킢���v�����藧�͂��ł����A�Ȃ�ƂȂ����k�Ƃ��A�b�������ōς�ł��܂������ȋC�����܂��B���ہA���́u��Q�ҁv�����́u�p�p���v�͂��̃P�[�X�����Ȃ������Ƃ͎v����ł��̂ŁA�ޏ��Ƃ��������s�ׂ������j���w��{�C�ŒT���Ă�������A��̂ǂ��������ƂɂȂ�̂ł��傤�ˁB
�@�܂��ł��A�}�X���f�B�A��������x�킩���Ă���̂��A���̎����ɂ��ẮA���̌�̑���͂قڂȂ��ł��ˁB�����Ƒߕ߂��ꂽ�x���͈ˊ�ސE���đސE����������Čx�@���l�����I����̂ł��傤�ˁB�������A���O������N����Ă��܂��܂����̂ŁA�Ƒ��͑�ςł��B�~�߂Ă��炦�Ȃ��ł��傤�ˁB�J�߂�ꂽ�s�ׂł͂Ȃ��̂ŁA������x�̎Љ�I���ق���������͎̂d���Ȃ��ł����A�Ȃ������肵�Ȃ������ł��B
![]()
��1054���i�Q�O�Q�T�D�W�D�Q�X�j�w���ƃ����w���x
�@���ݕ��f���̒��h���u����ς�v���A�w�A���p���}���x�̍�҂ł��閟��Ƃ�Ȃ��������v�w�����f���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ́A�݂Ȃ���A�������̂Ƃ���ł����A���ɂƂ��Ă̂�Ȃ����������́w�A���p���}���x�̍�҂Ƃ������A���傤�Ǎ��T�̘b�̒��S���������l��Ȃ��������̎����̕�����ۂ������ł��B�ǂ������o�܂œ��肵�����o���Ă��Ȃ��̂ł����A���̊w�K���̏�ɂ́A��Ȃ��������̃C���X�g�Ǝ��������ꂽ�Ă����������Ă���܂����B�ʐ^�Ƃ��c���Ă��Ȃ��̂Ŏ����������Ȃ��̂��c�O�ł����A��Ȃ����������炵���A��������������������Ă����Ǝv���܂��B
�@���w���̏I��肭�炢�����w�����܂ŔM�S�Ɏ��������Ă������́A��Ȃ������������ҏW���߃T�����I�����s���Ă����w���ƃ����w���x�Ƃ����G���ɂ����e�������Ƃ�����܂��B�m��1�C2�x���炢�͎G���Ɍf�ڂ��Ă���������Ƃ��������悤�ȋC������̂ł����A������������Ȃ��̂ŁA�B���ȋL�������Ȃ̂��c�O�ł����B�E�B�L�y�f�B�A�Œ��ׂ���A�w���ƃ����w���x��1973�N5���ɑn�����ꂽ�����ł�����A������3�̍��ł��B���傤�Lj�ԔM�S�Ɏ��������Ă������ł�����A�����Ƃ��̍��ɓ��e�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�i���Ȃ݂ɁA���̍������������̎��̉��т��́u�C���̐��E�v�Ɍf�ڂ��Ă��܂��̂ŁA�����̂�����͒T���Ă݂Ă��������B�j
�@����L�e�B�������͂��߂Ƃ���L�����N�^�[����̉�ЂƂ����C���[�W�̃T�����I���A����������ɂƂ��Ă̓O���[�e�B���O�J�[�h��̔������ЂƂ����C���[�W�ł����B�����畷�����b�ł����A�܂��T�����I�Ɩ��O��ς���O�̉�Ёi�R���V���N�Z���^�[�j���o�ŋƂɐi�o���悤�Ƃ������ɁA���̋Ζ����Ă�����Ђɘb�������|���Ă������Ƃ������������ł��B���̉�Ђ͋��ȏ���Ђł�������Ȃ������悤�ł����A��Ɂu���̉�Ђ��T�����I�ɂȂ��đ�l�C��ƂɂȂ�Ƃ͂Ȃ��c�v�Ɗ��S�[�����Ɍ����Ă��܂����B
�@���h�����c��1�������炢�Ȃ̂ŁA���ꂩ��͂����ς�w�A���p���}���x����݂̘b�ɂȂ��Ă����낤�ȂƎv���܂����A���ɂƂ��ẮA���T�����肪��Ԏ����̎v���o�Ƃ��d�Ȃ�y�����X�g�[���[�ł����B
![]()
��1053���i�Q�O�Q�T�D�W�D�Q�U�j������M���āA���������l�������̂���
�@��T��NHK�́u���j�T��v�Ƃ����ԑg�ŁA�c���ӎ��Ə�����M�����グ�Ă����̂ł����A������Ƌ����܂����B�ǂ�������Ԃ̕]���ƈႤ�l���������Ƃ����b�������̂ł����A�c���ӎ��̕��́u�d�G�����Ɓv�Ƃ��u�����̕�炵�����������v�Ƃ����͈̂Ⴄ�Ƃ����b�ł������A����͎��ɂƂ��Ă͈�؋����̂Ȃ��b�ŁA�������̂͏�����M�̕��ł��B��M�Ƃ����Ɗ����̉��v�ŁA�ُk�E�ߖ��O�ꂵ�đł��o���A�c������̎��R�ȋ�C����ߕt�������͂̂Ȃ������l�ԂƂ����C���[�W�������̂ł����A���̔ԑg�ł́A��M�͂��������]���Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ�ʂ������Ă����l���ƏЉ��Ă��āA�����������̂��Ƌ������킯�ł��B
�@��������������M�Ɋւ��ẮA�����̉��v�����m��Ȃ������킯�ł����A����͒�M��28����34�܂ŘV��������߂Ă������̂��ƂŁA��M���g�͂��̌�70�܂Ő����Ă��܂��B�V������߂���̒�M�̂��ƂȂǑS���m�����Ȃ������̂ł����A���͂��낢�돑���c���Ă������̂����邻���ł��B�ԑg�ŏЉ��Ă����̂́A��������S�����~�j�u�b�N�̂悤�Ȍ`�ŏ����ʂ������̂�ނ�9������������Ƃł��B�����Ȏ��ɏ������Y��ȕ����Ō�������S����9������ʂ���Ƃ́A���̍��C�ƌ�������D���ɂ܂���������܂����B�������A���ꂾ���Ȃ�܂��߂Ȑl�Ԃ���邱�Ƃ����āA���ԂԂ��ɍ��C�̂��邱�Ƃ�����ɂ�����̂��낤�Ǝv�����Ƃ��ł��܂����A���ɏЉ�ꂽ�̂��A��M�������c�������M��I�s���A�G�b�Z�C�̂悤�Ȃ��̂ŁA���ꂪ�����������̂ł��B�ԑg�Łu�S�̑o���v�Ɩ��t����ꂽ��M�̖{�̈ꕔ���Љ��Ă��܂������A����͒�M���g���������G����̃G�b�Z�C�ŁA�\�ʂɕ\��Ă���s���ƐS�Ŏv���Ă��邱�Ƃ͂����Ԃ�Ⴄ�Ƃ������Ƃ��������̂ł����B��̓I�ɏЉ��Ă����̂́A��l�����̉��ɕt�����킳�ꂽ�q�ǂ��̓��̏�ɐ����o���̂悤�Ȃ��̂��`����A���̐����o���̒��ɂ́u���v���`���ꂢ��Ƃ������̂ł��B�����ɑ�l�����̉��ɕt�������Ă�����̂́A�{���́u�����Q�����v�Ǝv���Ă���̂��Ƃ������Ƃ�\�����G�ł��B���ɂ��A�����ɗD�������Y���悤�Ɍ�����j�̓��̏�̐����o���ɂ́A�L�c�l���l���������G���`����Ă���A�����ɂ��Ă��̏������x���Ď����̂��̂ɂ��邩���l���Ă���Ƃ������Ƃ�������܂��B�G���A�l���̕\����ɖL���ɕ`���Ă���A���ɏ��ł����B���̃G�b�Z�C�ƌ���������g��W��������A���p�قŁu������M�W�v���\���J����̂ł͂Ȃ����Ɩ{�C�Ŏv���܂����B
�@���̔ԑg�����ď�����M�̈�ۂ������ƕς��܂����B��M�͂����̌����ł͂Ȃ��A���w�D���ŊG��������肭�A���ɍ˔\�L���Ȑl�������̂��ƁB�u���j�ɖ����c���v�Ƃ����͉̂����f���炵�����Ƃ̂悤�ɕ������܂����A�l���Ă݂�ƁA���̐l���̐l���͂��̈ꎖ�݂̂ō\������Ă���킯�ł͂Ȃ���ł���ˁB����o�����ŗL���Ȑl���ɂ��A���͗l�X�Ȗʂ�����̂��ƒm�邱�Ƃ͑�Ȃ��Ƃł��B�ǂ��w�тɂȂ�܂����B
![]()
��1052���i�Q�O�Q�T�D�W�D�P�W�j�������u�n���E�m�[�g�v�����������A�A�A
�@����A������NHK�ŕ������Ă����u�V�~�����[�V�����v�Ƃ����h���}�͎j���Ɋ�Â����h���}�ŁA�Ȃ��Ȃ�������������܂����B���a16�N�ɁA�D�G�Ȏ����Ƃ��W�߂āu���͌������v�Ƃ����g�D�����A�����ł��������ĊJ��ƂȂ�����ǂ��Ȃ邩�Ƃ����V�~�����[�V�����������Ă݂��Ƃ���u�K��������v�Ƃ������_�ɂȂ�A�u�A�����J�Ƃ͐푈���ׂ��ł͂Ȃ��v�ƌ����������o�[�͕��������A���Ǔ��{�̓A�����J�Ɛ키���ƂɂȂ�A�V�~�����[�V�����ʂ�̔ߎS�Ȍ��ʂ��������Ƃ������e�ł����B�����Ȃ��h���}�ł������A�m���Ă��鎖�����m�F���邾���̂��̂ł����Ȃ������Ƃ������܂��B�ŁA���I����Ďv�����̂́A���������͌������̎��̃A�h�o�C�X�ɏ]���āA���{���A�����J�Ɛ푈���Ȃ�������A���̌�̓��{�␢�E�͂ǂ�ȕ��ɂȂ����̂��낤�Ƃ������Ƃ����A���V�~�����[�V�������Ă݂����Ȃ�e�[�}���ȂƂ������Ƃł����B�ŁA������ƌl�I�Ƀ`�������W���Ă݂悤�Ǝv���܂��B��̓I�ɂ́A���̎��_�œ��{���{���Ƃ��Ă�������Ȃ��Ƃ����u�n���E�m�[�g�v�\�\�A�����J�����{�ɋ��߂��v�]���\�\���A���{������Ă�����A�Ƃ����z��ł̃V�~�����[�V�����ł��B
�@���{���{��������Ȃ������̂́A�u���{�̎x�߁i�����j�y�ѕ���̑S�ʓP���v�A�u蔣��ΐ����i���������}�d�c���{�j�̏��F�v�Ȃǂł����A���������������ăA�����J�Ƃ͑Ό������A�ނ���A�����J�ƕ��������킹�邱�Ƃɂ��Ă���A���N�����A��p�A���B�ɂ��ẮA�n���E�m�[�g�ł͉����G��Ă��Ȃ��̂ŁA���Ȃ葽���̗̓y������{�鍑�̗̓y�\�\�e���͂��s�g�ł�����̂��܂߂ā\�\�Ƃ��Ďc�������ƂɂȂ�܂��B�A�����J�̌������Ƃɏ]���Ƃ����p����������A�����A�o�̋֎~�������ꂽ�ł��傤����A�o�ς����������ł��傤�B����Ӗ����̎��_�Ŕ����A�����J�̎x�z���ɓ��邱�Ƃɂ͂Ȃ�܂��B
�@��������̊��S�P�ނȂǁA�����̍����͔[�����s���Ȃ��l�������A�\������ƁE�R�l�̈ÎE���N�������ł��傤���A�V�c�����߂����Ƃ��Ƃ������Ƃ��`���ŏI�I�ɂ͑����̓��{�l�͎��ꂽ�ł��傤�B���{���A�����J�Ɛ푈���Ȃ��Ƃ������f�����Ă�����A���[���b�p�̑�2�����E���̓W�J���ς���Ă�����������܂��A��͂�ŏI�I�Ƀh�C�c���������邱�Ƃ͓�������Ǝv���܂��B�C�^���A���E�����h�C�c���s�k������A�푈�ɎQ�����Ȃ��Ƃ����I������������{�鍑�͖����̂܂�1945�N���}���邱�ƂɂȂ�܂��B���R�A����{�鍑���@��ς���K�v�����Ȃ��A�V�c�����ƌ���ł���A�������̑�������R�����ێ�����Ă������ƂɂȂ�܂��B
�@���N�����A��p�A���B�������I�Ɏx�z���ɒu�����܂܁A���̑���{�鍑�̓X�^�[�g���邱�ƂɂȂ�܂��B���ۏ�ł́A�����̗��j�Ɠ��l�ɕă\�̑Η����������Ȃ�A���������͍�������̌��ʋ��Y�}����������`�ɂȂ�A��͂蓌����펞����}���Ă����ł��傤�B���{�͔������ƂƂ��ăA�����J���ɗ��Ƃ����I��������ł��傤�B���N���p�ł͂��Ԃ�Ɨ��^�����������Ȃ����Ǝv���܂����A����{�鍑�͂����ȒP�ɓƗ������Ȃ����A�A�����J���Ɨ��^���̍���ɂ͎Љ��`���͂�����Ƃ����F���ŁA���{���x�z�������邱�Ƃ��x������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�܂�����ł��A���E�̒�����������A�ǂ����œƗ��Ƃ����̂�F�߂�������Ȃ��Ȃ��Ă������낤�ȂƂ����C�����܂��B�Ȃ��A����A�W�A�����̓Ɨ��́A�����̗��j�ł͓��{���Â����[���b�p�̏@�卑����������ǂ��o�����ƂłȂ��₷���Ȃ����Ƃ��낪����̂ŁA���{���C���h�V�i�i�o���Ȃ������Ƃ���A��2�����E���ȑO�̏@�卑�����̂܂ܗ͂����������鎞�オ�����̗��j��蒷���������̂ł͂Ȃ����Ƒz�肳��܂��B���B�����������Ă���A���X�ɓ��{�̉e���𔖂ꂳ���Ă����Ƃ������ꂾ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A����������ƒ�����������ڎw���A����ɒ�R����`�ő���{�鍑�͂��̐푈�ɉ��S���A�Ăѓ����푈���N���Ă����ł��傤�B���̍ۂɂ́A�A�����J�͓��{�̑��ɂ��A�\�A���������ɂ��Ƃ����\�}�ɂȂ�A�����̗��j�ŋN���Ă������N�푈�̂悤�Ȃ��̂����B�ŋN���Ă����Ƃ������Ƃ��l�����܂��B
�@�R�������������Ă�������{�鍑�́A�A�����J���͂���Ƃ������̉��ɁA�x�g�i���푈�ɂ��Q�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������x�����̍��܂ł͈ێ�����A�x�g�i���푈�������������キ�炢����A�悤�₭�p�~�̌������n�܂�Ƃ��������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B������ɂ���A�R���I�ɂ̓A�����J�Ɠ����W�ɋ߂����̂����сA�A�����J�ƂƂ��ɌR���s�������鍑�Ƃ��Đ����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�V�c�Ɋւ��ẮA�������͂邩�ɋ���Ȍ��͂��������N��Ƃ��ČN�Ղ������邱�ƂɂȂ�܂����A���a�V�c�ȗ����Ƃ��Ɨ����N�吧�̂悤�Ȃ��̂ł�������A���܂苭�������邱�Ƃ͂Ȃ��������낤�Ǝv���܂��B�R���̍ō��i�ߊ��Ƃ��Ă̓V�c�Ƃ�������������{�鍑���@���ێ�����Ă����炻�̂܂܂ł����A���Ԃ@���C������āA���������V�r���A���E�R���g�[���̌����̐��ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�u���l�_�v�Ƃ����̂͐M����l�͏��Ȃ��Ȃ��Ă����ł��傤���A����ł��l�X�Ȑ_�����c��Љ�ł��葱���邱�ƂɂȂ��Ă����ł��傤�B
�@��������čl���Ă����ƁA���{�̓A�����J�Ɛ푈���đ�s�������炱���A���̂悤�ȕ��a�ōK���ȎЉ�o���オ���Ă���̂ł����āA�������A�����J�Ɛ푈���Ă��Ȃ���A�����悢�Љ�ł��肦���̂��͂悭�킩��Ȃ��ȂƎv���܂��B���j�ɂ����͂Ȃ��̂ł����A���́u�����n���E�m�[�g��������Ă���v�Ƃ����₢�ƃV�~�����[�V�����͂��Ȃ�ʔ����Ǝv���܂��B���j���u���R�ƑI���v�̌J��Ԃ��ł��ˁB
![]()
��1051���i�Q�O�Q�T�D�W�D�P�T�j�^�Ɠw�́A���邢�͋��R�ƑI��
�@�����̐l����U��Ԃ��Ă���ƁA���낢��Ȃ��Ƃ��l�X�ȋ��R�̐ςݏd�˂ł����Ȃ��Ă���Ȃ��Ǝv������A���₻������Ȃ��Ă���Ȃ�ɂ������悤�Ǝv���ēw�͂������炱���Ȃ����̂��Ƃ�����������C�������N���Ă��܂��B�O�X���ŏ������u�l���ɂ͒����ڕW���K�v�v�Ƃ����̂́A���ӎ��Ɍ�҂̎��_�ɗ������l�����̒������킯�ł����A�l���Ă݂�ƁA���̖ڕW�ݒ�Ƃ����͎̂����\�ƍl������͈͓��ł̂��̂Ȃ킯�ŁA���̎����\�Ȕ͈͂Ƃ����̂́A�����̓w�͂ł͌��߂��Ȃ������肷�邱�Ƃ������悤�Ɏv���܂��B�܂��A�ڕW��B���ł����Ƃ��Ă��A�����100�������̓w�͂̌��ʂł��邱�Ƃ͏��Ȃ��A�l�X�ȉ^�i���R�j����p���Ă���ꍇ�������Ǝv���܂��B�^�������œw�͂������Ƃ��͒P���Ɍ����Ȃ��ł����A�ǂ��炩�����ł͂Ȃ����Ƃ͊m���ł��傤�B
�@���A���ɂ͈��݉�ɕt�������Ă���邽������̋����q���������āA�ނ�ɍK����������Ă��܂����A�ނ�Ƃ���ȊW�ɂȂ��Ȃꂽ�̂��낤���Ǝv���ƁA���R����������ςݏd�Ȃ��Ă̍�����Ȃ��Ƃ��݂��ݎv���܂��B��������w�Љ�w���̋����ɂȂ����̂��ʂɐ̂��炻���Ȃ肽���Ǝv���āA�����Ȃ����킯�ł͂���܂���B����w�ւ̗U���̐���������܂Ŋ���w�̋����ɂȂ�Ƃ����I�����͍l�������Ƃ�����܂���ł����B�ǂ��炩�ƌ����A���������̕��̑�w�Ɉڂ�낤�ȂƎv���Ă������炢�ł��B���܂��ܐ��c�Ƀ}���V�������ďZ�ݎn�߂Ă������ɐ����������āA�E�Z�ڋ߂ɂȂ��Ă����ȂƂ������R�����ňڂ邱�Ƃ����߂܂����B����ȑO�ɂ��A���������������Ă�����Ă�����w������܂������A�����͑I�������A����w�͎��ɒP���ȗ��R�ňڂ����킯�ł��B���c�ɏZ�ނ̂��ʂɂ��А��c�ɏZ�݂����Ǝv���Ă����킯�ł͂Ȃ��A�k���n��̂ǂ����Ǝv���Ă�����A���܂��܂悢�����Əo����������ł��B�������A�w�b�h�n���e�B���O�̐��������Ă�����������x�ɁA�]�������d�������Ă����Ƃ����_�ł͓w�͂̕���������̂ł��傤���A����w���߂����Ă����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���Ȃ���R�̗v�f������܂��B
�@�����āA�֑�ɗ��Ă���A�w���Ƃ̑������悩�����̂��[�~�����Ɋy������肪���������āA�ǂ�ǂ�悫�����q���������܂�Ă������킯�ł����A�ނ�Əo������̂����ċ��R�̐ςݏd�˂��قƂ�ǂł��B600�l�ȏア��[�~���̒��ŁA���Z���ォ��Ћ˃[�~��m���Ă��ē��肽���Ǝv���Ă����Ƃ�������Ȋw�������l���܂����A99���͕Ћ˃[�~�Ȃ�č��Z����ɂ͂܂������m��Ȃ������̂ł�����A���R�̌��ʂł��B���܂����̊�b���̃N���X�ɓ��������̂ł����ňӊO�ƕ|���搶�ł͂Ȃ��Ƃ킩��������ŁA��b���N���X�ŏo����Ă��Ȃ���[�~�I�������Ă��Ȃ������Ǝv���܂��Ƃ����[�~���͉��l�����܂����A������������w�͑�1�u�]�ł͂Ȃ����̑�w�ɍs�������Ǝv���Ă����Ƃ����[�~�����������܂��B���܂��܋��R���d�Ȃ��ĕЋ˃[�~���ɂȂ��Ă���āA�����Z���t���������肵�Ă���킯�ł��B����ȊW�͍�낤�Ǝv���č�����̂ł͂Ȃ��ł��B�������A�[�~���ɂȂ��Ă���Ĉȍ~�͂悢�W����낤�Ǝv���ēw�͂��܂������A���ƌ�܂ł���Ȃɒ����[���t�������鋳���q���������܂��Ƃ́A�A�A����ȖڕW�ݒ�Ȃǂ܂��������Ă��܂���ł����B
�@�{���ɕs�v�c�Ȃ��ȂƎv���܂��B�������A�܂������̋��R�����ł͂Ȃ��A�w�͂Ƃ��̏̒��ł̍őP�̑I���͂��Ă����̂��ȂƂ͎v���Ă��܂����B����ł��A�������̊w�������Ȃ���A�������̃C�x���g���Ȃ���A�ƍl���n�߂�ƁA��͂�l�X�ȋ��R���ςݏd�Ȃ��Ă̍����ȂƂ����C�����ɂȂ�܂��B�^�Ɠw�́A���邢�͋��R�ƑI���A�l���͖ʔ������̂��Ȃ��Ɖ��߂Ďv���Ă��鍡�����̍��ł��B
![]()
��1050���i�Q�O�Q�T�D�W�D�P�R�j�u���{���p�̍z���W�v���ʔ���
�@���A��㒆�V�����p�قŊJ�Â���Ă���u���{���p�̍z���W�v�͔��ɖ��͓I�ȓW����ł��B�ɓ���t�Ɖ~�R������2�l��1�̛����������Ă����̂�������A���ꂪ�ő�̖ڋʂɂȂ��Ă��܂����A�s���Č��Ă݂���A���ɂ���������̖��͓I�ȍ�i���W������Ă��܂��B���̑啔�����܂������m��Ȃ���Ƃ̂��̂ŁA�s�v�c�ȍ�i���炯�Ȃ̂ł��B�p���t���b�g�Ɂu�i���W���R�����I�A���v�Ƃ����h��ȃL���b�`�R�s�[���ڂ��Ă���̂ł����A�R�s�[�ɋU��Ȃ��ł��B�{���Ɂu�ȂA����́I�v�ƌ��������Ȃ��i����������܂����B�܂��A��i�̐������ʔ����āA���N�X���Ə��Ă��܂��܂��B
�@7�̕����ɕ�����Ă��āA��1�̕����͎�t�Ɖ����̛��������C���ł����A����Ƃ����]�ˎ���̉�Ƃ����j�[�N�Ȋy�����G��`���l�Ȃƒm��܂����B��2�̕����ł͎�������̐��n�悪�Љ��Ă��܂������A�����P���̉������̊y���̂悤�ț����������[�������ł��B��3�̕����́u�f�p�G�ƑT��v�Ɩ��t������Ă��܂����A������ǂނƉ���ȊG���W�߂Ă���A���̖��킢���y�������Ƃ����_���������ł��A17���I�̉�ƁE���J��b���́u�������O�}�����v�ɂ́A�u��ԉ���ȗ������O�}�v�Ɛ��������Ă��܂������A��������ɕ`���ꂽ�u�z������G���v�ɂ́u���̓E�}���̂ɊG�̓w�^�v�ƓŐ�ł����i�j��4�̕����͗��j�G�̕����ł����A���c�����Y�Ƃ�����������̉�Ƃ��`�����u�f���j�������֑ގ��v�̊G�ł́A�Ȃ����L�����o�X��˂��j���ă|���[���Ƃ�����������o���܂��B�܂��Ɂu�Ȃ�A����́H�v�ƙꂫ�����Ȃ��Ă��܂��܂����B��5�̕����͓S�̒����ƃv���X�`�b�N�⎆�ő���������������Ă��܂����B�Ƃ��Ɍ���̎Ⴂ��Ƃ̍�i�ł����A�O�҂͖L�b�G�g���������ƌ����鉩���̒����ւ̑R�������ŁA��҂͐痘�x�̘l�ю�т̌���łƂ����ӎ��ő����������ł��B��6���́A�u�]�˖�������ߑ�ցv�Ƃ������Ƃő����̍�i���W������Ă��܂������A�m��Ȃ���Ƃ���ŁA����ȑf���炵����i���c���Ă����l�������ƕ��ɂȂ�܂����B���l���f���炵����Ƃ����܂������A�l�I�ɂ͊}�؎��Y�g�Ƃ�����Ƃ̖�������̕�����`������i�ƁA����{�썁�R�Ƃ����������Ƃ̍�i���f���炵���Ǝv���܂����B�L���X�g���ƕ�����Z���������e�[�}�̊G��`���Ă����q���@���̊G�������[�������ł��B�Ō�̑�7���́A�ꕶ����̊�Ƃ���ɉe������������p���W������Ă��܂����B�l�b�g�Ńp���t���b�g�i�z���W_�`���V_�\_0413�j��������悤�ł��̂ŁA�����̗N�������͂��Ђ������������B
�@�`���V�����邾���ł����Ȃ�ʔ����̂ł����A�`���V�ɍڂ��Ă��Ȃ���i�ł��ʔ������̂���������܂������A���̃T�C�Y��������Ō��Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��Ǝv���̂ŁA�����Ԃ̂�����͂��Њςɍs���Ă݂Ă��������B8��31���܂ł������ł��B���p�ق̒��͂ƂĂ��������̂ŁA���̏��������ɏo������X�|�b�g�Ƃ��Ă͂��傤�ǂ悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
![]()
��1049���i�Q�O�Q�T�D�W�D�P�O�j�l���ɂ͒����ڕW���K�v
�@���Ԃ̂����Ղ肠��ċx�݂ɁA����̐l����U��Ԃ����肵�Ă���̂ł����A������x���̂��l������悤�ɂȂ����N��ȍ~�́A��ɒ����ڕW�������Ă����ȂƉ��߂ċC�Â��܂����B�����ڕW�Ƃ�2�`10�N���炢��ɂ����Ȃ��Ă������ȂƂ����ڕW�ł��B20�`30�N��̒����ڕW���l���邱�Ƃ͂���܂������A���܂�ɂ���߂��関���͂��̂��߂ɂǂ��w�͂����ׂ����Ƃ����̂͌����ɂ����̂ŁA������̖ڎw���ׂ��p�ł��钆���ڕW�̕������d�v���Ǝv���܂��B�����̐l�����Ԃ鎞���܂ł͓����悤�ɒ����ڕW�𗧂ĂĂ����Ǝv���܂��B����ȏ����̂��Ƃ��l����悤�ɂȂ�̂͏��w�Z���w�N���炢���炾�Ǝv���܂��̂ŁA�ŏ��͒��w�Z�ɓ������牽���ɓ��낤�Ƃ����w�̕����撣�낤�Ǝv���A���w�ɓ�������A��������ł������ʂ��o�������A�����Ă悢���Z�ɍs�������ƍl���A���Z���ɂȂ�����t�����������A�ǂ���w�ɂ��s�������Ɗ撣���Ă����͂��ł��B���̕ӂ܂ł́A���ł���Ȃ菬�Ȃ蓯���悤�Ȓ����ڕW�ݒ�����Ă���l�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�������A��w�ɓ����Ĉȍ~�́A�̂ƍ��ł͒����ڕW�ݒ肪���Ȃ�Ⴄ�C�����܂��B�̂́A�ǂ�Ȏd���������������l�����̎d���ɏA����悤�ɓw�͂��A10�N�キ�炢�ɂ͉ƒ�������Ă���Ȃ�Ē����ڕW�𑽂��̐l�����ĂĂ����Ǝv���܂����A���͂Ƃ肠�����A�E�͂ǂ����ɂ���Ƃ��Ă����̌�̐l���v����������l����l�����Ȃ��Ȃ��Ă���C�����܂��B���́u��w�������v�ł��u�����ڕW�v�Ɋւ��鎿��ŁA�u��������ƌv��𗧂ĂĖL���Ȑ�����z���v�Ƃ����I������I�Ԑl�́A1987�N��30.5�������̂��A2022�N�ł�19.7���܂Ō����Ă��܂��B�����A�u���̓����̓������R�Ɋy�����߂����v��I�Ԑl�́A38.1�������܂��B���w���⍂�Z�������i��ڕW�ݒ肷��͓̂��R���Ǝv���܂����A��w�����A�E������ڕW�ɐݒ肷��̂́A�{���ɂ���ł����̂��ȂƎv���܂��B��w����́A�ǂ�Ȑl���𑗂肽���̂�����������l���Ă��̂��߂ɓw�͂��Ăق����Ǝv���܂��B�܂����܂��̒����I�ڕW�͗��Ă��Ȃ��Ƃ��Ă��A30���炢�ɂǂ��Ȃ��Ă����������l���āA���̖ڕW�̂��߂ɉ������Ȃ���Ȃ�Ȃ���������łق������̂ł��B
�@30���߂�����A���x��40���炢�ɂǂ��Ȃ��Ă����������l���Ă݂Ăق������̂ł��B�q�ǂ���������q�ǂ��ɂ����Ȃ��Ă��Ăق����Ǝq�ǂ��̏����̂��Ƃ��l�������Ȃ邩������܂��A�������g���ǂ��Ȃ��Ă������������l���Ă݂Ăق������̂ł��B�d���Ɋւ��Ă��A�e�Ƃ��Ă��B���X�̕�炵�ɒǂ��ĒZ���I�ɂ����ڕW�ݒ肪�ł��Ȃ��Ƃ����l���������ł����A��̂��ƂȂl�������Ȃ����䂦�Ɂu�����v�̂��Ƃ���l���ę��ߓI�y�����ɓ����Ă���l���������ł��B�ڕW�ݒ肵�A���̖ڕW�̒B���Ɍ������ēw�͂���̂͂���ǂ��Ǝv���l�����邩������܂��A�����̌o�����猾���A���������ڕW�ݒ肪�ł�����������ɒ��肪�o�܂��B
�@40���߂�����50�̎��ɁA50���߂�����60�̎��ɁA�ƂȂ�܂����A���̂����肩��i�X�����I�ڕW�̐ݒ肪����Ȃ��Ă��܂��B40�̎���50�̐ݒ�͂܂�������ł��傤���A50�̎���10�N���60�̎��ɂ����Ȃ��Ă������Ǝv���̂͗e�Ղł͂Ȃ���������܂���B50���炢�܂ł͂܂��܂����C�ł����A���낢����邾�낤�Ǝv���܂����A60���C���[�W����ƁA���Ȃ萊���Ă��Ă���̂ł͂Ƒz�����Ă��܂��l�������ł��傤�B����䂦�A50���߂����璆���ڕW�̐ݒ���Ԃ͏����Z�߂ɂ��������ǂ��̂��낤�Ǝv���܂��B3�`5�N�キ�炢�Ȃ�ݒ�ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@��w�����E�����҂̐��E�͐��Ԉ�ʂ��N����߂Ȃ̂ŁA�����g��50�̍��͂܂������o���o���Ƃ����ӎ��ŁA10�N���60�̎��ɂ����Ȃ��Ă������Ƃ����悤�Ȑݒ�͂��Ȃ������C�����܂��B����ł��A50�Α�͎��X�ɏd�v�Ȗ�E�ɏA���A���̎d����������Ƃ��Ȃ����ƂŊm�������|�W�V��������������ێ����ď[���������X�𑗂邱�Ƃ��ł����悤�Ɏv���܂��B60�Α��50�Α�قǂɂ͖Z�����Ȃ��Ȃ�܂������A�����ڕW�̐ݒ���傫�Ȃ��̂͂Ȃ��Ȃ�܂������A���N�����Ă�����w��������A�Љ�w����̖{���o�������Ƃ��������҂Ƃ��Ă̖ڕW�͂���܂������A������D���ȎЉ�w�����ʂ��Ċw����Ă��ł���Ƃ����y���݂œ��X���߂����܂����B
�@��70�ɂȂ�A����7�J����ɂ͊��S�ސE������킯�ł����A���N4���ȍ~�ǂ������Ă������Ƃ��������ڕW�ݒ�𗧂ĂȂ��Ƃ����Ȃ��ȂƎv���Ă��܂��B�����Ȃ��Ǝv���ƁA�C�͂��o�Ȃ��Ȃ肻���Ȃ̂ŁA�����ڕW�ݒ�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł����A�Ⴂ���قNJȒP�ɖڕW�ݒ肪�ł��܂���B���Ɖ��N�����邩���킩��Ȃ��̂ł�����A10�N��͂������5�N��ł�����������Ԃ�������܂���B70���߂��Ē�E���Ȃ��Ȃ����l�Ԃ́A������ƒZ���ɂȂ�܂����A���N��A1�N�キ�炢�̊��Ԃł̖ڕW�ݒ肪�����̂�������Ȃ��ȂƎv���Ă��܂��B�ł��A�����́u������r�v�ɂȂ�Ȃ����߂ɂ́A�i�Z�j�����ڕW�͕K�v���Ǝv���܂��̂ŁA70�Α�Ȃ�́A���Ȃ�̉��������������Ǝv���܂��B
![]()
��1048���i�Q�O�Q�T�D�W�D�R�j�G�b�`
�@������ƋC�p���������^�C�g���ł����A���̌��t�ɂ��ĎЉ�w�I�ɕ��͂��Ă݂����Ȃ����̂ŁA�X�g���[�g�ɕ\�����܂��B���̌��t�͂������Ȃ������������́A�����畷�����b�ł����B�ŋ�8�̑����u�h��������v��ǂ�ł��āA����������u�̂ё�����̃G�b�`�I�v�Ƌ��ԏ�ʂ�����A�u�}�}�A�G�b�`���ĉ��H�v�ƕ����ꂽ�Ƃ����G�s�\�[�h�ł��B���������A�u�h��������v�ł́A�̂ё����h��������̔閧����̎g�������ԈႦ�āA�����������̂����C��ɓ��R�����Ƃ�������ʂ����\����܂�����ˁB�i�ŋ߂́A�R���v�����������̂ŁA�����Ƃ��������V�[���������Ă���̂ł��傤���B�j
�ŁA������u�G�b�`���āA�Ȃ�̗��Ȃ낤�v�ƕ�����āA�u���Ԃ�A�j���p�̓��������痈�Ă����Ȃ����ȁv�Ɠ������̂ł����A���̌㒲�ׂĂ݂�Ɓu�ϑԁv�̓��������Ƃ��������L�͂Ȃ悤�ł��B�����u�j���p�v�̗���ł͂Ȃ����Ǝv�����̂́A1960�N��I���ɉi�䍋�́u�n�����`�w���v�Ƃ����}���K����q�b�g���A����Łu�G�b�`�v���L�܂����̂ł͂Ǝv��������ł������A���ۂ͂����ƑO����g���Ă����悤�ł��B�E�B�L�y�f�B�A�ɂ��A1950�N��ɂ͏��w���̊ԂʼnB��Ƃ��Ă��łɎg�p����Ă��������ł��B���Ȃ݂ɁA�u�ϑԁv�Ƃ������t���ٗl�Ȑ��I�S�Ƃ��Ďg����悤�ɂȂ����̂��A�����ɏЉ��Ă�������������Ȃ�A�吳����㔼�����肩��̂悤�ł��B
�u�G�b�`�v�́A1970�N�㍠�܂ł́A����������̂ё��N�ɋ��ׂ����x�ɁA���I�ȊS���������Ƃ�\�����x�̌��t�Ƃ��Ďg���Ă��܂������A1980�N��ȍ~�A���ΉƂ���܂����肪�A�Z�b�N�X���_�炩���\�����邽�߂Ɂu�G�b�`�v�ƌ����悤�ɂȂ�A���ꂪ�L�܂��āA���ł́u�G�b�`�v�͈��N���艺�̐���ł́A�Z�b�N�X�Ƃقړ��`�ɂȂ��Ă���悤�ł��B��{�I�ɂ��̌��t�͎Ⴂ�����̗p��Ȃ̂��Ǝv���܂��B����܂��Ⴂ��������̃g�[�N��W�J���邽�߂ɁA���̌�����������悤�ɂȂ����̂��Ǝv���܂��B�j�������̉�b�̒��ł́A�u�G�b�`�v�Ȃ�Ă��킢���������͂��܂肳��ĂȂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̌��t�͂�����Ƃ��킢����������Ƃ��낪�d�v�ȃ|�C���g�Ȃ̂ł��傤�B
1970�N��܂ł́u�G�b�`�v�̈Ӗ��Ƃقړ��`�̌��t�Ƃ��āu�X�P�x�i�����q�j�v�����݂��Ă����킯�ł����A���w�������ɂ��₷�����t�ł͂Ȃ������ł��傤�B�܂��A1980�N��ȍ~�̈Ӗ��Ȃ�u�Z�b�N�X�v�ɂȂ�킯�ł����A������X�g���[�g�����邩��Ⴂ�����Ƃ��Ă͌��ɏo���ɂ��������킯�ł��B�j���������X�g���[�g�ɕ\���ł��錾�t�����������͂��ɂ����Ƃ������ŁA���̌��t�͐��܂�A���Ӗ��ϗe�����Ă����ƍl�����܂��B
![]()
��1047���i�Q�O�Q�T�D�W�D�P�j���߂Ȃ��g�b�v
�@���������7�����Ɏ��E����ƌ����Ă����c�v�ۈɓ��s�����O����P�A���߂Ȃ��Ɛ錾���܂����B�����ŋ߂̔ޏ��̑ԓx����A���̑O���P��錾���o�����ȕ��͋C�͏\������܂������A�Ȃ������ł��ˁB���Ԃ����u���m��w���Ɓv���Ă��Ȃ����Ƃ�99���킩���Ă���͂��ł��B�Ȃ����ЂɂȂ������킩��Ȃ��ƌ����Ă��܂����A���ʁA��w�����ЂɂȂ�͎̂��Ɨ��̖��[���ł��B���Ԃ�A�ޏ��������������̂ł��傤�B�����̎�����S���������Ă���͂��ł����A�u�����ł͑��Ƃ��Ă����Ǝv���Ă����v�Ƃ��u�Ȃ����ЂɂȂ������킩��Ȃ��v�Ȃ�Ă����R���ʂ��ʂ��ƌ���������u���_�͂̋����v�ɂ͂���Ӗ��Ŋ��Q���܂��B������^�������炩�ɂ�����E�I���@�ᔽ�ŗL�߂ɂȂ�s���E���������ƂɂȂ�̂𗝉�������ŁA�����Ȃ�M���M���܂Ŏs���Ƃ��Ă̋��^����낤�Ƃ����헪�Ȃ̂��ȂƂ����C�����܂��B�L�߂��m�肷��܂łɂ͂��Ȃ莞�Ԃ�������ł��傤����A�s���Ƃ��Ă̋��^�͂��Ȃ蒷�����Ǝ��邱�ƂɂȂ�ł��傤�B�������ɂ��Ă���ٌ�m�����m�b�𐁂�����ł���悤�Ɍ����܂��B
�@�����Ŏ��߂�ƌ���Ȃ��s�������߂�����ɂ́A���R�[��������܂����A�L���҂�3����1�̏������W�߁A�����̌�Z�����[�ʼnߔ����̎^�������Ȃ��Ƃ����܂��A���Ȃ�̘J�͂��K�v�ł��B������ȒP�Ȃ͎̂s�c��ŕs�M�C�Ă������邱�Ƃł����A������͑��s���ސw�ɂȂ�Ƃ͌��炸�A�s���͎s�c����U�Ƃ������łĂ܂��B���̍đI���őI�ꂽ�s�c��c�����Ăѕs�M�C���������炳�����Ɏs�������߂�������܂���B���ꂪ���Ԃ��Ԍ����I�Ȑ헪�ł����A���̓c�v�ێs���̑ԓx�����Ă�����A�ԈႢ�Ȃ��s�c����U��I�Ԃł��傤�B��������ƁA�����őI���Ǘ��������A���̌�A�܂��s���I���ł����������邱�ƂɂȂ�܂��B�킪�܂܂ʼnR���̎s���̂������ňɓ��s�͖��ʂɂ������g��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂��B���m��w���Ƃł͂Ȃ��Ƃ����������������i�K�ŁA�f���ɔF�߁u���o�����U���Ă��܂��܂����B�{���͑��Ƃ��Ă��܂���B���߂�Ȃ����B�s���͎��߂܂����A������x�`�������W�����Ă��������v�ƌ����Ă�����A�o�����I���ɏo�Ă������������珟�Ă���������܂���B�������A�����܂ʼnR���������A�s�������������Ă��܂��ẮA�����ޏ��̍đI��100�����肦�܂���B���A�����̂ǂ�Ȏd����ޏ����ł���̂��z�����ł��܂���B���������������Â������������邩�炱���A�M���M���܂Ŏs�����^�悤�Ǝv���Ă���̂�������܂���B�Ԉ�����I�����Ǝv���܂����B
�@����ɂ��Ă��ŋ߂́A���낢���肪�N���Ă����߂Ȃ��g�b�v�������ł��ˁB��N�A�s�ϖ�肪���炩�ɂȂ����i��ݘa�c�s���������ł͎��߂��A�s�c��ŕs�M�C���s�c����U���s�c��I�����ēx�s�c��ŕs�M�C���s�����C���đI���ŗ��I�Ƃ����`�ł悤�₭�P�������܂����B�V�����Ɍ��m���͌��c��̕s�M�C�������ꂢ�����C���܂������A�đI���ɏo�n�������̗\�z�𗠐��čē��I���Ă܂��m���ɖ߂��Ă��܂����A�ވȗ������̔�͔F�߂��A�������玫�E�����Ȃ��Ƃ����I�������\�����肤����̂ƂȂ��Ă��܂��������ł��B
�@�����ł��Δj���������߂Ȃ��ł��ˁB�����}���������͈̂��{�h�𒆐S�Ƃ����u�����ƃJ�l�v�̖��Ŏ����̂����ł͂Ȃ��Ǝv���Ă���̂ł͂Ƃ����b������Ă��Ă��܂����A���R�͂ǂ�����A����܂ł�������I���̌��ʐӔC���g�b�v�����̂�������O�����������������ς�����悤�ł��B�u�����ƃJ�l�v�̖�����������������܂��A�Δj�����͂���������Ƃ������_���������������炱���̂��̑I�����ʂł��傤�B����������i���Y�������Ȃ�A�����܂ł͎����}�������Ȃ������ł��傤�B���̈Ӗ��ł́A�Δj�ɂ͌��ʐӔC�����łȂ��A�����I�ӔC���������ƍl����ׂ��ł��B����ł��A�{�l�����߂Ȃ��Ɠ˂�����Ȃ�A�Ȃ��Ȃ��������ق����߂����邱�Ƃ͓���悤�ł��B���ّI�̑O�|�������s�����F�߂Ȃ��Ɠ���悤�ł�����A���Δj�h�̎����}�c�����Δj�����߂����錈��I�Ȏ肪�łĂȂ��悤�ł��B��}�����̂܂ܐΔj�����ɋ��͂���Ƃ����̂ł͍���̎Q�c�@�I���̐��_�ɉ����Ă��Ȃ����ƂɂȂ�̂ŁA�����܂ł��Δj�����߂Ȃ��Ȃ�A���t�s�M�C�Ă��o����Ƃ������ł��Ȃ��Ƃ����Ȃ���������܂���B��������o���ꂽ��O�c�@�Ŗ�}���ߔ����������Ă���̂ŁA�f���ɍl��������ł����A��}�����̌�Δj���������U���I���ɑł��ďo���ꍇ�ɁA�c�Ȃ�L����Ǝv���Ă���͍̂�������}�ƎQ���}���炢�ł��傤����A�P���Ɏ^���ł��邩�ǂ����킩��܂���B�܂�������������A�����}���̔��Δj���͂��s�M�C�ĂɎ^����������Ƃ������\�����[���ł͂Ȃ��C�����܂��B�������A���̏ꍇ�����U���I����Δj���I�ԂȂ�A���ǁA�����}�͐Δj�����̉��ŁA����ɂڂ�ڂ�̑��I�����s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A�����͂����Ƌc�Ȃ����炷�ł��傤�B
�@�ǂ��l���Ă������̈���̂��߂ɂ́A�Δj���������E���A�V�����̉��ŁA�����{�ېVor�����Ƃ���3�}�A����������邱�Ƃł����A�Δj�����߂Ȃ��ƌ���������Ƃ���͎������܂���B���̐������n���̐��������߂Ȃ��g�b�v�̂����ō����������܂��B�����g�D�����łȂ���Ƒg�D�ȂǑ��̊����g�D�ł��A���ʐӔC�Ƃ��Ǘ��ӔC����炳��ăg�b�v�����߂���āA�Ȃ��������ȂƎv�������Ƃ�����܂������A�����������Ă����Ԃɂ����߂����đO�ɐi�ނ��߂ɂ́A�g�b�v�����߂�Ƃ��������͂���Ȃ�ɏ��@�\���ʂ����Ă����ȂƂ������Ƃ��������鍡�����̍��ł��B
![]()
��1046���i�Q�O�Q�T�D�V�D�Q�U�j�P�A�n�E�ƂɏA�������̍������͍����̂ł́H
![]() �@20�N�ȏ�ʂ��Ă��鎕�Ȉ�@�Ŏ��ȉq���m����Ƙb���Ȃ���ӂƎv�����̂ł����A���ȉq���m�̕��̍������͈�ʏ�����肩�Ȃ荂���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�S���̎��ȉq���m������u�m���Ɍ������Ă���l�͑����ł��ˁv�ƌ����Ă��܂����B���̌ア�낢��l���Ă�����A�P�A�n�̐E�Ɓ\�\���ȉq���m�A�Ō�t�A���m�A�ۈ�m�A�c�t�����@�A���w�Z���@�ȂǁA����̂�����l�Ԃ̐��b������悤�ȐE�Ƃŏ����䗦�������E�Ɓ\�\��I�ԏ��������̍������͂��ׂ��炭�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����Ă��܂����B�E�ƕʍ������̃f�[�^�I�Ȃ��̂͑�������悤�ł����A�u�P�A�n�E�Ɓv�Ƃ����͎̂�������ɍl�����E�Ɩ��̂Ȃ̂ŁA����ɂ҂����肷��f�[�^�͌�����܂���B�����ĎQ�l�ɂȂ肻���Ȃ��̂�T���ƁA�}�C�i�r�E�[�}�������\���Ă���E�\�̃f�[�^��������܂����B���̒��ŁA�P�A�n�E�Ƃ��ȂƎv����̂́A�Ō�t�A�Љ�����E�Ə]���ҁA���T�[�r�X�E�Ə]���ҁA�ی���ÃT�[�r�X�E�Ə]���҂�����ł��B���ꂼ��̏�����50�Ύ��������́A13���A9���A11���A10���ł��B���ς�15���ł��̂ŁA�ǂ̐E�Ƃ����ς��͖��������Ⴂ�\�\�܂荥�����������\�\�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂��A�ɒ[�ɍ�������Ƃ����قǂł͂Ȃ��̂ŁA�\���ȃf�[�^�Ƃ͌����܂��A�������̍����E�ƂȂǂƔ�r����ƁA��͂�ǂ������d����I�Ԃ��ɂ���č������͂��Ȃ�قȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ͌��������ȋC�����܂��B���̃f�[�^�́A50�Ύ��̃f�[�^�Ȃ̂ŁA����̐��オ�Ώۂł��B�����������̐���i30�Α�㔼������j�̍������ׂ�������ƍ�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@20�N�ȏ�ʂ��Ă��鎕�Ȉ�@�Ŏ��ȉq���m����Ƙb���Ȃ���ӂƎv�����̂ł����A���ȉq���m�̕��̍������͈�ʏ�����肩�Ȃ荂���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�S���̎��ȉq���m������u�m���Ɍ������Ă���l�͑����ł��ˁv�ƌ����Ă��܂����B���̌ア�낢��l���Ă�����A�P�A�n�̐E�Ɓ\�\���ȉq���m�A�Ō�t�A���m�A�ۈ�m�A�c�t�����@�A���w�Z���@�ȂǁA����̂�����l�Ԃ̐��b������悤�ȐE�Ƃŏ����䗦�������E�Ɓ\�\��I�ԏ��������̍������͂��ׂ��炭�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����Ă��܂����B�E�ƕʍ������̃f�[�^�I�Ȃ��̂͑�������悤�ł����A�u�P�A�n�E�Ɓv�Ƃ����͎̂�������ɍl�����E�Ɩ��̂Ȃ̂ŁA����ɂ҂����肷��f�[�^�͌�����܂���B�����ĎQ�l�ɂȂ肻���Ȃ��̂�T���ƁA�}�C�i�r�E�[�}�������\���Ă���E�\�̃f�[�^��������܂����B���̒��ŁA�P�A�n�E�Ƃ��ȂƎv����̂́A�Ō�t�A�Љ�����E�Ə]���ҁA���T�[�r�X�E�Ə]���ҁA�ی���ÃT�[�r�X�E�Ə]���҂�����ł��B���ꂼ��̏�����50�Ύ��������́A13���A9���A11���A10���ł��B���ς�15���ł��̂ŁA�ǂ̐E�Ƃ����ς��͖��������Ⴂ�\�\�܂荥�����������\�\�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂��A�ɒ[�ɍ�������Ƃ����قǂł͂Ȃ��̂ŁA�\���ȃf�[�^�Ƃ͌����܂��A�������̍����E�ƂȂǂƔ�r����ƁA��͂�ǂ������d����I�Ԃ��ɂ���č������͂��Ȃ�قȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ͌��������ȋC�����܂��B���̃f�[�^�́A50�Ύ��̃f�[�^�Ȃ̂ŁA����̐��オ�Ώۂł��B�����������̐���i30�Α�㔼������j�̍������ׂ�������ƍ�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�P�A�n�̐E�Ƃɂ��Ă��鏗�������̍������������̂ł͂Ȃ����ƍl����̂́A���̎d���ɏA�����Ǝv�����l�ςƁA�Ƒ�����낤�Ǝv�����l�ςɐe�a���������̂ł͂Ȃ����Ǝv������ł��B�l�Ƃ��Ċy�������������Ǝv�������́A��̂�����l�Ԃ̐��b������悤�Ȏd���͑I�Ȃ����A�������邱�Ƃ��K���������Ƌ����v��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����20�N���炢�̎�����l����ƁA�����Ƃ������͎̂��R�ɂł�����̂ł͂Ȃ��A���Ȃ苭���ӎu�Łu���悤�v�Ǝv��Ȃ��Ƃł��Ȃ��Ǝv���܂��B�����̐l���ɂƂ��āA�������K�v���Ǝv���ӎ��̈Ⴂ���������̈Ⴂ�ɂȂ��Č����Ǝv���܂��B�������A�o�ϓI�Ɏ�������̂�����E�ƂɏA���Ă���ꍇ�́A�����Ƃ����I��������������Ȃ��Ƃ����P�[�X������Ǝv���܂����A�P�A�n�E�Ƃ̒��ɂ͏\�������ł�������Ă��鏗���������Ǝv���܂��B����ł��A�P�A�n�̐E�Ƃ�I�ԏ����́A��������Ƃ����I���������̐l���ɂƂ��ĕs���Ȃ��ƂƎv���l���������ȋC�����܂��B
�@����̉Ƒ��͏����������P�A������̂ł͂Ȃ��ł����A��͂蒷���ԁA���������C���[�W������Ă��āA����ł����S�ɂ͕��@����Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B�玙�A���ȂLj�Ԏ�̂�����d���Ɏ����I�ɏ������ւ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ����́A�܂����Ȃ�c���Ă���Ǝv���܂��B�������ĉƑ������Ƃ������Ƃ́A���������ʓ|�Ȃ��ƂƂ��t������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ����C���[�W�͂܂��܂�����Ǝv���܂��B�z�肳��邻�������ʓ|�Ȃ��Ƃ��Ȃ�ׂ����������Ǝv���Ȃ�A�����Ƃ����I���̈ӎu���݂�ł��傤�B�������A��̂�����l�̐��b�����邱�Ƃ�������Ȃ��P�A�n�̐E�ƑI�������������̏ꍇ�A���������`���I�ȏ����������A�����܂Ō��Ȃ��ƂƎv��Ȃ����l�ς������Ă���l�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̌��ʂƂ��ăP�A�n�̎d���ɏA���Ă��鏗�������̍������͍����Ƃ������ʂ����܂��̂ł͂Ȃ����ƍl���܂��B
![]()
��1045���i�Q�O�Q�T�D�V�D�Q�T�j��w���������玟�̑I���ŋN���邱�Ƃ�������
�@�Q�c�@�I���̌��ʂ́A�����}�ƌ����}���c�Ȃ�啝�Ɍ��炵�Q�c�@�ł��ߔ��������荞�݂܂������A�^�}�����łȂ���������}�A���Y�}�A�Ж��}�Ƃ��������j�̒������}�����ׂĐL�єY��A�c�Ȃ����炵���肷�����ŁA��������}�A�Q���}�Ƃ��������}���傫���[��L���Ƃ������ʂɂȂ�܂����B���[�����O�ɂ͂قڌ����Ă����ʂ�̌��ʂ��o�܂������A���͂����������ʂ��o�邱�Ƃ́A����2022�N�Ɏ��{������w�������ŁA���łɖG�肪�����Ă��܂����B
�@���}���A2022�N��w�������ɂ�����e���}�̎x�����ƌ������̃O���t�ł��B�����}��34.7���Ńg�b�v�ł����A���{��������������2017�N�����̎����}�x������52.3���ł�������A�傫�����炵�Ă��܂����B����ł��A2012�N��33.6���A2007�N��32.9���Ƃقړ������炢�ł����̂ŁA�܂����̎��_�ł͂��������x�����������ƌ�����ł��傤�B������������20������Ă����Ȃ����Ǝv���܂��B
2�ʂ͈ېV�̉�ł����A�����Ώۂ̑�w�����̑�w���قƂ�ǂƂ������ƂȂ̂ŁA�֓��Œ���������͂͂邩�ɍ����x�������o��![]() ����킯�ł����A����2022�N�̎Q�c�@�I���ł͈ېV�̉�͑S���ŕ[�����c�Ȃ��傫���L���܂����̂ŁA���̎��_�ł͂��Ȃ�l�C���������ƌ�����ł��傤�B�g�����{�m�����R���i�ЂŊ撣���Ă���N�m���Ƃ����D��ۂ����������ł����̂ŁA���Ɏx�������������ł����B���������A������w�Œ������Ă����Ȃ藎���Ă���ł��傤�ˁB�܂��A���̑�w���ɂ͂��������x�������邩������܂��A�S���I�ɂ͑��������Ă���ł��傤�B
����킯�ł����A����2022�N�̎Q�c�@�I���ł͈ېV�̉�͑S���ŕ[�����c�Ȃ��傫���L���܂����̂ŁA���̎��_�ł͂��Ȃ�l�C���������ƌ�����ł��傤�B�g�����{�m�����R���i�ЂŊ撣���Ă���N�m���Ƃ����D��ۂ����������ł����̂ŁA���Ɏx�������������ł����B���������A������w�Œ������Ă����Ȃ藎���Ă���ł��傤�ˁB�܂��A���̑�w���ɂ͂��������x�������邩������܂��A�S���I�ɂ͑��������Ă���ł��傤�B
�����āA���̎��_��3�ʂ̎x��������������}�������̂ɔ��ɋ������̂ł����A���̌��2024�N�̏O�c�@�I���A����̎Q�c�@�I���ƁA��������}�͑傫���[���c�Ȃ��L�����̂ŁA�w�������̕�������葁�߂ɍ�������}�ɖڂ����Ă����킯�ł��B������5�ʂɂ͎Q���}�������Ă��Ă��āA�������ł�������̐��}�������̂�5�ʂɓ����Ă��邩�Ƌ������̂ł����A����̎Q�c�@�I���̑啝���ɂȂ����Ă���킯�ł��B�����̌�̑I���ŋN���邱�Ƃ����ʂƂ��Č����Ă����킯�ł��B
���̑�w�������̌��ʂ�����̑I���̌��ʂƂȂ����Ă����̂́A1��ڂ�1987�N�����̍ۂ�5��ڂ�2007�N�����̍ۂɂ�����ꂽ���Ԃł��B1987�N�����̍ۂɂ́A�����}�x����28.7���A�Љ�}�x����23.7���ł������A�������́A�����}��30.4�����������̂ɑ��A�Љ�}��8.5�������Ȃ��A�I���ɂȂ����疳�}�h�w�̕[���Љ�}���W�߂�̂��\�z�ł��܂����B�����Ď��ۂɁA1989�N�̎Q�c�@�I���ŎЉ�}�������}��葽���̋c�Ȃ��l�����A�u�R���������v�ƌ���ꂽ���̂ł��B2007�N�����̍ۂɂ́A�����}�x����32.9���A����}�x����25.4���ŁA�������͂��ꂼ��18.3����10.5���ł����B�����āA2009�N�̏O�c�@�I���Ŗ���}���叟���Đ�����オ�N�����킯�ł��B���̒������n�߂������炷�łɐ����ɊS���Ȃ������Ɍ�������w���ł����A�Ȃ�ƂȂ����̎���̋�C�͂���ł����ł���ˁB�ʔ������̂ł��B
�Ō�ɁA��҂̕ێ牻�ɂ��Ĉꌾ�B2000�N��ɓ����������肩��A�u��҂̕ێ牻�v�Ƃ������Ƃ������Ă���A������w�������̌��ʂƂ��ĉ��x�����̌��t���g���Ă��܂����B�������A�����u�ێ牻�v�ƌ����Ă�2��ނ���Ǝv���Ă��܂��B���̐��������܂�ς���Ăق����Ȃ��ƍl����u����ێ��^�ێ�v�ƁA���{�̍��v��D��ɍl����ׂ����Ƃ����u������`�I�ێ�v�ł��B00�N�キ�炢�܂ł̎�҂̕ێ牻�C���[�W�͑O�҂����S�ł������A2010�N����߂��Ĉȍ~�́A�ǂ�ǂ��҂̕ێ炪�����Ă��Ă��܂��B���̒����̒��ł́A2012�N��������A���q���̑�����j�������m�肷���w�����}���ɑ����Ă�����A�ێ������������{���t���x������Ƃ������w�������ɑ����Ă��܂����B2017�N�����ŁA���{�����}�̎x������5���������́A���_�����ł��Ⴂ����͈��|�I�Ɏ����}�x���������Ƃ������ʂ��o�Ă��܂����B
����̑I�����ʂ�����ƁA40�Α�ȉ��̎Ⴂ����͎����}���痣��A��������}��Q���}�ɍs���Ă��܂����킯�ł��B�u����𑝂₷�v����咣���鍑������}�̐����I�����ʒu�͔����ł����A�Q���}�͖��炩�Ɂu������`�I�ێ�v�̗���ł����B2017�N���Ɉ��{�����}���x�����Ă����u������`�I�ێ�v�w�́A���̐Δj�����}�͒������Ɣ��f���A�Q���}��1�[�𓊂��Ă������킯�ł��B���{�����}����́A�u����ێ��^�ێ�v�Ɓu������`�I�ێ�v�̗����̎x���Ă��������}������u����ێ��^�ێ�v�̕[�����W�߂��Ȃ��Ȃ����킯�ł��B�����}�̎x����������ɂ́u��Վx���w�v�ƌ�����ێ�w�̎x�������߂��K�v������A���̂��߂ɂ͍��s���c�⏬�ё�V�𑍍قɂ��悤�Ƃ�����������悤�ł����A�ނ炪�Ȃ����Ƃ��Ă��������}�ł�������}�Ƒg��Ńo�����X�悭�������^�c���悤�Ƃ������A�����}�͂����u������`�I�ێ�v���}�Ƃ��ẴC���[�W��O�ʂɏo���͍̂���ł��傤�B����ێ�x�̍������ɕ��ׂ�ƁA�ێ�}�A�Q���}�A�ېV�̉�A�����}�A��������}�A�����}�A��������}�A�ꂢ��V�I�g�A���Y�}�A�Ƃ��������ɂȂ�A�����}��薾�m�ɕێ炾�Ǝv���鐭�}���o�Ă��Ă��܂��Ă���̂ŁA�u������`�I�ێ�v�w�̎x�������߂��͍̂���ł��B��x���ׂĂ̐��}���K���K���|�����āA�ێ�n���}�A�����n���}�A���x�����n���}��3���炢�ɐ����������ꂽ��킩��₷���Ȃ�̂ł����A���낢��ȗ��Q������܂�����A����ȕ��ɂ͊ȒP�ɂ͂Ȃ�܂���B���ʕs����Ȑ����������܂��ˁB
�l�I�ȗ\���Ƃ��ẮA���LjېV���A�������ɉ�����āA�����ۘA���������ł���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B�ېV��������𒆐S�Ƃ����u����ێ��^�ێ�v���x�����鐭�}�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�����Ƒg��ł��x���w�ɂƂ��Ă͗���ꂽ���͂Ȃ��Ǝv���܂��B���̂܂ܖ�}�̗�����т��Ă��A���̏O�c�@�I���œ}�����g�傷�錩���݂͂܂������Ȃ��ł�����A���{�̐��������肳���邽�߂ɂƂ������ڂŗ^�}���肪�ېV�ɂƂ��Ă��x�^�[�Ȑ헪�ɂȂ�Ǝv���܂��B��������}�Ǝ����}�݂͌��ɑg�߂�Ǝv���Ă���悤�ł����A��������̋ʖؗY��Y�͑���������ƌ���ꂽ��A�����t�����{�C�ōl����ł��傤���A�����Ȃ�����A�ߋ��̐��}�Ɠ����悤�ɂ���������Ă����܂��B��������}�ɕ[����ꂽ�����̗L���҂́A�����}�ᔻ�[�Ƃ��ē���Ă��܂�����A���A�A���������肵����A�L���҂͗���ꂽ�Ǝv���ł��傤�B�������A�����}���ق���サ�A�O�c�@�I�����s��ꍑ������}������ɐL�т����ɂ͘A����������͂��邩������܂���B
![]()
��1044���i�Q�O�Q�T�D�V�D�P�U�j���}�}�b�`���O�������Ă݂�
�@�ŋ߂́A���}�}�b�`���O�Ƃ������̂�����A�����̍l�����Ƌ߂����}�͂ǂ��Ȃ̂������킩��Ɛ�`����Ă���̂ŁA����1�x�g���Ă݂悤�Ǝv���A�����Ă݂܂����B�u���}�}�b�`���O�v�ƃL�[���[�h������Ƃ���������炵���T�C�g���o�Ă����̂ŁA�Ƃ肠�����ANHK�A�ǔ��V���A�����V���A�����V���A�I���h�b�g�R���AJAPAN CHOICE�Ƃ���6�̃T�C�g�ł���Ă݂܂����B���̌��ʂ��ȉ��̕\�ł��B

![]() �@�ŏ���NHK�̃T�C�g�ł���Ă݂��̂ł����ANHK�͑I����̌��҂Ƃ̃}�b�`���O���ʂ��������̂ł������A��ʂɏ��h�Ƃ��������̌��҂����сA�u�N���A���̌��́H�v�Ƃ�����ۂł����B���v������ԍ����l��40�����炢�ł�����A���܂�}�b�`���Ă��Ȃ������ł����B�����悤�ɑI����̌��҂Ƃ̃}�b�`���O������̂́A���ɓǔ��V���̂��̂��������̂ŁA�����������Ă݂��Ƃ���A�g�b�v�ɂ܂��������̌��҂������Ă��܂����B�܂������m��Ȃ����҂ł������A������Ƌ������o�܂����B�������A���̐��}�}�b�`���O�͊�{�I�Ɍl���҂Ƃ̃}�b�`���O��萭�}�̐���Ƃ̃}�b�`���O��������̂ł��傤����A�I����ł͂Ȃ����}�Ƃ̃}�b�`���O������T�C�g�̌��ʂ����Ă݂܂��傤�B
�@�ŏ���NHK�̃T�C�g�ł���Ă݂��̂ł����ANHK�͑I����̌��҂Ƃ̃}�b�`���O���ʂ��������̂ł������A��ʂɏ��h�Ƃ��������̌��҂����сA�u�N���A���̌��́H�v�Ƃ�����ۂł����B���v������ԍ����l��40�����炢�ł�����A���܂�}�b�`���Ă��Ȃ������ł����B�����悤�ɑI����̌��҂Ƃ̃}�b�`���O������̂́A���ɓǔ��V���̂��̂��������̂ŁA�����������Ă݂��Ƃ���A�g�b�v�ɂ܂��������̌��҂������Ă��܂����B�܂������m��Ȃ����҂ł������A������Ƌ������o�܂����B�������A���̐��}�}�b�`���O�͊�{�I�Ɍl���҂Ƃ̃}�b�`���O��萭�}�̐���Ƃ̃}�b�`���O��������̂ł��傤����A�I����ł͂Ȃ����}�Ƃ̃}�b�`���O������T�C�g�̌��ʂ����Ă݂܂��傤�B
�@�����}�Ƃ̍��v���́A�ǔ��ƒ����ł�64�C65���ƍ����Ƃ��Ƀg�b�v�ł����A�����ł�46����8�ʁAJAPAN CHOICE�ł͂킸��20����6�ʂł��B�X�̃T�C�g������Ɋւ��鎿������Ă��Ă���ɉ��邱�Ƃō��v����������̂ł����A�����悤�Ȏ��₪�������̂̐q�˂�����I���������ꂼ�ꏭ��������Ă�����A�ǂ��ɏœ_��u���č��v���𑪂�̂����Ⴄ�̂ł��傤�B���̕\�����Ă��邾���ł́A�Ȃ��Ȃ��킩��ɂ����̂ŁA5�̃T�C�g�̌��ʂ����v���̕��ςƂ��Ă܂Ƃ߂Ă݂܂����B���ꂪ�E�̕\�ł��B
�@���ʂ�������鐭�}���T�C�g�ɂ���ĈႤ�̂ŁA2�̃T�C�g�����Ō��ʂ��o�Ă���16���}�̍��v���Ń����L���O������Ă��܂����A4�̃T�C�g�Ō��ʂ��o�Ă���10���}�A5�̃T�C�g�Ō��ʂ��o�Ă���8���}�ł̌��ʂɂ����ڂ��Ăق����Ǝv���܂��B4�����Ō���ƁA�����}��58.8����1�ʁA�����ō����A�����ƂȂ�܂��B5�����Ō���ƁA�����A�����A�����̏��ƂȂ�܂��B������3�}�ɓ��[�������Ƃ͈�x���Ȃ��̂ł����A���̓e�[�}�ɂ���Ă̓��x������������ێ炾�����肵�܂��̂ŁA�g�[�^������ƌ��ǒ������̕ێ�n���}�����ΓI�ɂ͍��v������⍂���Ƃ������ƂɂȂ�̂�������܂���B�܂��ł�50����ł�����A���܂荂���}�b�`���O���ł͂Ȃ��Ƃ͎v���܂����B
�@�b��̎Q���}�Ƃ̓}�b�`���Ȃ������ł����A�ꂢ��⋤�Y�}�Ƃ��}�b�`���Ȃ��悤�ł��B�܂��A�������낤�ȂƎv���܂��B�ЂƂ����̌��ʂ��Ƃ��܂�s���Ƃ��܂���ł������A6������Ă݂ăg�[�^���Ō���ƁA�܂��m���ɂ���Ȋ������ȂƂ����C�����Ă��܂��B�������A���[�Ɋւ��Ă͑��ɂ��l�X�ȗv�f���l�����čs�����܂��̂ŁA���̐��}�}�b�`���O�ŏ�ʂɗ������}�ɓ��[����Ƃ͌���܂���B
![]()
��1043���i�Q�O�Q�T�D�V�D�P�T�j�Q���}�̐L���͂���
�@������\���ꂽNHK���_�����̐��}�x�����ŁA�Q���}��5.9���ŁA�����}��24.0���A��������}��7.8���Ɏ�����3�ʂɂȂ��Ă��܂����B�܂��A�����̒����V���ł��A�Q���}�͔���ł͖�}�g�b�v�̋c�Ȃ����\���������Ȃ��Ă����Ə���͂�����Ă��܂����B���Ր���l�C�����܂��Ă��Ă���A�I�Ր�ɂ����Ă܂��܂������𑝂������ł��B3�N�O�̎Q�c�@�I���̑O�ɍ���1�c�Ȃ�����������̐V�������}�Ȃ̂ɍ���������̂������ł��B����܂łɂ��A�V���R�N���u�A���{�V�}�A���{�ېV�̉�ƐV�����ł������}���ꎞ�I�ɍ����x���āA���̌������邱�Ƃ͂���܂����̂ŁA�Q���}�̏ꍇ�������Ȃ�̂�������܂��A�����������炱��܂ł̐��}�Ƃ͈Ⴂ�A�����ɐ������Ă����\���������Ă���C�����܂��B�Ƃ����̂́A����x���҂𑝂₵�Ă���ő�̌����ł���Q���}�̃L���b�`�t���[�Y�ł���u���{�l�t�@�[�X�g�v���m��I�Ɏ~�߂�w�����ݓI�ɂ͂��Ȃ肢��ƍl�����邩��ł��B
�@�u�����t�@�[�X�g�v�̓g�����v���ŏ��ɑ哝�̂ɂȂ������ɏ����A���ꂪ���낢��ȂƂ���Ŏg����悤�ɂȂ����킯�ł����A����ȑO����ږ��������������Ă������[���b�p�����ł́A�����I�ɓ����悤�Ȃ��Ƃ������鐭�}�����킶��Ǝx�����g�債�Ă��Ă��܂����B�O���[�o���[�[�V�����ɂ�萶�����ꂵ���Ȃ����Ǝv���l�X�́A�������S��`��ł��o�����}���x������悤�ɂȂ���̂ł��B�t�����X�ł��h�C�c�ł��ɉE�ƌĂ�鐭�}���c�Ȃ�L���Ă��܂��B�Q���}�������������}�̂ЂƂł��B����Љ�ł́u���l����F�߂悤�v�u���E�̕��a����낤�v�Ƃ������������u�����������v�Ƃ��Č���Ă��܂����A���̗��Łu�{���͈Ⴄ��Ȃ����v�u���{�Љ�͂܂����{�l�̂��Ƃ��l����ׂ����v�Ƃ����z���l�̓��ɗ��ߍ���ł���l�������Ȃ��Ă��Ă��܂��B���̐��ɏo���Č����Ȃ��v�����A�V���v���Ɍ��ꉻ���Ă���̂��Q���}�Ƃ�����ۂ����l�������Ȃ��Ă���̂ł��傤�B�ێ�}���咣���͎̂Q���}�Ǝ����悤�Ȃ��̂��Ǝv���܂����A�g�b�v�ɗ��l���̃C���[�W�ő傫�ȍ������Ă��܂��B
�@���������Ă������Ȃ������z���l�����ꉻ���Ă��鐭�}�Ƃ��Đl�C���o�Ă��Ă���Ȃ�A���̂܂����}�ƘA��������g�肹���ɁA�u���{�l�t�@�[�X�g�v�̓Ǝ��H�����т�������A10�N�キ�炢�ɂ��Ȃ�傫�Ȑ��}�ɂȂ��Ă���\��������C�����܂��B���E�̒����͎������S��`�A�r�O��`�ł��B�Q���}�͂��̗���ɏ���Ă��܂��̂ŁA����ɐL�тĂ����\���������ł��B
![]()
��1042���i�Q�O�Q�T.�V�D�P�R�j���������A����Ȋ����Ȃ̂���
�@�V���̏��߂ɑ傫�Ȓn�k�����邩������Ȃ��Ƃ����\������A���g�J���Œn�k�������Ă����̂ŁA�n�k���|�ǂ̎��́A�e���r�̃j���[�X�����Ă���ƌ��Ȃ��Ƃ���l���Ă��܂��̂ŁA�������e���r�̃j���[�X�������ɁA�C���^�[�l�b�g�Ŏ������ɂ����߂���鑊�o��h���}�̏�����Ă��܂����B�n�k�̂��Ƃ��l���Ȃ��Ă悭�A�����̈����j���[�X�����Ȃ��悤�ɂ��Ă�����A�Ȃd�ꂵ���C���������ĉ߂������Ƃ��ł��܂����B����ȂP�����߂����Ďv�������Ƃ́A���������A����������ƎႢ�l�͂���ȕ��ɉ߂������ƂŁA���̒��ɂ��܂舫�����Ƃ͋N���Ă��Ȃ��悤�ȍK���ȋC�����ʼn߂������肵�Ă���ȂƎ������܂����B�����̂��ƂƂ������̎�̂��Ƃ����l�b�g�Œ��ׂĂ�����A�ȂK���ɕ�点���ł��傤�ˁB
�@�u�`�̑O���ŁA�g�����v�ł̂��Ƃ�NATO�e�����h�q���GDP����グ��b�Ȃǂ����Ă��u����Ȃ��Ƃ��N���Ă���Ƃ͒m��܂���ł����v�Ƃ������z�������������̂��A�Ȃ�قǂ����������ڐG�̎d�������Ă���Ɠ�����O�ɋN����ȂƂ킩��܂����B���͂P�������ł܂������̂悤�Ƀe���r�̃j���[�X�������������鐶���ɖ߂�܂������A�Ⴂ�l�͂���ȕ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł���ˁB���{�̋ߖ����ɂ͑����̖�肪����Ǝv�����A����Ȃ�Ƀe���r�̃j���[�X�ł����낢��Љ�Ă��܂����A�����������ɐڐG���Ȃ��l����ɂǂ�ǂ�Ȃ��Ă����Ă��܂��͕̂|�����Ƃ��ȂƎv���܂��B
�@�����ŁA������ƎЉ�S���������l������YOUTUBE�Ƃ��ł��̃e�[�}�ɂ��Ē��ׂ悤�Ƃ�����A�ߌ��ȃj���[�X���莟�X�Ɍ��邱�ƂɂȂ��Ă��܂���ł��傤�ˁB�e���r��V���Ƃ������}�X���f�B�A�̕ɂ��m���ɕ肪����܂����A�A���S���Y���ŋɒ[�ɕ���������ڂɂ��邱�ƂɂȂ�SNS����̏����͂܂��ȋC�����܂��B���Ȃ��Ƃ��ASNS�̃j���[�X�����łȂ��A�e���r��V���̃j���[�X���ӎ����Ēm�낤�Ƃ��Ȃ��ƁA��Ȃ��Љ�ɂȂ��Ă��܂��C�����܂��B�l�X�ȏ��������������悤�ɂ��Ăق������̂ł��B
![]()
��1041���i�Q�O�Q�T�D�U�D�Q�W�j����̍u�`�����Ƃ�����
�@�������x����������ǂ�6�����{�ŁA��N�Ȃ炠�Ɖ���Ŏ��Ƃ��I���Ȃ��Ǝw�܂萔�����肵�Ă������̂ł����A���N�͋C�������Ⴂ�܂��B���������Ō�̔N�ŁA���N����Ă������̍u�`���w���̑O�Œ���̂͂��ꂪ�Ōォ�Ǝv���ƁA����̍u�`�����Ƃ����������܂��B���TLMS�Ɋ��z�������Ă�����Ă��܂����A���Ƃ���h�����Ă���Ă���ȂƎv���銴�z�ɏo��ƁA�������Ȃ�܂��B���ɁA1�̊�b�Љ�w�Ɋւ��ẮA20���I����Љ�w��U�̎��Ƃ�1�`2�N���X�͂����ƒS�����Ă����̂ŁA�v�����ꂪ�����ł��B������������I�Ȏ��Ƃ��D�܂Ȃ����������Ȃ��Ȃ��ł����A���͍D���ł����B�Ȃ�ƂȂ��Љ�w�Ɏ䂩��ē��w��������ǁA�Љ�w���ǂ������w�₩���܂�悭�킩���Ă��Ȃ��w�������ɁA�Љ�w�Ƃ͂����������͓I�Ȋw��Ȃ�Ɠ`����̂́A�����̃L�����o�X�ɊG��`���悤�Ŋy���������ł��B
���N��1�́A�����猩���51�����̎q�����ł��B�O�C�Z�ŏ��߂ĎЉ�w����̎��Ƃ�����������1�͂킸��9�Ή��̎q�����ł����B42�N�Ƃ��������N���̊ԁA�܂������قȂ鐢��ɂ������Ǝ~�߂Ă��炦����Ƃ�����Ă����Ƃ������M������܂��B����w�������̑c����ɋ߂��N��ł����A����ł��w�������ɓ͂����Ƃ��ł��Ă���Ǝv���Ă��܂��B�Љ�̕ω��A�w�������̕ω���������Ɣc�����邱�Ƃ��A�e����ɓ`�����Ƃ�����|�C���g���Ǝv���܂��B�Љ�w�Ƃ����w��͂�������������Ƃ�K�v�Ƃ���w��ł����A���ꂾ���łȂ����̏ꍇ�́A��w���̉��l�ϒ�����35�N8����������Ă������ƁA25�N�ȏ�ɂ킽���Ă���HP�Ŏ��㕪�͂��������Ă������ƁA�����Č����w���⑲�ƌ�������q�����Ɗy������������t�������Ă������ƁA����炷�ׂĂ��قȂ鐢��ɓ͂����Ƃ������Ŗ��ɗ������Ǝv���Ă��܂��B
������ɂ���A���T���Ƃ��n�܂�O�ɁA���̘b������͍̂Ōゾ�ȂƎv���ƁA�C�͂��N���Ă��܂��B2�ȏ�����̗��_�Љ�w����͂蓯���悤�Ȏv���������Ă���Ă��܂��B����ȐÂ��ȍ��g���̂悤�ȓ��ʂȋC�����͒�N�ԍۂ̋��t�������ĂȂ����̂��ȂƎv���ƁA���\���̍Ō��1�N�Ƃ����̂������Ȃ��ȂƎv���܂��B2�ȏ�̊w�������ɂ͂܂��H�w���̗��_�Љ�w�̍u�`���c���Ă��܂����A1�̊�b�Љ�w�͎��������Ă�����3�T�ŏI���ł��B�I���j�o�X�́u�Љ�w���_�v�Ƃ������Ƃł���2��A1�Ɍ����Ē���@�����܂����A�v������̋�����b�Љ�w�͂���3�T�\�\��������������2�T�\�\�ŏI���̂��Ǝv���ƁA���S�[���ł��B�I���͎̂₵���Ƃ����v�����������̂ł����A�ЂƂЂƂ��Ō�ȂȂƂ��Ƃ������v���邱�̋C�������ɍu�`�Ɍ����������Ǝv���܂��B���N��1�����ɁA�u�Ō�ɕЋː搶�̎��Ƃ��Ă悩�����v�Ǝv���Ă��炦��悤�ɁA�c��̍u�`���M����葱�������Ǝv���܂��B
![]()
��1040���i�Q�O�Q�T�D�U�D�Q�Q�j��㖜���T�K�L�i���̂Q�j
�@���3��ڂ̑�㖜���ɍs���Ă��܂����B����܂ł�2���1�l�ʼn���Ă��܂������A����͂��ł�11��ڂƂ��������q�Ɉē����Ă��炤�`�ʼn��܂������A������11����s���Ă��邾�������āA�S�R�m��Ȃ�������������낢�닳���Ă��炢�y���߂܂����B��Ԗʔ��������̂́A�����O�������o�X�ւ̏�Ԃł����B���Q�[�g�k�^�[�~�i�������Ԃ��A�܂�������ƕ��ԑ��z���p�l�������Ȃ���A���ԃN���}�̔�����i���͂܂��������ł��Ȃ��悤�ł����j�̎�������AEXPO�A���[�i�̊O�������A�C�̏�ɒ���o���Ă���剮���̉��𑖂�A�����̊O�����H�ɓ���A���F�w�̊O�������A�܂����Ɍ������܂��B�r���E��̍L���~�n��IR�̌��ݗ\��n�ŁA���łɓy����ǍH�����n�܂��Ă���A�傫�ȃN���[���Ԃ�����������Ă��܂��B���̖��F�̒����I�ȑ_���́A����IR�̕��ɂ���킯�ŁA���������A�����H�����n�܂��Ă���ȂƏ��߂Ēm��܂����B�����q�̐����ɂ��A���̖��F�w�̉��D����1���������ł����AIR���ł������ɂ͋t���ʂɂ����D�����ł��AIR�Ƃ͒n�����łȂ��邻���ł��B���ăo�X�ɖ߂�ƁA����IR�~�n�̂͂�������ɋȂ�������ɏI�_�̃����O���o�X�^�[�~�i���ɒ����܂��B���̖����̊O�����߂���o�X�̂��Ƃ͒m��Ȃ��l�������Ǝv���܂����A�l�I�ɂ͔��ɖʔ��������ł��B
�@��A���邱�Ƃ��ł����p�r���I���ł͒����ق����ɂ悩�����ł��B�܂���������Ă���킯�ł͂Ȃ��ł����A����܂Ō������ł͂����Ƃ��[�����Ă��Č�����������܂����B�Ñ�̊������L���ꂽ�M�d�Ȉ╨����n�܂�A�L���Ȏ��R�Ǝl�G���D��Ȃ��̂���̒����̐������Љ��A�����̌𗬁A���㒆���̔���Ƃ�����炵�Ԃ�A�����ĉF����[�C�ւ̒T���܂ŕ��L���W�����Ă��܂����B�Љ��`�������Ƃ�����ۂ͂قƂ�Ǐo���Ă��炸�A�����F�𔖂߂Ă����̂��D���������Ď~�߂��A�悩�����Ǝv���܂��B���݂��݁A���A�����͐����̂��鍑���ȂƎv�킳��܂����B���܂������������Ă��Ȃ�������������܂��A�e���r�ԑg�ő��̍��̃p�r���I���͂悭�Љ��Ă��銄�ɂ́A�����̃p�r���I���Љ�͌������Ƃ�����܂���ł����B�Ȃ�ƂȂ��e���r�ǂ͒����̃p�r���I���̏Љ������Ă���̂��ȂƎv����������܂����A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ����ȁB55�N�O��1970�N�̑�㖜���̎��́A�p�r���I�����o���Ă����̂́A���ؖ����i���̑�p�j�������킯�ł�����A�ω��������Ƃ��傫���\��Ă��邱�Ƃ̂ЂƂł��B���Ȃ݂ɁA���͔��ɐ���������ȂƊ����������ł����A���̂܂܂����Ɛ������������ǂ����͂킩��܂���B����̉₩�ȉf���̒��ŁA�Ⴂ���l������Ƒ��A�q�ǂ��������y�������ɉ߂����Ă���f������������f���o����Ă��܂������A�����̒����͍�������������}���ȏ��q�����i��ł���̂ŁA���\�N��ɂ́A���̂悤�Ȑ����͂Ȃ��Ȃ��Ă���̂�������܂���B���{��80�N��́A���E�ň�Ԑ����̂��鍑�������̂ɁA40�N�قnjo���������ł́A�}���K�ƃA�j���Ɗό������ƐH��ɂ��鐊�ޓr�㍑�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��ł��A�Ƃ肠�����A���̑�㖜���̒����ق͂��E�߂ł��B50���҂��ƌ����܂������A�X���[�Y�Ȑl�̗���Ŕ�����25���҂����炢�œ��ꂽ�̂��悩�����ł��B
![]()
��1039���i�Q�O�Q�T�D�U�D�P�W�j�V�u�����������v
�@�����ɕK�v�ȁu�����������v�Ƃ����ƁA���Ắu�ٖD�^�^�^�����^����^�|���v�Ɋւ���\�͂ł������A���₻��Ȃ��Ƃ������l�͂����△�ƂȂ�A�ŋ߂̎Ⴂ�����ł��́u�����������v��������l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ǝv���܂����A���V�����u�����������v���Ⴂ�����̊ԂōL�܂���邻���ł��B����́A�u�������^�m��Ȃ������^�������^�Z���X�����^�����Ȃv��5�������ŁA����5�̌��t�����ɐD�荞�ނƁA�j���͊�сA���܂��g�������̓��e��̂������ł��B�̂Ō����A������u�Ԃ�����v�p��̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł��傤���A�m���ɂ����̌��t���g���ď��ɑ��Ƃ�ł��ꂽ��A�����C���悭�����Ă��܂������ł��B�v�Z���Ă���Ă���̂��ǂ����킩��܂��A������ƈӎ����ăe���r�����Ă���ƁA�m���ɎႢ�����^�����g���A���邭���C�悭�����������t�����x���g���Ă��āA�R�~���j�P�[�V���������Ɏ���Ă��܂����B
�@���������Ɉʒu�t���đ�������߂�悤�ȗp��ł�����A�����������Ă����ȋC�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B���������̌��t���₷���̂́A��͂�Ⴂ���������Ȃ̂ł��傤�ˁB�j����킸�N�����Ȃ�ɂ����Ă���l�������̌��t���g���Ă�����A�u���̂�m��Ȃ��l�v�Ɣn���ɂ���Ă��܂������ł��B����ɒj���̏ꍇ�́A�Ⴍ�Ă������Ȃ��A���̂�m��Ȃ��ƃ��b�e����\����̂́A��͂�v���X�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
�@��������čl���Ă݂�ƁA���ς�炸�����͂���ȂɌ������o���Ȃ��������ŁA�j���͌������K�v�Ƃ����A�̂Ȃ���̒j���ς��܂������Ă���݂����ł��ˁB�ł��A�悭�l���Ă݂�ƁA����͂ǂ�ǂ�i�݁A�N�z�҂̕����m��Ȃ����Ƃ���������܂��B���ہA���̓[�~���̕��Ȃ���A�u�ց[�A�����ȂB�m��Ȃ������Ȃ��v�Ƃ����ʂɌ����Ă��܂��B��L��5�̌��t�́A�{���͂��������Ă��Ȃ��̂Ɏg���Ă���Ƃ����猙�ł����A�����Ƒ���̘b�ɋ����������ĕ����Ȃ��玩�R�ɏo�錾�t�Ȃ�A���ɖ��͂Ȃ��C�����܂��B
�@�m��Ȃ������[�����ƂɁA�f���Ɂu�m��Ȃ������v�Ƌ����A�u�������Ȃ��v�Ɗ��S���邱�Ƃ́A�j���N����킸�Ɏ��R�Ɏg���Ă������t�ł���ˁB�ςɁA�V�u�����������v������ӎ����Ďg��Ȃ��悤�ɂ��悤�Ƃ��A�t�ɑ���ɋC�ɓ����邽�߂Ɏg�����Ƃ��ɂȂ�Ȃ��łق����ȂƎv���܂��B�����l����ƁA���̐V�u�����������v�͂���ȏ�L�܂�Ȃ����������ȂƎv���܂��B
![]()
��1038���i�Q�O�Q�T�D�U�D�P�S�j�������胉�e�����������Ă��܂���
�@����̃e���r�ԑg�ŁA��㖜����EXPO�A���[�i�Ƀ_���X���������l��2000�l�قǏW�܂��āA�X�e�[�W�̉̎肽���ƃ_���X������Ƃ����C�x���g���s��ꂽ�l�q�����f����Ă��܂����B�Ⴂ�������������S�ł������A�݂�Ȓe����悤�ȏΊ�������Ă��Ď��Ɋy�������ł����B���Ă��邾���̂���������C�ɂȂ��قǂł����B�����������ŁA���{�l���ς�����Ȃ��Ƃ����v���������N���Ă��܂����B�m���A�̂�����{�l�����e�����������Ă����̂ł͂Ƃ������͂��������C������ȂƒT������A�Ȃ��25�N�O�ł����i�Q�ƁF�u��22���@�u���{�̖����͐��E���A�ށv���ȁH�i�Q�O�O�O�D�V�D�Q�W�j�v�B���̍����A�̂����Ƃ�x�邱�Ƃ��͂��߂Ƃ��ĕ\�o�I���y���y���ސl�������A���ʓI�m�I�y���݂����߂�l������X���ɂ��邱�Ƃ��뜜���Ă��܂������A��������25�N�A�\�z�ʂ�Ƃ������A�\�z�ȏ�ɕ\�o�I���y�����߂�u�����͋��܂�A���ʓI�m�I�y���݂����߂�u�����͎�܂��Ă��܂��B�_���X�ȊO�ł��A�t�@�b�V������O���̗ǂ���ǂ�����SNS�Ŕ�I����A�f����H�ו���SNS�ɂ�����A��������������B��������\�o�I�y���݂����߂�s�ׂł��B�����ŁA�l����A���͂������Ƃ������s�ׂ́A���Ȃ�̕�����AI�ɔC���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��Ă���A�����Ŗ{��ǂށA�l����A���͂������Ƃ������Ƃ��y�������ƂƎv���l�͂����킸���ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B���̗���͂܂��܂����������Ă����̂ł��傤���A�t�]�����邱�Ƃ�����̂͂킩���Ă��܂����A�l�I�ɂ͂ǂ����Ă��D�܂��������Ƃ͎v���܂���B���߂ĕ\�o�I�y���݂����߂��A���ʓI�E�m�I�y���݂����߂�Ƃ������������̐l�ԂɂȂ��Ăق����ȂƊ肤�����ł��B
![]()
��1037���i�Q�O�Q�T�D�U�D�P�S�j�������u�ׂ�ڂ��v
�@3���̎��_�ō����]��������̓h���}�u�ׂ�ڂ��v�i�Q�ƁF��1024���@��̓h���}�u�ׂ�ڂ��v�i�Q�O�Q�T�D�R�D�R�O�j�j�ł����A�����̂Ƃ��떣�͂������Ă��܂��B�O�����x�������ŕ��Ԃ̉Ԋ@�u����v�A�����g���������s�����l�̌��Z�A�����Ĉ��c�������镽�ꌹ���Ƃ��������͓I�ȉ��Z�����Ă����l�������ׂđޏꂵ�A�������T�Ԃ͋Y��҂��������S�ɘb������Ă��܂����A���ꂼ��Ȃ�ƂȂ����O�͕��������Ƃ�����l�����ł����A�h���}�����Ă��Ă��A���̖��͂������`����Ă��܂���B�����A�݂�Ȏ�������Ŕn���X�X�������̂�����Ă��邾���ŁA���Ă��Ėʔ�������܂���B�܂��A�Ԋ@�����ŕ��Ԃ̌�͕����y�������Ă��܂����A�Â����邢�����������o�߂���ޏ��ł́A���ŕ��Ԃ��o���Ă����Ԋ@�̂����݂��܂������o�܂���B�����ȏ��D����ł͂Ȃ��ł����A����̉Ԋ@�ׂ͉��d�������ł��B�c���e�q�A���ɑ��q�̓c���Ӓm��������{��X���ɖ��͂�����܂���B�܂��A�n�ӌ��̈ӎ����d���߂��Čl�I�ɂ̓C���[�W�������܂���B�Ƃ������ƂŁA�ŋ߂́u�ȂA�����ЂƂ��Ȃ��A�A�A�v�Ǝv���Ȃ��猩�Ă��܂��B
�@�ł��A����͎̂~�߂܂���B������Ӓm���E����A�c���h�����r����͂��ł����A�̖��̑�u���[�N�A��̊G�t�E���F�֎ʊy���ǂ��������ɏo���Ă���̂��A�Ƃ��������҂����y���݂����邩��ł��B���Ƃ��ƁA���Ȃ���j�D���̒ʌ����h���}�ł����A�������ɂ��������h���}�`�b�N�ȓW�J�ɂ��Ȃ��ƁA���j�D���̎����҂ɂ��O�����Ă��܂��܂��B��������̃h���}�`�b�N�ȓW�J�Ɋ��҂������Ǝv���܂��B
![]()
��1036���i�Q�O�Q�T�D�U�D�X�j���{��`�ɂ���
�@�ĒÌ��t���u�ׂ�ڂ��ɖʔ��������v�Ɣ����������ƂŁA2002�N�ɏ��ł��o���ꂽ�|���m�搶�́w���{��`�̖v���@�ς��䂭�G���[�g�����x�i�����V���j���ău�[���ɂȂ��Ă���ƕ����A����͂�������ǂݒ����āA���{��`�ɂ��čl�@���Ă݂悤�Ǝv���A��قǖ{��ǂݏI���A�u�{��ǂ����I�f����ς悤�I�v�̃R�[�i�[�Ɋ��z�i1072�D�|���m�w���{��`�̖v���@�ς��䂭�G���[�g�����x�����V���j�������܂����B�ŁA���C���͋��{��`�ɂ��Č�邱�ƂȂ̂ŁA�����������Ǝv�����̂ł����A���������Đ̂Ȃ����Ă��Ȃ��������ȂƒT���Ă݂���A�����|���m�搶�́w�w���M���̉h���ƍ��܁x�i�u�k�Њw�p���Ɂj�̊��z�i909�D�|���m�w�w���M���̉h���ƍ��܁x�u�k�Њw�p�����j���������R�[�i�[�ɁA�������Ǝv�������Ƃ̍��q�����łɏ����Ă���܂����B�ȉ��̕����ł��B
�u���̖{��ǂ݂Ȃ��炸���ƍl���Ă����̂��A�u���{�v���ĉ����낤�Ƃ������Ƃł��B���{��`���x�z�I�����ɂȂ����������Z����̑�w�œǂ܂�Ă������{���́A���̎����猩��Ɠ��ɓǂޕK�v���Ȃ��{�̂悤�Ɏv���Ă��܂��܂��B���҂��悭���グ��w�O���Y�̓��L�x�Ƃ����{�Ɋւ��ẮA���N�O�Ɉ�x�����Ɠǂ�ł݂悤�Ɠǂݎn�߂Ă݂��̂ł����A�܂������ʔ����Ȃ��r���œǂނ̂���߂Ă��܂��܂����B�܂��A60���Ă���ǂނ悤�Ȗ{�ł��Ȃ��̂ł��傤���B���̋��{���Ƃ��ċ������Ă���{���ǂ݂����Ǝv���{�͂قڂ���܂���B
�@�����g�A�Ǐ��͑���Ǝv�����A�m���������Ƃ����ɑ���Ǝv���Ă���̂ł����A�u���{��g�ɒ�����v�Ƃ����̂́A������������g�ɒ������炢���̂��A���������Ă悭�킩��Ȃ��Ƃ��낪����܂��B���đ�w�ɂ́u���{�w���v������A���ł��u���{�Ȗځv�Ƃ������O������A�����Ⴋ���ɂ͓N�w����v�z���A���������l���鏑�ЁA���w�Ȃǂ��蓖���莟��ǂ��Ƃ�����̂ł����A���u���{�v�Ƃ͉����Ɩ��ꂽ�炤�܂��������܂���B�ł��A���̋��{���d�����オ�����������Ƃ������Ƃ����̖{�ōĊm�F���A���{���ĉ��Ȃ̂������߂čl���Ă݂����Ǝv���܂����B(2022.10.7)�v
�@3�N�O�ɂ��������Ă��܂����i�j�����ɏ����Ă���悤�ɁA������w�ɓ����������A������u���{�v��g�ɂ������Ǝv�����̂ł��傤���A�}���N�X��`�W�̖{�A��g���ɂ̗l�X�Ȗ{�A�������_�Ђ́u���E�̖����v�V���[�Y�A���w�������a�����]���O�Y�A�Ȃǂ����X�ɓǂ����Ƃ������̂ł����B���������{��ǂ�ł��邱�Ƃ��A�G���[�g��w���̂���ׂ��p�Ǝv���Ă����̂ł��傤�ˁB1970�N�㔼�̑�w�����ŁA���łɑ����̑�w�ŋ��{��`���v�����n�߂Ă������ł������A���̒ʂ��Ă�����w�͂��Ԃ��ԍŌ�܂ŋ��{��`�I�ȕ��y���c���Ă�����w�������̂ŁA�u�}���N�X��ǂ܂����ĕ��������ȁv�Ȃ�Ĉ̂����Ɍ����l���������܂����B
�ł��A��������u���{�v�Ƃ͉����͂킩���Ă��Ȃ������C�����܂��B�L���Ȋw�҂�v�z�Ƃ̏��������̂�ǂ��Ƃ�����ƌ�����������������������܂���B���ǁA���́u���{�v�ɋ�����������������ƂȂ��A�����Љ�����ߑ����Ă����Љ�w���ʔ����Ȃ�A�u���{��`�v����͂ǂ�ǂ�Ă������C�����܂��B���t�ɂȂ��Ă�����A�w�������ɒm���ƌo���𑝂����ƂŐl�͖��͓I�ɂȂ�Ƃ͌��������Ă��Ă��܂����A�u���{��g�ɂ��Ȃ����v�ƌ��������Ƃ͈�x������܂���B����HP�́u�{��ǂ����I�v�̃R�[�i�[�ł��A���{���ƌ�����悤�Ȗ{�͂قƂ�ǏЉ�����Ƃ͂���܂���B
�����̒m���������Ƃ́A�u���{�v�����߂��ł��厖�Ȃ̂ł��傤���A�u���{�v�̊j���Ȃ��悤�Ȓm���́A�N�w��v�z�̂悤�Ȃ��̂ł���A�Љ�ۂɊւ���f�[�^��m���ł͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B������Љ�w�ҁA�Љ�w����҂Ǝ��o�������قǁA���ʂɏ��������������N�w��v�z����͉��������Ă����܂����B��ʓI�ȑ�w�����������u���{�v�ɖ��͂͊����Ȃ��Ȃ��Ă������̂ŁA���͂�u���{��`�v�͗��j�I�ɑ��݂����l�����������ƌ����Ă��܂��Ă����C�����܂��B�m���ƌo����ςݏグ�邱�Ƃ͑厖�ł����A�u���{��`�v�������邱�Ƃ͂Ȃ��ƌl�I�ɂ͎v���Ă��܂��B�ɂ�������炸�A�w���{��`�̖v���x�Ƃ����^�C�g���̖{�������̂́A�܂������u���{�v�Ƃ������t�ɖ��͂�������l����������Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�ˁB
![]()
��1035���i�Q�O�Q�T�D�U�D�R�j�����ΗY������
�@�����C���^�[�l�b�g���J������A�����l�R�ē̒����ΗY�����S���Ȃ����Ƃ����j���[�X���ڂɔ�э���ł��܂����B���������A���ɂ��̓������Ă��܂������Ɨ�ÂɎ~�߂܂������B�Ȃ����̗�Â���������Ǝc�O�ȋC�����܂����B�Ƃ����̂��A�����ΗY�́A�قƂ�ǃt�@���Ƃ������̂ɂȂ������Ƃ��Ȃ������A���S���������炢���N��ɂȂ�܂Ńt�@���������ƌ����鐔���Ȃ��l����������ł��B
�ނ͏��a33�N�ɋ��l�R�ɓ��c���A�V�l�ł��������̔N�Ƀz�[���������Ƒœ_�����l������劈��ł����Ƃ����Ԃɖ싅�E�̑�X�^�[�ɂȂ�܂����B�䂪�ƂɃe���r���������̂͏��a33�N12���������̂ŁA���͗��N����e���r�ɂ�������Č��Ă��܂����B�����̒��ň�Ԗ싅�M�������������w���̍��́A���W�I�̒��p�������畷���n�߁A�e���r�Œ��p���n�܂�ƃe���r��^���Ɍ��Ă��܂����B�قڒ����̌l�t�@���݂����Ȃ��̂������̂ŁA�������}�łŃA�E�g�ɂȂ����肵����A�e���r�������Ă��܂����炢�̃t�@���ł����B���ނ̓��́A�����̓d�C�������ċ����Ȃ���e���r�����Ă��܂����B�ēɂȂ��Ă�����A�����̃��j�t�H�[���p�ƏΊ炪�������ċ��l���������Ă��܂������A�ނ����j�t�H�[����E���ł���́A�v���싅�ɑ��鋻�����̂������܂����B���ꂪ�A�A�e�l�I�����s�b�N�œ��{��\�`�[�����ē��ė�����ƕ������̂ŁA���x�͓��{��\�`�[�����������悤�Ǝv���Ă��܂������A���̃^�C�~���O�Ŕނ��]�[�ǂɓ|��A�ē��ł��Ȃ��Ȃ�A���͖싅���̂ɊS�������Ă����܂����B
���̂��炢�̃t�@���������̂ŁA�����̃j���[�X�ɂ����Ǝ������V���b�N���邩�Ǝv�����̂ł����A�����ł��Ȃ������̂ŁA������Ƌ���������ł��B��͂�A�|��Ă��烊�n�r�����撣���Ă��Ȃ蕜���������̂́A�����D���������̂́A����Ƃ��������ΗY�������ȂƉ��߂Ďv���܂����B�ނ���A�|�ꂽ����悭�撣��܂����ˁA����J�l�Ƃ������₩�ȋC���ł��B
�y�NjL�i�Q�O�Q�T�D�U�D�W�j�z�U���R������l�X�Ȓ����ΗY���W���g�܂�Ă��܂������A���������Ȃ���A�ӂ��قǎv�������Ƃ�����A�����Ă������Ǝv���܂����B�ЂƂ́A�����ΗY�Ƃ����X�^�[�͂������{�l�̓w�͂�����܂����A���オ������X�^�[�������Ƃ������Ƃł��B���A��J�I�肪�劈������Ă��܂����A�ނ��Ȃ��o�ꂵ�X�^�[�ɂȂ������́A�܂��ɔނ̑f���炵���˔\�ȊO�ɐ������邱�Ƃ͂ł��܂���B�������A�����ΗY���Ɋւ��ẮA���オ���x�������ŁA�ƒ�Ƀe���r��1��A�싅�����͋��l�����Ƃ������ゾ�������Ƃ��傫���e�����Ă��܂��B���i���ʐ��Y�̎���ŁA��O�݂�Ȃ��������̂����߂Ă�������ł����B������������̏ے��Ƃ��Ē����ΗY�Ƃ����X�^�[���a���������̂ł��B���݂̂悤�ɁA�l�X�Ȋy�����I���������钆�ł́A��J�I�肪�ǂ�Ȃɑf���炵���L�^������Ă��A�����ΗY���̂悤�ȍ����I�X�^�[�ɂ͂Ȃ�܂���B�싅�ȊO�ɂ��y���߂���̂�����A�싅�����ł��A�e�`�[���̎������t�@���͌�����Ƃ�������ł��B���|�I�ɑ����̎���������1�l�̖싅�I��Ɍ������Ƃ�������ł͂���܂���B
�@�������A�����ΗY�����I�肾��������ɂ����ɂ��I��͂��������킯�ł��B����Ȓ��ŁA�����ΗY�������ʂ̃X�^�[�ɂȂ����̂́A�L�^�ȏ�ɔނ��t�@���Ɋy�����A���邳��^���Ă��ꂽ����ł��B�v���I��Ƃ̓t�@���̑O�ł͖��邭�C������t�o�����Ƃ��A�ނ͎���ɉۂ��Ă��܂����B����������͑f���炵�����̂Ǝ~�߂��킯�ł��B�����̍��ʎ��ŁA���厡���������ΗY���z�ɚg���܂������A�����܂߂ē����悤�Ɏv���Ă����t�@���͑��������Ǝv���܂��B
���͎��́A���̒����ΗY���̖��邳��^�����Ă������Ƃ��v���o���܂����B���ꂪ��ڂ̂�菑�������������Ƃł��B1993�N�ɓ�x�ڂ̋��l�R�ēɒ����������A���Ă���A�ނ̎w���҂Ƃ��Ă̖��͂��A��͂薾�邳�ɂ���ȂƉ��߂ċC�Â����̂ł��B�����A�쑺����ēȂǂ��u�R���s���[�^�싅�v�ƌ����āA����Ȃ�Ɍ��ʂ��o���Ă��܂������A���͖쑺�ē̂悤�ɁA�싅�̒m���͖L�x�ɂ���Ƃ��Ă��Â��ԂԂ����Ȃ���w��������l�̉��ł͓��������Ȃ��ȁA�u�J���s���[�^�v�ƌ����A�����Ŏw��������A�����킯�̂킩��Ȃ���킾�Ɣᔻ����邱�Ƃ������������ēł������A�ǂ��������Ȃ�A�����������邢�ē̉��������ȂƎv�����̂ł��B�����āA�ӂƋ��t�Ƃ����d�����w���҂Ƃ����Ӗ��ł͓����Ȃ̂�����A���邢��C��O�ʂɏo���ׂ����Ƌ����v���悤�ɂȂ����̂ł��B����܂ŁA���[�_�[�̏����Ƃ��āu�C�z��v�Ɓu�������v���K�v�ƌ����Ă����̂ł����A����Ɂu���邳�v������ׂ����Ǝv���A���̌�́A����3�̗v�f�����[�_�[�ɕK�v�Ȏ������Ǝv���A�����Ȃ�ɂ�������H���Ă�������ł��B
�@�I��E�����ΗY�̂P�t�@�����������́A�ēE�����ΗY���w���҂̗��z�̎p�Ƃ��ĉe�����Ă������Ƃ��v���o�����̂ŁA�����ɂ�����Ə����Ă������Ǝv��������ł��B��������9����������ƂŁA��w���t�Ƃ����w���҂̗���𗣂�܂����A���̌�������q�����Ƃ̊W�͑����ł��傤����A�����ΗY������w���邳���A�����ς�炸�������������Ǝv���܂��B��������ċL���������e�������Ƃ����l�Ԃ��������A�����ΗY���͐���������ƌ�����̂�������܂���B�悤�₭��t�@�������������ΗY���ɂ��āA�[���̍s�����͂������܂����B
![]()
��1034���i�Q�O�Q�T�D�U�D�Q�j�����̕������Ȃ�i��ł���A�A�A
�@������w�@�̎��ƂŁA�����l�̊w�����猻�݂̒������퐶���ɂ�����IT������A�����܂����B�ނ�̘b�ł́A�����͂����قڃL���b�V�����X�Љ�ɂȂ��Ă���A�L���b�V���ł̔����������悤�Ƃ���Ƌ��ۂ��邨�X�����邻���ł��B���ہA�ނ玩�g����ԍŋ߃L���b�V�����g���Ĕ����������̂�10�N���炢�O�������ł��B����ɁA�������̂́A�Ƃ̌��������Ă��Ȃ������ł��B��F��w��F�ŏZ��ɓ���̂������ł��B���[�[�[��A�����܂ōs���Ă���̂��Ɨ����ɋ����܂����B�������A���{�ł��Z�p�I�ɂ͉\�Ȃ̂��Ǝv���܂����A�����܂ōs���̂͂ǂ̂��炢�̎��Ԃ�������ł��傤���B�Ǘ������̂Ɋ���Ă��钆���Ɠ��{�̈Ⴂ�����肻���ł����A���{��������͂���ȎЉ�ɂȂ�̂ł��傤�ˁB
�Ԃ�������EV�Ԃ�6�����炢�ɂȂ��Ă��āA�V���������ւ���l�͂قڂ��ׂ�EV�Ԃ������ł��B�u���{�͂Ȃ��EV�Ԃ����y���Ȃ��̂ł����v�ƕs�v�c�����܂����B�Ȃ��b���Ă�����A�����̕������S�ɐ�ɍs���Ă���悤�ŁA���{�͒x��Ă���Ȃ��Ǝv�킴������܂���ł����B�����������Ƃ̔�r�Ƃ����l������悤�ɂȂ����̂́A1970�N�゠���肩�炾�Ǝv���܂����A����܂ŃA�����J���܂߂ē��{���͂邩�ɐi��ł���Ȃ��Ǝv�������Ƃ͂��܂�Ȃ������̂ł����A����͑f���ɂ����v���Ă��܂��܂����B���̂܂܂��킶����{�͐�i�����犊�藎���Ă����̂�������܂���ˁB
![]()
��1033���i�Q�O�Q�T�D�T�D�R�O�j�����̓ǂݕ����Ēʏ̂������̂��ȁH
�@5��26������ːЖ@����������A�ːЂ̎����Ƀt���K�i���L������邱�ƂɂȂ�A���̊m�F�ʒm�̗t�����e���тɓ͂����ƂɂȂ��Ă��܂��B���̃j���[�X�Ŏv�����̂́A�����̓ǂݕ����āA�����ɂ͓o�^����Ă��炸�A�ʏ̂ɉ߂��Ȃ������̂��ȂƂ������Ƃł��B���₢��A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł���B�����Ƃ��ŏ��ނ��o����Ƃ��ɂ��A�t���K�i���ӂ��Ē�o���Ă��܂�����ƌ��������Ȃ�܂���ˁB���������v���Ă��܂����B�ł��A���߂Ď����̌ːГ��{�A�}�C�i���o�[�J�[�h�A�^�]�Ƌ����Ɗm�F���܂������A�ǂ�ɂ��t���K�i�͂ӂ��Ă��܂���ł����B�����ɏ��ނ��o���Ƃ��Ƀt���K�i���K�v�Ȃ̂́A�\���҂��Ăяo���Ƃ���m�F���邽�߂ɕK�v�����珑�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������A�����̏��ނɁA�����g���Ă���ǂݕ��ƈႤ�t���K�i�������Ă��A���Ԃ��ؖ��ɂȂ�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�������A���݂̏o���͂ɂ̓t���K�i���ӂ��Ă��܂���ˁB�i���Ȃ݂ɁA���a5�N���܂�̕�e�̎��́A���������͂��āA�ǂݕ��͌�ōl�����Ƃ����G�s�\�[�h������܂�����A�̂͏o���͂Ƀt���K�i�͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�j�����炱���A���̊����ł���ȓǂݕ���������̂��Ƃ������u�L���L���l�[���v�_�c���N���Ă��Ă����킯�ł���ˁB�ł��A�o���͂ɏ������t���K�i�͌ːЂɂ͋L�ڂ���Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃł���ˁB�ǂ��������ƂȂ̂ł��傤���B�o���͖͂{�Ђ̂���Ƃ���ł͂Ȃ��A���Z�n�̖����ɓ͂��܂���ˁB���̌�A�{�Вn�ɂ��A���͍s���͂��ł���ˁB�ːЂɍڂ��Ȃ��킯�ɂ͍s���Ȃ��̂ł�����B�������A���̍ۂɃt���K�i�͌ːЂɂ͕K�v�Ȃ��Ƃ������Ƃŏ�������Ă����̂ł��傤���B���[�[��A�ǂ��������Ƃł��傤���B�ł��A�Ƃ肠�����A���ꂩ��̓t���K�i���L�ڂ���ƂȂ����Ƃ������Ƃ́A����܂ł͋L�ڂ���Ă��Ȃ��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������ł��B�ːЂɓo�^���ꂽ���������g���Ă���A�o���͂ƈႤ�ǂݕ��Ő����Ă��Ă��Ȃ����͂Ȃ������Ƃ������ƂɂȂ肻���ł��B����̊m�F��Ƃł��A�o���͂Ƃ̏Ƃ炵���킹�Ȃ�čs��Ȃ������ȋC�����܂��̂ŁA���̍ہA�ǂݕ�������ɕς��Ă��܂��Ƃ������Ƃ��ł������ł��B
���̖������łȂ��A��̐����ːЂɃt���K�i���Ȃ������Ƃ������Ƃ͌����ɂ͓ǂݕ��͌��܂��Ă��炸�A�����܂ł��ʏ̂������Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���H�悭���������Ȃ̂������Ȃ̂��A���������ł��Ⴄ�l�����܂���ˁB�u���v�Ƃ������́A�����̐l�́u�N���L�v�ƓǂނƎv���܂����A�u�N���M�Ƒ����ł��v�Ƃ��������q�����܂����B���ŋߗF�l���璴�L���Љ�w�҂ł���u�����ׁv�搶�́A�u�V�I�o���v�ł͂Ȃ��A�{���́u�V�I�����v���������̂��ƕ����A���̂����������܂����B�@���Ȃ́A���������{�l�����݂̂��m���Ă��鎁���̐������ǂݕ����ǂ�����ē��肷��̂ł��傤���B���������S���̏o���͂Ȃ�Ċm�F�ł��Ȃ��ł���ˁH
����HP��ǂ�ł���Ă���F����ł��A������Ƃ������ʂƂ͈Ⴄ�ǂݕ������鎁���̕���������Ǝv���܂����A�@���Ȃ���͂��t���ɐ������t���K�i���ӂ��Ă��������ǂ����A���Ћ����Ă��������B
![]()
��1032���i�Q�O�Q�T�D�T�D�Q�P�j�l���̐ߖڂ̃C�x���g�͑��
�@�������̒ʂ�A����u�Ê�̏j���v���150�l�̋����q�ɏj���Ă��炢�܂����B�{���ɍK���ȋ��t�ł��B�ł��A�������������̂́A���̌Ê���l�^�ɋ����q���W���A�^�e���R�i�i�i�����j�Ɍq����������A���ꂼ��𗬂��y����ł��ꂽ���Ƃł��B���߂Ęb�����Ƃ����l���������������Ǝv���܂����A�u�Ћ˃[�~�v���邢�́u�ЋːV���v�Ƃ������ʂ̃L�[���[�h������܂�����A����10�N���̗F�̂悤�ɘb���ł���悤�ł����B�r�f�I���B���Ă�������̂ŁA���������ƁA�{���ɂ������ł��������ł����낢��ȃR�~���j�P�[�V�������Ȃ���Ă���A�݂�Ȃ����Ί�ł����B
��������Ȃ���v�����̂��A����ς�l���̐ߖڂ̃C�x���g�͑���Ƃ������Ƃł��B����͏j���Ă��炤�{�l�ɂƂ��ĂƂ����ȏ�ɁA���������C�x���g����邱�Ƃɂ���āA�����ɎQ�������l�������f�G�Ȍ𗬂����Ă�Ƃ������Ƃł��B�m���ɁA70�̋��t���j�����߂�150�l���W�܂�Ƃ����̂͂߂����ɂȂ����Ƃł��傤���A�W�܂�l���͂��ꂼ��ł��A�݂�Ȑl���̐ߖڂ��o�����Ă��Ă��܂���ˁB�a������n�܂��āA���{�Q��A���H�����߁A�a�����A���O�A���w�Z���w�A���w�Z���w�A���Z���w�A��w���w�A���l���A��w�̑��Ǝ��ƁA���̂�����܂ł́A���e�哱�A�Ȃ����͖{�l�����R�̂悤�ɐߖڂ̃C�x���g���o�����A�Ƒ���F�l�����ƂƂ��ɍK���ȋC�����𖡂���Ă����͂��ł��B
�@���āA���͂��̌�ł��B�������g�̍ő�̃C�x���g�Ƃ��ẮA����������Ǝv���̂ł����A�ŋ߁\�\���ɃR���i���s�ȍ~�\�\�A�����̃C�x���g�����K�͉��A�Ȃ����͂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂���ˁB�R���i�ȑO�͔N��1�`2��͋����q�̌�����I���ɏ��҂���Ă����̂ł����A�R���i�ȍ~�p�^�b�ƂȂ��Ȃ�܂����B�܂��A��w����̃[�~�̋��t���ĂԂȂ�Ă��Ƃ����Ƃ��ƒ����������̂ŁA�����Ă�Ȃ��Ȃ����̂͂܂������\��Ȃ��̂ł����A��I�����̂����Ȃ��Ƃ����l�������Ă���̂��c�O�����A����ł����̂��ȂƖ₢���������Ǝv���܂��B�ȑO�A�����q�̔�I���ł悭�b���Ă����̂́A������I���̎���͎Ⴂ2�l�����łȂ��A���Ƃ̂����e��������Ƃ����b�ł��B�e�ɂƂ��āA�艖�ɂ����Ĉ�Ă��q�ǂ����悫�����������āA�ːЂ���Ɨ����Ă���錋���́A�q��ẴS�[���ɂ悤�₭���ǂ蒅�����悤�ȋC������r�b�O�C�x���g�ł��B�����e����e�����F�l�����ɂ����Ă��炦��̂́A�{���Ɋ��������Ƃł��B
�@�Ȃ̂ɍŋ߂́A������I���ɂ����������邭�炢�Ȃ�A�V�����s��V�����ɕK�v�Ȃ��̂����낦��̂Ɏg�������Ƃ������āA��I���͂����A�E�F�f�B���O�h���X�𒅂Ďʐ^�����B��ɍs���Ƃ����J�b�v�������Ȃ��Ȃ��悤�ł��B�e�Ƃ��ẮA�{���͉Ƒ��A�e�������ł����������I��������Ăق����ƌ��������Ƃ���ł����A���ǂ��̎���̕��͋C���猾���o�����A�܂��ʐ^�B�e�����ł�������Ɨ��������ӂ������������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���K�͂ł��A�����Ɣ�I��������Ă����e������Ă����Ăق����Ƃ����̂��A���������v�����Ƃł��B��������2�l�ɂƂ��ĂƂ������z�ł͂Ȃ��A�Ƒ���e�����l����ԏ���ǂ����������̂��ȂƂ������z���ق������̂ł��B
�@��������2�l���悯�����ł����Ȃ�Ĕ��z�ōs������A���̌�̐l���ɂ����āA���x�͐e�̂��߂ɂ��낢�����Ă��������Ԃ悤�ȁA���e�̋⍥���A�җ�A�Ê�Ȃ�Ă��̂������Ƃ���Ă����悤�Ƃ������z�͏o�Ă��Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ��ł����B����ɂ́A�e���S���Ȃ����������V�������A�u�C�ɎU�����āv�ƌ����Ă�������A��ɂ����ꂸ�A�@���������A��Q��������A���Ă��ƂɂȂ�܂���ˁB�e�̕����A�����͎q�ǂ��ɕ��S���������������Ȃ��Ƃ������ƂŁA�Ƃ肠�����V����C�x���g�I�Ȃ��Ƃ͉������Ȃ��Ă����ƌ����Ă���l�������̂��Ǝv���܂����A����͖{���Ȃ�ł����ƕ����Ă݂����ł��B�{���́A������Ă��������̂��߂ɁA�q�⑷���W�܂��Ă���ďΊ�������Ă���邱�ƁA�܂�������������A�����Ƃ����l�Ԃ��v���o�����߂ɏW�܂��Ă����l�����āA�����Ō𗬂��Ȃ���邱�Ƃ��A�����̐������Ӗ����m�F�ł���悤�ŁA�������͂��ł��B
�@���K�͂ł������ł�����A�l���ߖڂ̃C�x���g�͂����Ƃ��܂��傤��B�`����`�Ƃ��V���`�Ƃ��ł͂Ȃ��ł���B�����ɏW���l�����ɍK����^���邽�߂ɂ��܂��傤��B���Ȃ݂ɁA���́A���ꂩ�������A�P���A�Ď��A�����ƌ��C�Ȍ���A������l�^�ɂ݂�ȂɏW�܂��Ăق����ȂƎv���Ă��܂��B�Ȃ�Ȃ�A������A���ʂ�̉���A���㉽���N�Ƃ��ł��A�܂������q�������W�܂��āA�u�Ћ˃[�~�v�Ɓu�ЋːV���v���L�[���[�h�Ɍ𗬂��Ă��ꂽ��ō����ȂƎv���Ă��܂��B�傻�ꂽ��]�ł��ˁi�j
![]()
��1031���i�Q�O�Q�T�D�T�D�P�U�j����ȕ��Ɏv���Ă��炦�Ċ������Ȃ�
�@���T��4�[�~�i�Ō�̃[�~����31�����j�ŁA����70�̒a������ɏj���Ă���܂����B�����̋����ɍs������A�u�ʂ̋����ɗ��Ă��������v�Ƃ������b�Z�[![]() �W���u���Ă���A�����ɍs���Ă݂�ƁA��������̕��D�Ŕh��ɏ���t�����s�Ȃ��Ă��āA����ɂ��j�������Ă���܂����B�u�ʂ̋����ɗ��Ă��������v�Ƃ����悤�ȏ����Ɏ��Ԃ̂�����{�i�I�Ȋ��́A�ȑO�͎��X����܂������A�ŋ߂͂����܂ł̖{�i�I�ȏ������������͂Ȃ������̂ŁA�Ȃ������A�������������ł��B�������j���Ă���邱�Ƃ͊������̂ł����A���Ƃ��ẮA���̒a�������j���Ƃ������ƂŁA�[�~���������܂Ƃ܂��Ċ������A�y����ł���邱�Ƃ������������̂ł��B����A�����ɂ����[�~���������A�݂�Ȃ������y�������������̂������������������ł��B
�W���u���Ă���A�����ɍs���Ă݂�ƁA��������̕��D�Ŕh��ɏ���t�����s�Ȃ��Ă��āA����ɂ��j�������Ă���܂����B�u�ʂ̋����ɗ��Ă��������v�Ƃ����悤�ȏ����Ɏ��Ԃ̂�����{�i�I�Ȋ��́A�ȑO�͎��X����܂������A�ŋ߂͂����܂ł̖{�i�I�ȏ������������͂Ȃ������̂ŁA�Ȃ������A�������������ł��B�������j���Ă���邱�Ƃ͊������̂ł����A���Ƃ��ẮA���̒a�������j���Ƃ������ƂŁA�[�~���������܂Ƃ܂��Ċ������A�y����ł���邱�Ƃ������������̂ł��B����A�����ɂ����[�~���������A�݂�Ȃ������y�������������̂������������������ł��B
�@�����Ă����ЂƂ���ƂĂ������������̂��A�[�~�������S������������1�����ŕ\���A���̗��R���������J�[�h�����ꂽ���Ƃł��B������ꗗ�\�ɂ������̂��E�̕\�ł��B�݂�ȏW�܂��Ă�����킯�ł͂Ȃ��A���ꂼ�ꂪ���R�ɍl���������ł����A�P���������Ԃ�Ȃ����������ł��B�����āA���̗��R������ƁA�݂�Ȃ������������Ƃ������Ă���Ă��āA�ǂ�ł��ăW�[���Ƃ��Ă��܂��܂����B�[�~���n�܂���1�N��1�J��������ƁA�v���[�~���琔���Ă��܂�1�N���o���Ă��܂���B�����Ĕނ�Ƃ�48�����Ⴂ�܂��B�����c����ɋ߂��N��ł��B���ꂾ���̔N�������A�܂��t��������1�N������ƂȂ̂ɁA����ȕ��Ɏv���Ă���Ă���Ǝv������A�������Ă��܂��܂����B
�@��w���t�����A���Ǝc��10�J���B����50�߂��̗��ꂽ�ނ�ƁA�Ō�̑�w���t�����������Ȃ������Ă��������Ǝv���܂��B��낵���A31�����I
![]()
��1030���i�Q�O�Q�T�D�T�D�U�j�����̍ۂɕv�w�̖���������荇���邩�H
�@�A�x�����̍���ŁA��������}�����o���Ȃ��ꂻ���ȁu�I��I�v�w�ʐ��v�@�Ăł����A�ǂ����ψ���ł������͎�ꂸ�����͓�����ł��B���_�����ł��A������Ő��������Ȃ��Ă����Ƃ����ӌ����������Ă���悤�ł��B�u�I���v�Ȃ̂�����A���������炢���̂ɂƎv���̂ł����A�����ɂ��Ƒ��̈�̊����咣����ێ�h�͋����悤�ł��B���ƁA���E�ł����������{�̌ːА��x�\�\�̂̌ˎ��f�i������ːЕM���҂̉��ɓ��ꐩ�̂��̂��L������\�\�Ƃ̌��ˍ������l���Ȃ��Ƃ����Ȃ��悤�ł��B�������_�ŁA�q�ǂ��̐����ǂ��炩����Ɍ��߂Ă����Ƃ����Ă��L�͂Ȃ悤�ł����A���Ԃ�͌ːЕM���҂����߂�Ƃ������Ƃ��Ӗ�����̂ł��傤�B�ƂȂ�ƁA���������́u�I��I�v�w�ʐ��v�@�����������Ƃ��Ă��A�����̂悤�ɍȂ����قȂ鐩�ɂȂ�Ƃ����p�^�[���������Ȃ肻���ł��B�ȂA����͂���ł܂��V���Ȗ��������N���������ł��B
�@���̂f�v���ɁA�����̋����q2�l���猋�����܂������A������̖����ɂ��ẮA1�l�i�`�j�͑S�R�b���ĂȂ��i�������I�ɕv�̖����ɂȂ邱�Ƃ𗹉����Ă���H�j�ƌ����A����1�l�i�a�j�͎����̐����D��������j���ɕς��Ă��炦�Ȃ����Ƙb��������ǁA���܂ɂȂ��Ă��܂������ŁA���Ǐ��������ƌ����Ă��܂����B��N3�[�~�ŁA�u�I��I�v�w�ʐ��v�ɂ��ċc�_�������̂��Ƃ́A�u��997���@�I��I�v�w�ʐ��i�Q�O�Q�S�D�P�O�D�Q�R�j�v�ɏ����܂������A�j�q�w�����S���Ȃ̖����ɕς�����ƌ����Ă��̂ł����A����͂܂������������I�ɍl���Ă��Ȃ����猾���邱�ƂŁA���ۂɂ��̎���������A�j���̕�����u�����͂ǂ����悤���H�v�Ȃ�Ęb��ɂ��邱�Ƃ͂قڂ��Ȃ����낤�Ǝv���܂��B���̎��̋c�_�ł��A�u�I��I�v�w�ʐ��v�̓����Ɏ^�����Ă������ׂĂ̏��q�w�����A�������g���ʐ���I�Ԃ��Ɩ₤����A�N1�l��������Ȃ������悤�ɁA�Ⴂ�����������u�������遁�v�̖����ɕς��v�Ǝv���Ă��܂��̂ŁA�u�����͂ǂ�����H�v�Ȃ�ċc�_�����悤�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��ł��傤�B�ƂȂ�ƁA�j�������̓^�e�}�G�Łu�����̖����ɕς���Ă������v�ƌ����Ȃ���A�z���l�ł́u����Ȃ��Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�v�Ɩ��ӎ��Ɏv���Ă���̂ł��傤�B
�@���������A����1�l�f�v�Ɍ��������j���̋����q�i�b�j�̏ꍇ�́A�������ޏ��̐��ɕς��������A���傤�ǗL���l�Ɠ������O�ɂȂ��Ėʔ�������ς��Ă������ȂƖ{�C�Ŏv���������ł����A�������唽�ŁA���ǒj�����̖����ɂȂ��������ł��B�j���{�l���ς��Ă�������Ǝv���Ă��A�j���̐e��������Ƃ������Ƃ����Ȃ肠��̂�������܂���ˁB���������A�ȑO�j���̋����q�i�c�j��1�l�A�Ȃ̖����ɕς����l�����܂����B�ނɂ��̌o�܂�����A�����͒j�O�Z�킾���A�C�O���C�̂���d���Ȃ̂ŁA�C�O���C�ɂ��ė��Ă����Ȃ�A�����͏������̖����ł����Ƃ����b�ɂȂ����ƌ����Ă��܂����B�����̋����q�Ō���������̖����𖼏���Ă���l��1�l�i�d�j�����m��܂���B�ڂ�������͕����Ă��܂��A�ޏ��͊m��2�l�o���������̂ŁA�Ƃ��p���ӎ����������̂�������܂���B�j�������ǂ�Ȕ������������͕����Ă��Ȃ��̂ł킩��܂���B
�@���Ǎ��̎��_�ł́A�������v���|�[�Y�������Ƃ������Ƃ́A�j���̖����ɕς�邱�Ƃ𗹏������Ƃ����Ӗ��ɂȂ��Ă���̂ł��傤�ˁB�v���|�[�Y�̍ۂɁu�����͂ǂ�����́H�v�Ȃ�āA���ʂ͕����Ȃ��ł��傤�B���̓`�ōs������A�u�I��I�v�w�ʐ��v�@����������Ă��A�قƂ�ǂ̃J�b�v���́A����܂Œʂ菗�����j���̖����ɕς���Ƃ������ƂɂȂ肻���ł��B�v���|�[�Y����ɂ������āA�u���͖�����ς��܂���B�q�ǂ��̖��������Ɠ����ɂ������B�����F�߂Ă����Ȃ�A�v���|�[�Y���܂��v�Ȃ�Č�������̂ł��傤���B���ł��A�@����́A�ǂ���̐��ɂ��Ă��悢�킯�ŁA�j�������ł��B�������A�����̊��K�́A�ǂ���̖������邩�Ƃ����b�������������ɁA�������������j���̖����ɕς��邱�ƂɂȂ��Ă���킯�ł�����A�u�I��I�v�w�ʐ��v�@���������Ă��A�قƂ�ǂ̃J�b�v���͘b�������������ɒj���̖����ɂȂ�̂ł��傤�ˁB�������A�ɏ����̃J�b�v���́A������Ƙb�������āA�����ɂ��邩�ʐ��ɂ��邩�A�q�ǂ��̖������ǂ���ɂ��邩���߂�̂ł��傤�B�������A����̂a����̂悤�ɁA�������̖����łǂ��H�ƒ�Ă�����A���܂ɂȂ肻���ɂȂ����Ƃ����悤�ȃp�^�[�����A�u�I��I�v�w�ʐ��v�ł��N�������ł��B���ɁA�������g�̖����͂��̂܂܂ł��A�q�ǂ��̖������ȑ��̖����ɂ������ƌ���ꂽ�ꍇ�́A���̍����̍ۂɏ������̖����ɂ������Ƃ�����ĂƓ������x�̔�d�������A������Ȃ��j���₻�̗��e�͑������ł��B�q�ǂ��̐��͓��ꂵ�Ȃ��Ă������A�ːЂɂ͑S�������L������Ƃ��������ɕς��Ȃ��ƁA���܂��s���Ȃ������ł��B���Ă��āA�u�I��I�v�w�ʐ��v�@�Ă͂ǂ��Ȃ�ł��傤���H
![]()
��1029���i�Q�O�Q�T�D�S�D�Q�V�j��㖜���T�K�L
�@����A��㖜���ɏ��߂čs���Ă��܂����B���̒T�K�L���܂Ƃ߂��̂ł����A���̂܂܍ڂ����璷������̂ŁA�Љ�w�I���_����C�ɂȂ������Ƃ��������Ă����܂��B
�@�܂����A�ǂ�ȃ`�P�b�g���w���������Ƃ����b����n�߂܂��B���Ƃ��Ƃ����܂ŋ����S���������킯�łȂ��A�܂��������1�炢�s���������ȂƎv���Ă����̂ł����A�J�����߂Â��A�����I���J����f�B�A���J���Ȃǂŏ�ǂ�ǂ�e���r�ŏЉ���悤�ɂȂ�ƁA�Ȃ���ς�ʔ����������A�Ǝv���n�߁A���ɊJ�����O���Ɂu�ʊ��`�P�b�g�v���w�����Ă��܂��܂����i�j�ł��A���ׂăI�����C���ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA���܂��ł��邩�ǂ����s���ł������A�Ȃ�Ƃ��w�����A�Ƃ肠�����s������\�A���ɂ�1�T�ԑO�܂łɗ\���I��҂Ƃ����Ƃ���ŁA5�̃p�r���I���Ɏ��Ԃ��w�肵�Đ\�����݂܂����B5���\��������3���炢�͍s����̂��ȂƎv������A���̂����̂ЂƂ�������A���̂͑S�������ɂȂ邻���ł��B���́u���̂��̖����v�Ƃ������{�b�g��A���h���C�h���o�Ă���p�r���I����������܂����B�i���Ȃ݂ɁA���̃p�r���I���͌�����������A������ł����B�j��́A3���O����n�܂�p�r���I���ւ̗D��g�Ƃ����̂ɂЂƂ\�����߂�Ƃ������Ƃ������̂ŁA�K���ɋĂ����u�I�[�X�g�����A�فv��\�����݂܂����B�i������́A����܂�ł����B�j
�@���Ă��悢�擖���ł��B������11�F00�`11�F15�Ƃ�������\�����̂ŁA10���������F�w�ɒ����܂����B���D���Ƃ�����ł��邩�ȂƎv���܂������A�����ɏo���Ēn��ɏオ��ƁA�U���������Ƃ��Ă��ē���Q�[�g�O�܂Ŏ~�܂炸�ɍs���܂����B10��40�����炢����Q�[�g�O�̗�ɕ��сA��10���œ���ł��܂����B���̊ԁA�傫�ȏa�͋N���Ă��炸�A��ו����������Ă��銄�ɂ͏����������ƌ�����Ǝv���܂��B�����͂����������̐l�����܂������A���b�V���Ƃ����قǂł͂Ȃ��A�l�ɂԂ���Ȃ����x�ɕ����邿�傤�ǂ悢���ݕ��ł����B�܂��́A��ԋ������������剮�������O�ɃG�X�J���[�^�œo��A50���قǂ����Ĉ�����܂����B�����ɓo��ƁA�ً�Ԃɗ����ȂƂ����C���ɂȂ�A�e���V�������オ��܂����B���ɁA�쑤�̊C�ɓ˂��o�������͂Ȃ��Ȃ��ǂ����͋C�ł����B
�@���ɍ~��A���x�͒n�㕔�����Ԃ�Ԃ�����܂����B�\��Ȃ��œ����p�r���I������������A�s��͂���قǒ����Ȃ��Ă��炸�A30�����炢���ׂΓ����Ƃ����Ƃ��낪���������ł��B�Ƃ肠�����A����͉��������낢�댩�ĉ�肽�������̂ŁA�����ɉ���������܂����B���̓��̓���҂̓����Ƃ��ẮA�������̎������k�����Ȃ藈�Ă������ƁA�l�ŗ��Ă���l�͕����Ƃ������Ƃ������Ă��A�N�z�҂����������ł��B�����̔N�z�҂͗F�B��v�Ǝv�����l�ƈꏏ�ɂ���l���قƂ�ǂł������A�j���N�z�҂�1�l�Ō��ĉ���Ă���l�����Ȃ肢�܂����B55�N�O�̓��{����������̂��Ƃ����̌��Ƃ��Ēm���Ă���낤�ȂƎv����l�����ł����B
�@�p�r���I��������ē�����l�ɂ��N�z�҂����ɑ��������ł��B���ƁA�����ڂ͓��{�l���ȂƎv����A�W�A�n�O���l���ē��W�ɂ��Ȃ肢�܂����B1970�N�̓��{����������̎��́A�ē����͎Ⴂ�����������肾�����̂Ƃ͑ΏƓI�ł��B������70�NEXPO�̎��́A�قƂ�ǃ~�j�X�J�[�g�ł������A����̓X�J�[�g�𗚂��Ă���l�͈ē��W�ɂ͂قڂ��Ȃ������C�����܂��B
�@�J�����ɂ��낢���肪�w�E����Ă����g�C����x���`�̏��Ȃ��ł����A�V����悩���������̂��̓��͂܂��������Ȃ��A�g�C�����x���`���g���������ɂ͎g�����Ԃł����B�����͂Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ��̂��ȂƎv�����̂́A�����ł��B�����̊Ԃ̓������炷���ƍs����̂ɁA�����������͂قڂ��ׂĊW�҈ȊO�ʍs�֎~�ƂȂ��Ă��āA�W�̐l����̑O�ɂ��ē���Ȃ���Ԃł����B����������́u�Â����̐X�v����k���̃]�[���ɂ������u�I�[�X�g�����A�فv�ɍs�����Ǝv������A���������̑剮�������O�̂Ƃ���܂ōs���A��������k���̕��ɕ����čs���Ȃ��Ƃ��ǂ�����A���Ȃ�̉������������܂����B�n�}�����Ă��A�ǂ����]�[�����͔��������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă���悤�ł��B���ׂĂ̌����̊Ԃ̓���ʂ��悤�ɂ���Ƃ͌����܂��A���ɍL���ʂ�₷�����ȓ����炢�ʂ��Ă��ꂽ�炢���̂ɂȂƎv���܂����B���ƁA�����̐H���̍����ɂ͋����܂������A�܂��ł�����͎d���Ȃ��̂�������܂���ˁB
�@1970�N�̓��{����������Ƃ̈Ⴂ�́A�O���l�̑����ł��B���A���{�Ɋό��ɗ��Ă���O���l�������̂͂悭�m���Ă������Ƃł����A��㖜���ɂ�����Ȃɗ��Ă���Ƌ����܂����B�������A1970�N�̎��͊O���l���������āA�����̊ό��q�ɂ��T�C������������肵�Ă������{�l�ł������A������O�ł����A���͂���Ȑl�͒N�����܂���ł����B���ƁA���������B�f�W�J���Ŏʐ^���B���Ă����̂́A���Ԃ����ł����i�j�݂�ȃX�}�z�ł��B1970�N�̖����̎��ɁA���C�����X�E�e���t�H���Ƃ��Ė����̒ʘb�@��Ƃ��ďЉ��Ă������̂��A55�N��̖����ł͎����Ă��Ȃ��ƁA�����ɂ͗����Ȃ��悤�ȕK���i�ɂȂ��Ă��܂��B�ʘb�@��Ƃ��Ă��A�J�����A�r�f�I�A�`�P�b�g�A�K�C�h�u�b�N�Ȃǖ��\�̖������ʂ����Ă��܂��B�����̓L���b�V�����X�ł����A���̂������55�N�O�̗\�z���i��ł��銴�������܂��B�p�r���I�����̎B�e�͂قڂ��ׂ�OK�Ƃ����̂��A����܂ł̔������~���[�W�A���Ƃ͈Ⴄ�ȂƊ���������Ƃ���ŁA�悩�����ł��B
�@�����n�߂���A�G���h���X�Ȃ��炢�������Ƃ�����܂����A����͂����܂łɂ��Ă����܂��B�Ȃɂ��ʊ��p�X�������Ă��܂��̂ŁA�܂����̂����s���Ă��܂��i�j����A�\��œ��ꂽ�u���̂��̖����v�ق̓W���͂Ȃ��Ȃ��悩�����̂ŁA���̐l�C�p�r���I�������邽�߂ɉ��x�������^��ł݂܂��B���������ʔ�Əh������g���Ăł��s�����l�����邩�ƌ���ꂽ��킩��܂��A���Ȃ��Ƃ����A��ōs����Ȃ��x�͍s���Ă݂鉿�l�͏\������Ǝv���܂��B�w�Z�P�ʂŗ��Ă��������E���k�������݂�Ȋy�������������̂ŁA���{����̖������҂�f�����w�Z�̎q�ǂ������͂�����Ɖ��z���ȂƎv���܂��B���ł������ɂ��������ېV�̉�̐�����Ɩь������鋳�t�����邱�ƂŁA�`�����X�������Ă���q�ǂ�����������Ƃ�����A�Ȃ�Ƃ����Ă��Ȃ��̂��ȂƎv���܂��B���Ԍ���Ń��N���N�ł����ł�����A���A��ōs����n��̎q�ǂ������ɂ͑̌������Ă�����ׂ����Ǝv���܂����B
![]()
��1028���i�Q�O�Q�T�D�S�D�P�R�j��
�@���X�A�w���Ɂu�ڂ��ˁv�ƌ����Ă��܂��̂ł����A�����啪�O����u�ڂ��ĉ��ł����H�v�ƕ����Ԃ���A�u�����A�C�P�����̂��Ƃ���v�ƌ��������̂ł����A���������Ȃ���Ȃ�ƂȂ��Ⴄ���ǂȂ��Ƃ����v���Ă��܂��B�Â�����͒m���Ă��邱�Ƃł����A�]�ˎ���̎ŋ������Ŏ�����ꖇ�ڂ̊Ŕɖ���������A�ڂɁA����ł͂Ȃ����F�j�\�\������Ⴂ�l�͂킩��Ȃ��ł��ˁi�j�u���e��j�v���ĂƂ����ȁ\�\�̖��������ꂽ���Ƃ���A�痧���̗ǂ��j�����u�ځv�Ƃ����悤�ɂȂ����킯�ł��B
�@�u�ځv�Ƃ������t�́A���a�̎���݂͂�ȕ��ʂɎg���Ă����C������̂ł����A���̊Ԃɂ��g���Ȃ��Ȃ�A���₻�̌��t��m��Ȃ��Ⴂ�l���炯�ɂȂ��Ă��܂�����A���鐢��ȍ~�ł́u����v�ɂȂ����ƌ����Ă������̂ł��傤�B�����A��҂͂��̌��t��m��Ȃ��ƋC�Â��Ȃ�����A��������������̌��t���g���Ă��܂��̂́A���ɂ��傤�ǂ悢�\�����Ȃ�����ł��B
�@�ގ��̌��t�Ƃ��ẮA�u�n���T���v�u�����j�v�����āu�C�P�����v�Ȃ̂ł��傤���A���ꂼ��g���ɂ��������ŁA����3�̌��t�́A�����ł͂��܂�g���Ă��܂���B�u�n���T���v���Â��ł���ˁB���ǂ��̎Ⴂ�l�͂�����g��Ȃ��ł��傤�ˁB�m����1960�N��܂ł̗p�ꂾ�ȂƎ����ł��v���܂��B�u�����j�v�͊痧�������ł͂Ȃ��A���͋C�i���i�H�j���܂ނ悤�ȋC�����܂��B�u�C�P�����v�͂ȂL������C���[�W�ŁA���ɂ̓s���Ƃ��Ȃ��ł��B�Ƃ������ƂŁA�痧���������Ă���j�����ȂƎv���ƁA���u�ڂ��ˁv�ƌ����Ă��܂��킯�ł��B
�@�ŋ߂̎Ⴂ�j���^�����g�ɂ́A�Y��Ȋ�������l����������Ǝv���܂����A�ނ�͉��ƌĂԂ̂������̂ł��傤���B�����v���u�ځv�ł͂Ȃ��ł��ˁB�u�����N�v���Ȃ��B���N�̔N������悤�Ȑl������̂ŁA���̂�����̐l�����Ȃ�u���N�v�ł��傤���B�u�ځv�Ƃ����C�ɂȂ�Ȃ��̂͂Ȃ����Ȃ��B�j�����ۂ��������̂��Ȃ��B
![]()
��1027���i�Q�O�Q�T�D�S�D�S�j�u�g�����v�E�V���b�N�v�͂��܂ő������H
�@�������݂Ȃ̂��S�R�悭�킩��܂��A�Ƃ肠�����g�����v���u���݊Łv�Ƃ������ڂŁA�����̍��ɑ��Ăׂ�ڂ��ȍ��ł������邱�Ƃɂ������߂ɁA�������ǂ��ł��啝�ɉ������Ă��܂��B�g�����v�́A�A�����J�̊������Ƃ肠����������̂͐D�荞�ݍς݂ŁA�����ɃA�����J�̌o�ς͂悭�Ȃ�A���������������Ǝ��M���X�ɔ������Ă��܂����A�ǂ��l���Ă������Ȃ�Ƃ͎v���܂���B�����̍����ŃA�����J���i�̗A���ɑ��Ċł���������Ɛ錾���Ă��܂��B��������������Ȃ��̂͂킩��܂����A����ȕ[�u���s�Ȃ�����A���Ǎ���̂͊e���̍����ł��B���{�́A�A�����J�Ƃ����u�W���C�A���v�ɂ͐�t�炦�Ȃ��u�X�l�v�v�Ȃ̂ŁA�[�u�ȂǂƂ͈ꌾ�����킸�ɓ��{�����ł�Ⴍ���Ăق����ƈ���ȑԓx������Ă��܂����A�Ƃ肠�������������Ă͂��炦�Ȃ������ł��B���ƂƂ��Ă݂͂��߂ȑԓx�ł����A���ʂɃA�����J����̗A���i�������Ȃ�Ȃ��̂͌��ʂƂ��Ă͈����Ȃ��ł��傤�B���{�̏ꍇ�A�A�����J����͏�����g�E�����R�V�Ȃǔ_�Y���̗A���������ł�����A����ɍ����ł���������A���{�̗l�X�ȎY�Ƃɑ�Ō���^���邱�ƂɂȂ�܂��B
�@����ɂ��Ă��A���́u�g�����v�E�V���b�N�v�Ƃ������鎖�Ԃ������N���������Ő���͂��܂ő����ł��傤���B���́A���������͑����Ȃ����낤�ƌ��Ă��܂��B500�N���炢�O����l�X���]�ޕ����Ƃ��Đi��ł����f�Ղ̎��R���ւ̃g�����h���A������1�l�̕ς�����j�̓��̒��̌v�Z�����ŕς�����͂�������܂���B����ȍ��Ő���̓A�����J�������܂ߒN���K���ɂ��܂���B�����A�����J�������C�Â��āA�g�����v�ᔻ���n�߂Ăق������̂ł��B�������A�����Ȃ�O�ɁA�����̌��������Ƃ�ς��邱�Ƃɒ�R�̂Ȃ����ߑ��ȃg�����v�́A���N�Ȃ�1�N�Ȃ�\�\��������Ƒ�����������܂���\�\�o���Ă��A�����J�o�ς��悭�Ȃ�Ȃ����Ƃ�F��������A�u�����\���Ȑ��ʂ͓���ꂽ�B�A�����J�͈̑�ȍ��ɖ߂ꂽ�v�Ƃ���噓�������āA���̍��Ő������߂�Ƃ������f���������ȋC�����܂��B�����̐l�X���]�ޕ����ƈقȂ�����ɎЉ�������Ƃ͍���ł��B�g�����v�ɂ������C�Â��Ăق������̂ł��B
![]()
��1026���i�Q�O�Q�T�D�S�D�Q�j�H���N�̉̎����āA�A�A
�@����́u���ʐM�v�ɏ������悤�Ɂu365���̎���s�@�v������������ł��܂��̂ł����A�u365���v�����łȂ��A�u����s�@�v���悭�킩��Ȃ��C�����Ă��܂����B�u�l���͎���s�@�v�Ȃ�ł����˂��H���Ȃ��Ƃ��A���̐l���͎���s�@����Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂��B�v���y���͂��Ă���C�����܂��B����s�@���āA�u�肢�∤���悹�āv���ł��܂����˂��H�u���̒���͂̌���v�i��łȂ��ł��傤�B�����������痎���܂���ˁB�u�܂����m��Ȃ��Ă����̂܂ɂ������v�Ȃ�Ă��Ƃ��Ȃ��ł���ˁB�����Ɛ܂�����w�Ȃ��ƁA����s�@�͔���܂���B�Y��ȃ����f�B�ɂ��܂����t������Ă��āA�Ȃ�ƂȂ��S�n�悭�����Ă��܂������A�̎�����������ǂ�ł݂�ƁA�u�ւ��H�v���ĂƂ������ł��B�Ȃ[���Ӗ����Ȃ��Y��Ȍ��t����ׂ��A�܂��ChatGPT�ɍ�点���悤�ȉ̎����ȂƎv���Ă��܂��܂����B
�@���������A����Ђ�̍Ō�̃q�b�g�ȁu��̗���̂悤�Ɂv���H���N�쎌�������ȂƎv���o���A������ƒ��ׂĂ݂���A��������u365���̎���s�@�v�Ɠ��l���Y��Ȍ��t����ׂ��A���������ȉ̎����Ƃ����C�����Ă��܂����B���Ȃ��Ƃ�����Ђ�̐l���Ƃ͂܂������قȂ邷�������}�Ȑl�̐l����������ł��܂��B���������u��̗���v�����̉̎��̂悤�ɂ������₩�ɗ���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�J���~��Ώ�����֖҂Ȑ�ɕς�����肷��킯�ł����A�Ȃ[���Ȃ��ł��B�u�����邱�Ƃ͗����邱�Ɓv�͂܂������ł����A�u�I���̂Ȃ����̓��v����Ȃ��A�����K���I��肪���܂��B���₩�ȕ����₷�������f�B�[���A����Ђ�Ƃ������Q�ɉ̂̏�肢�̎肪�S�����߂ĉ̂��̂ŁA�Ȃf���炵�����b�Z�[�W������Ă���C�����܂������A�悭�悭�̎������ǂނƕ��ł��B
�@����̋�V���l�ƌ����钆���݂䂫��A�����̑f���ȋC�������̎��ɂł���|���܂肠�Ƃ͑S�R�Ⴄ�l�ł��B�t�H�[�N�\���O���̂��Ă����l�������`���������t�������Ƒ厖���Ă��܂����B�H���N�̓����f�B�[�ɂ��܂����t���悹���A���c��Ȑ��̋ȂɎ����玟�ɉ̎������邱�Ƃ��ł���v���̍쎌�ƂȂ̂��Ƃ͎v���܂����A���l�ł͂Ȃ��ł��ˁB�܂��A���������݂����Ȋ��z�ł����A�ӂƎv���Ă��܂����̂ŏ����Ă����܂��B
![]()
��1025���i�Q�O�Q�T�D�S�D�P�j�V�N�x�X�^�[�g
�@4��1���ł��ˁB2025�N�x���X�^�[�g�ł��B���������œ��Ў����J����A���Ƃ�������̊w���������V�Љ�l�̑�1���ݏo�������Ƃł��傤�B������Ɗ��������ł����A���͂قږ��J�ŁA�Ȃ��Ȃ��悢�X�^�[�g�̓��ɂȂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����A���͒�����w���������̍Ō��1�N�̃X�^�[�g�ł��B�V�Љ�l�ɂȂ������Ƃ͂܂��Ⴄ���S�[��������܂��B��w�����ɂȂ��Ă���43��ڂ�4��1���ł��B��������ĕ�������Ƃ����������ł����A�����Ƃ����Ԃł����B���̊Ԃɂ���ȂɎ��Ԃ��o�����̂��낤�Ƃ����C���ł��B���N�x�́A�������Ă����ꂪ�Ō�ȂȂƎv���Ȃ���߂��������ł��B�y���݂Ȃ���Ō��1�N���߂��������Ǝv���܂��B
�@���Ȃ݂ɁA����365�����ȂƎv���ƁA�u365���̎���s�@�v�Ƃ����̂������ɕ�����ł���̂ł����A���̉́A�ǂ�����365���Ȃ�ł����˂��B365����ɂ͒ė�����̂��ȂƂӂƎv���ĉ̎��ׂĂ݂܂������A�ʂ�365���̖����Ə����Ă���킯�ł͂Ȃ��ł��ˁB�l�����y���������悤�Ƃ������e�ł����A�Ȃ��365���Ɖ̎��ɓ����Ă��邩�͂悭�킩��Ȃ��ł��ˁB�܂��A���͏���ɂ���365����Ԏ���s�@�Ǝv���Č������ނ��Ƃɂ��܂��B��������364���ł��B���ʂȂ��Ƃ͂Ȃ�1��1�����߂���1�N���߂��Ă����̂ł��傤�ˁB���C�ɗ�N�ƕς��ʑ�w��������������Ă��������Ǝv���܂��B
![]()
��1024���i�Q�O�Q�T�D�R�D�R�O�j��̓h���}�u�ׂ�ڂ��v
�@��N�́u����N�ցv���ۊ����̎���̋{���̕��G�Ȑ����������������`���Ă��Ėʔ��������ł����A���N�̑�̓h���}�u�ׂ�ڂ��v�����Ȃ肢���ł��B�Ӊ��d�O�Y����l���ɂ���ƕ��������́A����Ă���̒Ӊ��d�O�Y�����C���[�W���Ȃ������̂ŁA�L����Ƃ����Ƃ̗��݂��o�Ă���܂łǂ��Ȃ��̂��낤�Ǝv���Ă��܂������A�g�����܂�ŏ������n�ʂ��グ�Ă����Ӊ��d�O�Y�̐l�������ɋ����[���ł��B�����āA�l�b�g��ł��b��ɂȂ��Ă��܂����A���ŕ����̉Ԋ@�Ԃ�A�����Ē��R���Z�ɐg��������Ă�������͂̂��鉉�Z�ŁA����҂̐S�𑨂��܂��B���ɍ���͂悩�����ł��B�Ă����萔��O�̋g�����o�Ă�����ʂŁA���ŕ��Ԃ͂����o�Ă��Ȃ��̂��Ǝv������A�����̎s�����l�����钹�R���Z�Ƃ̂����͑f���炵�������ł��B���Ȃ݂ɁA���R���Z������Ƃ����Ԋ@�𑽊z�̐g�������Őg���������͎̂����ŁA�܂����̋��݂��Ƃ{�ɂ���Ď����܂���Ƃ����̂������̂悤�ł��B�r�{�Ƃ̐X�����q���͂悭�����Č����ȕ��������Ă���Ȃ��Ɗ��S���Ă��܂��B��������Ɋy���݂ł��B
�@�����A���̂悤�ȗ��j�D���̔N�z�҂ɂƂ��Ă͍ō��̃h���}�ł����A�����Ȏq�ǂ��������ꏏ�Ɍ�������j�h���}���ƌ����ƁA�����͌����Ȃ��ł��傤�ˁB�g�����Ăǂ������Ƃ��납�̐�����������A�h���}���́A��l�����̑�_�ȉf�������Ȃ�����܂���̂ŁB���́A���w�Z1�N�̎��̈�ɒ��J����l���ɂ�����1��u�Ԃ̐��U�v���猩�Ă��܂����A��2��́u�ԕ�Q�m�v�A��3��́u���}�L�v�A��4��́u���`�o�v�ƁA���w���ł��~�߂���uTHE�@���j�h���}�v�ł����B����60��ȏ����Ă��āA���x����������̑�͂����Ă��Ă��鎄�̂悤�ȔN�z�҂��������Ă��邱�Ƃ��l����ƁANHK�����܂���グ���Ȃ������ꏊ�����グ��������Ȃ��̂��Ǝv���܂����A���Ă̂悤�ɉƑ��Ō������̓h���}�Ƃ������ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���悤�Ɏv���܂��B�܂��ł��A���ǂ��e���r������͔̂N�z�Ғ��S�ł�����A�N�z�҂��y���߂���j�h���}�ł����̂ł��傤�B����Ɏq�ǂ�����N���܂őS����Ɏ�悤�ȃh���}���߂�������A�낭�Ȃ��̂͂ł��������Ȃ��ł�����B�u�ׂ�ڂ��v�ɂ́A���̂܂q�ǂ��ɂ͐������ɂ������݂̂���h���}�������Â��Ăق������̂ł��B
![]()
��1023���i�Q�O�Q�T�D�R�D�Q�V�j�z�[���ɖ߂����C��
�@����͍��N�x�Ō�̋�����̓��ł������A5�N�Ԃ�ɑ�3�w�Ɂi�Љ�w�����j�̉�c���ōs���܂����B60���̎Љ����������ƁB���傤�ǖ��ȂƂ��������̉�c���ł��B�V�^�R���i�̗��s�ȍ~�A������̓I�����C������{�ƂȂ�A���܂ɑΖʂł�邱�Ƃ������Ă��A�傫�ȍu�`�����g���ĉ�c�����Ă����̂ł����A����͗��n�̑�K�͊w��痢�R�L�����p�X�̂��������̊w�ɂ𗘗p���A��3�w�ɂ������̋������g�p���Ă����̂ŁA��ނ��������̉�c�����g�����Ƃɂ����悤�ł����A�v���Ԃ�ɂ��̉�c���ł̋�����́A�z�[���ɖ߂����悤�ȋC�����ɂ����Ă���܂����B
�@�Љ�w���̗ǂ��́A���̉�c���ł̕����I�����̋߂����S���I�����̋߂����o�����Ƃɂ���Đ��܂�Ă����ȂƂ������Ƃɉ��߂ċC�Â��܂����B�I�����C���ł͂킩��Ȃ�����U�̐搶���̗l�q�Ȃǂ��A���̉�c���ɂ���ƁA�悭�킩��܂��B����5�N�ŃI�����C����c����ԉ����A�����g���u���������͋�������B�I�����C�������痬���ĕ����������Ȃ��v�ƁA�S�R�C�����̓���Ȃ����Ԃ��߂����Ă��܂����B�y�����ǁA����Ȃɐl�ԊW���[�܂�Ȃ���Ԃ������Ȃ�A������������40�Α�Ƃ���������A���̑�w�Ɉڂ肽���Ȃ邾�낤�Ȃ��Ƃ��v���Ă��܂����B���ꂪ����A������̃z�[���ƌ������c���ɖ߂��āA���݂��݁u���������B���̊�������B���ꂪ������Ȃ��v�ƂȂ��������Ȃ�܂����B�ӂɂ́A�ސE�����𑗂�V�C�������}���銽���}��J����܂������A�������������̗]�C����Ί炪�����A���ɂ悢���͋C�Ői�݂܂����B�w�������A��͂肱�̉�c���Ő��܂�镵�͋C�̗ǂ��ɋC�Â��ꂽ�悤�ŁA����̐V�N�x1��ڂ̋�������A���̕����ł��܂��ƌ����Ă���܂����B���ɂƂ��čŌ�̔N�x�̃X�^�[�g�ł��B�����āA�قڂ��傤��1�N��ɁA�����ސE���鋳���Ƃ��čŌ�̋�����ɏo�Ȃ��邱�ƂɂȂ�܂����A���Ђ��̎������̉�c���ł���Ăق����ȂƎv���Ă��܂��B
![]()
��1022���i�Q�O�Q�T�D�R�D�V�j�䓰���Ă������痈�Ă����̂���
�@�v���Ԃ�ɁA���܂薾�m�ɍs��������߂Ȃ��̂�т肵�������������Ă��܂����B�{���̉w�ō~��āA�\���Ă��������Ӓn�}�����Ȃ���A�ǂ��ɍs�������Ȃƒ��߂Ă�����A�k�䓰�Ɠ�䓰�Ƃ�����y�^�@�̗��h�����Ȍ��������邱�ƂɋC�Â��A�����ɍs���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B�܂��A��䓰�ɍs�����̂ł����A�R�傪�r���ɂȂ��Ă��ď�̓z�e���ɂȂ��Ă��邵�A���������ɂ̓A���t�@�x�b�g�ŁuMINAMI MIDO�v�Ə����ꂽ�A�����̎ʐ^�X�|�b�g�ɂȂ肻���Ȃ��̂��ݒu����Ă��āu�ȂȂ��v�Ƃ��������ł������A�����ŃL���L���̖{���̓I�[�v���ŁA���s�̎��@�̂悤�ɔq�ϗ�����낤�Ƃ��Ă��Ȃ��Ƃ���͍D���������܂����B�����̋x�e���̂悤�ȂƂ���ŁA�r�f�I�ɂ���䓰�̐������ځ[���ƕ����Ă����̂ł����A�u��䓰�Ɩk�䓰�����Ԓʂ�Ȃ̂ŁA�䓰�ƌĂ��悤�ɂȂ����v�Ƃ����������āA�v�킸�u���������B�����������̂����I�v�Ǝv�킸�����o�Ă��܂��܂����B
�@���ɕ�炵��42�N�B�u�䓰�v�Ƃ������t�͉��������ł��傤���B����A���Ԃz���ɂ�1971�N�Ƀq�b�g�������u�J�̌䓰�v���Ĉȗ��A���̗L���Ȓʂ�Ƃ��ď\�㔼���炻�̖��O�͒m���Ă����̂ŁA�������琔������54�N�A������O�̂悤�ɕ����A������O�̂悤�Ɏg���Ă����u�䓰�v�̌��t�̗R�����܂������l�������Ƃ��Ȃ������ł��B�����āA���̖��O�̗R���ƂȂ��Ă��闧�h��2�̌䓰�����ł��䓰�Ɍ��R�Ƃ��Ă���Ƃ������Ƃ��m��Ȃ������̂́A��Ȃ���Ȃp���������ȂƂ����C�ɂ���Ȃ�܂����B���Ő��܂������l�́A�݂�Ȓm���Ă���̂ł��傤���B
�@����ʂ�̖��́A�̂����ɂ����������̂��������Ƃ������ƂŁA���͂������̖���\���悤�Ȃ��̂��Ȃ��Ƃ����Ƃ���������̂ł����A�䓰�̏ꍇ�́A���ł����X�ƌ䓰�ȂƖ��Ȋ��S�̎d�������Ă��܂��܂����B�r�f�I�̐����ł́A�L�b�G�g�ɐΎR�{�莛�̏ꏊ�i����̂���n��j���������^�@�ɁA�G�g�����̏ꏊ��^���Ĉȗ��A�����ɓ�䓰������Ƃ����b�ł������A�E�B�L�y�f�B�A�Œ��ׂ�ƁA����������₱�������ł��B�ڍׂ́A�E�B�L�y�f�B�A�����Ă������������ł����A�ЂƂ厖�Ȃ��Ƃ͓�䓰�Ɩk�䓰�͐ݗ���������S�R�Ⴄ���Ƃł��B��䓰�̕��́A�m���ɏG�g��ƍN�Ƃ̊W�������đ���ꂽ�悤�ł����A�k�䓰�͐M�k�������g�ɂ���Č��Ă�ꂽ�悤�ł��B�@�h���A��䓰�͓��{�莛�h�A�k�䓰�͐��{�莛�h�Ȃ̂ŁA�قȂ�悤�ł��B�䓰�Ȃ�Ė��O�����Ă���̂ŁA���ꂱ���M�k�������̎��@���s�������Ă��铯�@�h���Ǝv�����̂ł����A�Ⴄ��ł��ˁB�ł��A����Ȃ狞�s�̐��{�莛�Ɠ��{�莛���قړ��ܓx�ɂ���̂ł�����A���������Ԓʂ���u�䓰�ʁv�Ƃ��ɂȂ��Ă��悩�����C�����܂����A���s�͂����͂Ȃ�Ȃ�������ł��ˁB����ʂ肠���肪���̒ʂ�ɂ����邩�ȂƎv���܂����A���s�ł͂��łɒʂ薼�̂���������ł��Ă����̂ŁA�ς��邱�Ƃ͂Ȃ�������ł��傤�ˁB�Ƃ肠�����A���䓰�̗R�����킩���Ė����ł����������ł����B
![]()
��1021���i�Q�O�Q�T�D�R�D�T�j�u81���ˁI�v
�@�A�����J�ɂ��鑷�����Ƌv���Ԃ�ɂ����Ղ�r�f�I�ʘb�����܂����B��̎q��8�A���̎q��6�ł��B�����̊Ԑ��܂ꂽ�Ǝv���Ă��܂������A���{�̊w��ƁA�������w�Z2�N�ƔN������ŁA4���ɂȂ��3�N����1�N���ł��B�q�ǂ��̐����́A�{���ɑ��������܂��B���n�Z�ɒʂ��Ă��܂��̂ʼnp����ƂĂ���肭�Ȃ��Ă��܂����A�y�j���ɂ͓��{��̕�K�Z�ɂ��ʂ��A���{����撣���Ă��܂��B��̎q�͊��������\�ǂ߂�悤�ɂȂ����悤�ŁA�����I���W�i���ō�������b�{�i���b�u�͂�܂���Ƃ����܂���̂����ڂ�����v210216.docx�j��A�������I���W�i���́u���ƂƂ����̂͂Ȃ��v�ihttps://www.dropbox.com/scl/fi/4l5jp7y8os1z1u5e34p9t/.pdf?rlkey=a9zkqk20x2s6kb4ku0nvjgzmz&st=2thq97g6&dl=0�j�Ƃ������q�������Ă��āA��������ǂ߂�悤�ɂȂ����Ƃ���������Ă���܂����B���b�̕��́A�ǂݏI����āu�}�}�A�X�g�[�J�[���ˁi�j�v�Ȃ�Č����Ă܂����i�j
�����u�����������͂��Ȃ��������傫���Ȃ��āA�ꏏ�ɂ��������߂�̂��y���݂ɂ��Ă����v�ƌ����ƁA�u�����͂���������߂�́H�v�ƕ����̂Łu20����v�Ɠ�����ƁA�u���������B���Ⴀ�A���������͍�69������A81�̎����ˁI�v�ƌ����ƁA���̎q���u�ڂ���83���I�v�ƌ��C�Ɍ����Ă���܂����B�Ȃ܂��o�Ă��܂����B�����炨�����ꏏ�Ɉ��߂���͂����낤�Ȃ�Ęb����Ƃ́A�������Ă��܂��܂����B���̓��܂Ő�Ό��C�ł������ȂƋ����v���܂����B
![]()
��1020���i�Q�O�Q�T�D�R�D�S�j���h��18�����ǁA�A�A
�@����̗I�m�e���̐��N�L�҉�������ɂȂ�܂������B������Ƌْ����͌��������̂́A�������肵�������ŗ��h�ł����B�����Ǝ���͎��O�ɒ�o����Ă��ĉ�������l�ōl�����킯�ł͂Ȃ��A��l�̎�����������̂ł��傤���A��������18�̐��N�c���Ƃ��ē������Ă��܂����B�H�{�Ƃ́A�����E�^�q����̌������ȗ��t���ɂ��炳�ꑱ���Ă��܂����A����Ȓ��ł܂������ɑf���Ɉ���Ă���悤�ŁA�悩�����ȂƎv���܂����B����30�`40�N������A�ނ����{�̓V�c�ɂȂ��Ă���킯�ł�����A�����Ƃ����l���ɂȂ��Ă��Ȃ��ƍ���̂ł����A����Ȃ�ɒ鉤�w���w��ł���̂��A18�̍c�ʌp����2�ʂ̐l���Ƃ��Ă�100�_���_�̋L�҉�ł����B
�@�������A���̌�ނɂ͎���҂��Ă��܂��B����̋L�҉�ł����₪�o���悤�ł����A�����̌����A��p�����ł��B���̍c���T�͂̂܂܂Ȃ�A������������������A���̏������j�q��ł���Ȃ��ƁA���{�̍c�����x�͑����Ȃ��Ȃ�Ƃ��������܂����v���b�V���[���ނɂ͂������Ă����킯�ł��B�������c�ʌp���ł���悤�ɂ����Ƃ��Ă��A������`��ς��Ȃ�����A�q���Y�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����v���b�V���[����͌����ĉ������܂���B���{�l�͓V�c���̈ێ����قƂ�ǂ��ׂĂ̐l���m�肵�Ă��܂����A���̌��ʂƂ��ēV�c�Ƃ̐l�X�ɁA��ʐ��E�Ȃ狖����Ȃ��قǂ̂����܂����l���N�Q��s���R����^���Ă��܂��Ă��܂��B
�@����Ȉ�ʐl�ɂ͔F�߂��Ȃ��悤�Ȑl���N�Q��s���R�����ÎĂ��炤�ɂ́A��ʎЉ�ł͔F�߂��Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ�OK�ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�V���v���Ɍ����A��v���Ȑ���V�c�ƂɊւ��Ă͔F�߂邱�Ƃł��傤���B�ł��A����݂͂�ȋ��ۊ�������ł��傤�ˁB�K���q�����Ƃ����v���b�V���[��^���Ȃ���A�̂̓V�c�⏫�R�̂悤�ɁA�Ȃ����������Ƃ͋����Ȃ��Ƃ����̂́A���x�ێ��̊ϓ_���猩��ƁA���Ȃ薵�����Ă��܂��B��v���Ȑ����ǂ����Ă����߂Ȃ�A�ȑO�ɂ������܂����i�Q�l�F��819���@����Ȃɒj�n�j�q�ɂ�����肽���Ȃ��i�Q�O�Q�P�D�P�O�D�V�j�j���A�j���c�ʌp���҂̐��q�̗Ⓚ�ۑ�����������s���A���z�̕�V�ƈ��������Ȃ�V�c�Ƃ̎q�ǂ����Y��ł������Ƃ����������W���A�q���Y��ł��炤�Ƃ������@�͂ǂ��ł��傤���B�܂��A�����Ƃ�����s�����ނ̂ł��傤�ˁB
�@���ǁA�����͓V�c���x�̂��Ƃ�^���ɍl�����ɁA�����Ƃ����I�m�e�����f�G�ȏ����Əo��������A�����ɒj�̎q�����܂�邱�Ƃ�P���Ɋ��҂��Ă���̂ł��傤�ˁB�ł��A����Ȃɕs���R�Ől�����Ȃ��A�����j�q�ނ��Ƃ��������҂����I�m�e���̍ȂƂ����n���̒n�ʂ�I������悤�ȏ����͂���̂ł��傤���B40�N�قǑO�ɁA���݂̓V�c��H�{�����N���}�������́A�N������ȐS�z�͂��Ă��܂���ł����B�Ⴂ�j���c����2�l�����܂������A���̒��̉��l�ς��A�����͑f�G�Ȓj���Əo����Č������A�q�ǂ������̂��K�����Ƒ����̐l���v���Ă��܂����̂ŁA�����Ƃ���2�l�Ƃ��f�G�ȏ����Əo����āA���q�q��c�@�������ł������悤�ɁA���q�����3�l�����炢����Ă����̂��낤�Ɣ��R�Ǝv���Ă��܂����B�������A���́A�����A�q�������Ƃ��K�������K�����Ƃ͌����Ȃ��Ƃ������l�ς̎���ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ̂ɁA�V�c�Ƃ����͐̂̉��l�ςŐ�����ƌ����Ă��܂��B�I�m�e���̏������S�z�ł��B���{�l���{�C�œV�c���x���ێ��������Ȃ�A�V�c�Ƃ����ɓ��ʂȃ��[�����Ƃ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����A�N���^���ɍl���Ă��Ȃ��̂��s�v�c�łȂ�܂���B
![]()
��1019���i�Q�O�Q�T�D�Q�D�Q�T�j�A���t�B�[�Ƌ˓���
�@����u����ׂ���007�v�Ƃ����ԑg�ɁA�A���t�B�[��3�l���o�����A����50�N�A�S��70�����ǁA�ς�炸�y��������Ă���p�������Ă��܂����B�ނ��1973�N�ɖ����w�@��w�ɓ��w�������Ńo���h����������10�N�قnjo���Ă���o�����u�����[�A���v�Ƃ����ȂŔ���n�߂��o���h�ł��B���̔N��ȏ�̐l�͐̂���悭�m���Ă���Ǝv���܂����A�ŋ߂�Z����́A��N�̍g���̍����40�N�Ԃ肭�炢�ɔނ炪�o�����A�����ł���ȃo���h���������Ə��߂Ēm�����l���������������ł��B3�l�Ƃ��o���G�e�B�ԑg�̋�C���悭�m���Ă���̂Ŋy�����ԑg�ɂȂ��Ă��܂����B�ނ�́A�����D���Ȓ|���܂肠�Ɠ��w�N�ŁA����1��ł��B����Ȏ�X�����Ċy�����߂�����70�͂����ȂƎv�킹�Ă����l�����ł��B
�@���āA������̌��NHK�́u�����̗܁v�Ƃ����ԑg�ŁA�w����z�ƂƂ��Ė�50�N�߂܂炸�A���ʊԍۂɁu�����͎w����z�Ƃ̋˓������v�ƍ������A���̐�����ɖS���Ȃ����˓����̐l�����Љ�Ă��܂����B�Ȃ��A����������ɏ��������Ǝv�������Ƃ����ƁA�˓������A���t�B�[��1�N�O��1972�N�ɓ��������w�@��w�ɓ��w���Ă������Ƃ�m��������ł��B�قړ�����̎�҂œ�����w�ɓ��w��������1�l��1�g�̐l�������܂�Ⴂ�߂��āA�قړ�����ł��鎄�Ȃ�Ɍ���Ă݂����Ȃ�܂����B
�L�������R�s�o�g�̋˓����͑�w�ɓ����Ă���A�����R�J�̓��ق��J���҂̍�����ԂȂǂ�m��A��������Ƃ����邽�߂ɂ́A���{�̐��ʂ邢����ɐ��Ԃ̒��ӂ����������邽�߂ɂ͔��e�����Ȃǂ����ׂ����ƍl����悤�ɂȂ�A���������s�������鍶���ߌ��h�O���[�v�ɑ����܂��B�˓����g�͒��ډ��S���Ȃ������O�H�d�H�r�����j�����̂����܂������ʂɋ����A�������g�����S�������j�����ł͐T�d�Ɏ����҂��o�Ȃ��悤�ɔz�����Ă��܂������A�l�����Ȃ��Ǝv���Ă������Ԃɂ��܂��܂����]�ƈ������������Ƃ������Ԃ��N����A�E�l�����̍߂Ŏw����z����邱�ƂɂȂ�܂��B�����O���[�v�̃����o�[�͂��ׂĂ��܂�܂������A�˓��������͂��܂炸�A�U���̂܂�50�N�߂��B��Đ����A�Ō�Ɏ�����������ۂɁA����{���𖼏��A�x�@�ɘA�����Ă�����������ł��B�߂܂������Ԃ����́A���҂��o���Ă��Ȃ��������Ƃ������Ē����Y�ōς�ł����̂ŁA�˓������X�ɏo�����Ă�����10���N�̌Y�����o�ċ˓����Ƃ��Đ����邱�Ƃ��ł������Ƃł��傤�B�˓������ƃJ�~���O�A�E�g���ĖS���Ȃ����ނ̂����͐e�����������Ȃ��ƌ����Ă���̂ŁA��������̂Ȃ���n�ɖ�������Ă��邻���ł��B
�A���t�B�[�Ƌ˓����̐l�������̂͂ǂ���������ł��傤�ˁB���́A�u���炯����v��1953�N4�����܂ꂩ��1958�N3�����܂��5�w�N���T�^�w�N�ƍl���Ă��܂��B1955�N5�����܂�̎��́A�܂��ɂ��傤�ǂǐ^�ł����A�˓�����1954�N1�����܂�ŁA�A���t�B�[��3�l��1954�N4�����܂ꂪ2�l��1955�N1�����܂ꂪ1�l�ł��B�����܂߂�5�l��1�N4�����̊Ԃɐ��܂�Ă��܂��B�قڊ��S�ɓ�����ł��B��������5�w�N���u���炯����v�̓T�^�ƍl����̂́A1972�N�~�̘A���ԌR���������Z�����璆�w2�C3�N���Ō�������ŁA�����ɊS�͂����Ă��A�w���^���ɔM���Ȃ邱�Ƃɉ��^�I�ɂȂ炴������Ȃ����ゾ�����Ǝv������ł��B�A���t�B�[��3�l�͍��Z���ォ��o���h����������Ă����悤�Ȃ̂ŁA�������ɂ͂��܂苻�����Ȃ������̂�������܂���B�������A�˓����͑�w���w��Ɋ����ƂɂȂ��Ă����킯�ł��B�܂��A1974�N���w�̎��̐���ł��A�V�����n�قljߌ��Ȋ����͂��Ȃ��Ă�����������M�S�ɂ���l�����͂���Ȃ�ɂ͂��܂����̂ŁA�˓��������������l������1�l�������̂ł��傤�B
���l���Ă݂�ƁA���̍��̊w�������́A�����G�l���M�[����������̂�T���Ă����l�͑��������悤�Ɏv���܂��B�����A���y�A�����A�����ł����߂���̂��A�݂�ȒT���Ă����C�����܂��B�A���t�B�[�͉��y���A�˓����͎�҂��~�����߂ɎЉ��ς��邱�Ƃ��߂������̂ł��傤�B���́A�����߂����Ă������Ȃ��B��w�ɓ��������_�ł́A���͓c�ɂ̍��Z���߂��āA�Ƃ肠�����K���Ŕw�L�т��đ�l�ɂȂ낤�Ƃ͂��Ă��܂������A���ɑł����߂邩�Ȃ�ĂƂ��Ă��܂����߂��Ȃ��悤�ȏ�Ԃ������C�����܂��B�悩�����̂́A���ł������ɂ킩�����ӂ�����邱�Ƃ͂ł����ɁA�������g�����R�̂ŗ����ł��Ȃ����Ƃɂ͎����ƐT�d�ɂȂ�Ȃ����������Ƃł��傤�B�����āA�l���ɍl���āA�B�ꌈ�߂��̂��Љ�w��I������Ƃ������Ƃł����B��w1�N�̓~�ł����B�������炿�傤��50�N�B���悢��70�����Ɛ������Ō}���悤�Ƃ��Ă��܂��B70�܂łǂ�Ȑl���ɂȂ邩�A��w����ɃX�^�[�g�n�_���������C�����܂��B�A���t�B�[�Ƌ˓����A�����Ď����B
![]()
��1018���i�Q�O�Q�T�D�Q�D�Q�P�j�V�c�a����
�@��������3�A�x�ƃj���[�X�Ō����Ă����̂ŁA�u�����A�Ȃ�����Ȏ�����3�A�x�H�v�Ǝv�����̂ł����A2��23�����V�c�a��������������Ȃ�ł��ˁB���a�ň�������ɂƂ��ẮA�V�c�a�����ƌ�����4��29���Ƃ����̂��ς��Ǝv�������ԓV�c�a�����ŁA���������12��23�������ǂȂ��݂���Ȃ��܂܁A�V�����V�c�a�����ɂȂ��Ă��܂����킯�ł��B12��23����2��23������w�Ζ��̐l�ԂɂƂ��ẮA���܂肠�肪�����x�݂ł͂Ȃ������̂ɑ��A4��29����GW�̎n�܂�Ƃ��������ł悢�j���ł����B4��29���́A���́u���a�̓��v�Ƃ������O�̏j���ɂȂ��Ă��܂���ˁB�ʂɁA���a�V�c���f���炵����������A�j���ɂ����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�����̏��a�Ƃ�������Ɏv����y���邽�߂Ƃ������ڂŁA���ۂ�GW�����҂��鍑���̂��߂ɁA���̂܂j���ɂ��������悢���낤�Ƃ������f�������̂��Ǝv���܂��B�i�����ɓ����āA���炭�́u�݂ǂ�̓��v�ł����B�j���h�ȓV�c�������Ƃ����Ӗ��łȂ�A����c�����ɗ��h�Ȑl�Ȃ̂ŁA���̂܂j���ɂ��ׂ��������Ƃ������ƂɂȂ�܂����A����Ȃ��Ƃ����Ă�����A�V�c�Ƃ���������j���������Ă��܂��܂�����A�����ł���ˁB
�@�ł��A�����V�c�̒a������11��3���ŁA��O�͖����߂Ƃ����j���ŁA���́u�����̓��v�Ɩ���ς��Ă��̂܂j���ɂȂ��Ă���͂����Ȃ��Ǝv���o���A���������A�吳�V�c�͉����������܂�ő吳����͓V���߁i�V�c�a�����j�̋x�݂͂��������낤�ƒ��ׂĂ݂����Ȃ�T���Ă݂���A���낢������悤�Ȏ�����m��܂����B�܂��A�������N�ɂ����ẮA�V���߂�11��3���ł͂Ȃ�9��22���ł����B�����V�c�́A�Éi5�N9��22�����܂�Ȃ̂������ł��B���ꂪ11��3���ɕς�����̂́A����6�N�ɑ��A���z��i����j���瑾�z��ɖ������{�����ύX���邱�Ƃɂ������߂ɁA�Éi5�N9��22����1852�N11��3���ɓ�����Ƃ������ƂŁA11��3�����V���߂ɂȂ��������ł��B���̎��������ύX���ꂽ�̂��I���߁i���݂̌����L�O���j�ł��B�_�b�Ɋ�Â��悤�Șb�Ȃ̂ɁA�Ȃ��2��11���Ȃ�Ē��r���[�ȓ��ɂ��Ȃ̂��낤�Ǝv���Ă��܂������A����������1��1���������̂��A���z��ł�2��11���ɓ�����Ƃ������ƂŁA���̓����I���߂ƂȂ��������ł��B�����L�O���̍��ɁA�������Œ����x�ɂ�����������̐l�����������̂��A�����������ƂȂ�ł���ˁB���Ȃ݂ɁA�����́A1��6�̕t�����͋x�������������ł�����A4����������1���x�߂�Ƃ������Ƃ������悤�ł��B�i�܂��ł��A����ȃX�P�W���[���œ����Ă����l�͂����킸���������ł��傤���B�j�y�j���x�A���j�x���Ƃ���1�T�ԒP�ʂ̃X�P�W���[���ɂȂ����̂́A����9�N�̂��Ƃ������ł��B
�@���āA�a������m��Ȃ������吳�V�c�ł����A����12�N8��31�����܂�ł����B�܂��܂������Ă̎����̐��܂ꂾ������ł��ˁB�ŁA�吳����ɓ������炱�̉ċx�ݒ���1�����x���ɂȂ����̂��Ǝv������A�Ȃ�ƓV���߂�8��31���ł����A�V���ߏj���Ƃ������̂�����A�����10��31���ɂ��������ł��B�V���߂��ꉞ�j���������悤�ł����A�q��≃���10��31���ł���������ł��B������������ł��傤���H����Ȃ肾������ł��ˁB10��31���̍����͂Ȃ�����ł��傤�ˁB�����V�c�̒a������11��3���͂ǂ��Ȃ������Ƃ����ƁA�吳����͏j���ł͂Ȃ����ʂ̓��ɖ߂���Ă��܂����B�����V�c����݂ł́A�S���Ȃ���7��30���������V�c�ՂƂ��ďj�������������ł��B����������A���ł���F���V�c�̕�����\�\1��30���i����ł͌c��2�N12��25���j�\�\���F���V�c�ՂƂ��ďj�������������ł��B�u�����A�����߂́H�v�ƈ�u�s�v�c�Ɏv���܂������A���a�ɂȂ������ɁA���Ղ�7��30������吳�V�c�̕��䂵��12��25���ɕς��A�V���߂�4��29���ł������j���A�V���ߏj���Ƃ����̂͂Ȃ��Ȃ�1���j�������邱�ƂɂȂ肻���������̂ŁA�����V�c�̒a������11��3�����߂Ƃ��ĐV�����j���ɂ��ďj���̓��������炳�Ȃ��悤�ɂ��������ł��B�܂�A11��3���͖����ȗ������Əj���������킯�ł͂Ȃ������ł��B���Ƃ����ЂƂ��łɒm�����̂́A�t���̓��A�H���̓��Ƃ����j���́A��O�́A�t�G�c��ՂƏH�G�c��ՂƌĂсA���V�c�̌����Ղ���Ƃ��āA����11�N�ɒlj����ꂽ�����ł��B�ߋ��̂���������̗��j�ׂĂ���ƒm��Ȃ����Ƃ���������킩���Ĕ��ɖʔ����ł��B
![]()
��1017���i�Q�O�Q�T�D�Q�D�P�V�j�������Ă��Ȃ����낤���H
�@��قǃ��C�h�V���[�����Ă�����A�g�{�|�l���C�O�̃I�����C���J�W�m�ɎQ�����Ă������ƂŌx�@�̎������Ă���Ƃ����j���[�X���Љ�A����ɊC�O�̃I�����C���J�W�m������Ă�����{�l��350���l�ȏア�āA20�Α�A30�Α�̒j�������S�Ȃ̂ŁA�M�����u���ɂ͂܂�Ȃ��悤�ɗl�X�Ȏ藧�Ă�łK�v������ƌ���Ă��܂����B�����āA���̂�������ɁA���x�̓o�����^�C���W�����{���̐�`�����Ă��܂����B1��300�~�ŁA1����2���~�A�O��܂����킹����3���~�Ɣԑg���ŏЉ�Ă��܂����B���₠�A���������Ȃ��ł����H�M�����u���ɂ͂܂�Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�Ƃ�����������ŁA�����܂��傤���āB���Ŏv����A���{�l�̎ˍK�S���������Ă����āA�J�W�m��������瑦�@���ᔽ���āA�S�R�����ł��܂���B���͂悭�āA�J�W�m�͂����Ȃ����R�͂Ȃ�Ȃ̂ł��傤���H���ɂ��M�����u�����߂��閵���͂�������܂���ˁB�T�b�J�[�̎������ʂ�toto�Ƃ������@�ȓq���̑ΏۂɂȂ��Ă���̂ɑ��A�싅�̎������ʂ͓q���̑Ώۂɂ�����A�E�g�ł��B�ǂ�Ș_���ŁA�Е��̃X�|�[�c�͓q���̑Ώۂɂ��Ă悭�A��������͂��߂ƌ��߂���̂ł��傤���B���Ԃ�_���͂Ȃ��Ǝv���܂��B���ɂ��C���t�H�[�}���ɑ����̐l������Ă������Ȉ�@�ȃM�����u���ɁA�q���}�[�W�����A�q���S���t�A�q�����Z�싅�Ȃǂ�����܂��B�����ŁA���n�A���ցA�{�[�g���[�X�Ȃǂ�OK�ł��B���̓M�����u���ɂ͑S���������Ȃ��A�������������Ƃ��Ȃ��l�Ԃł����A��т����_���ōs���Ȃ�A�S�����@�I�ȓq���̑Ώۂɂ����炢���̂���Ȃ����Ǝv���܂��B�J�W�m��IR���ł�����A���@�ɂȂ�͂��ł����AIR�{�ݓ��ōs�����̂��������@�ŁA����ȊO�ōs���͈̂�@�Ƃ��ɂȂ�̂ł��傤���B�悭�킩��܂���B
����ɂ��Ă��A�����̊Ԃ܂ŁA�N���W�����{�̐�`�����Ă��Ǝv������A���x�̓o�����^�C���W�����{�������ł��B���܂ł��܂蕷�������Ƃ��Ȃ��ȂƎv���Ă��܂������A���ׂ���2018�N����n�܂����悤�ł��B���ɂ��A�h���[���W�����{�A�T�}�[�W�����{�A�n���E�B���W�����{�A�����ĔN���W�����{�ƁA��������܂��B���������W�����{���̑��`�����āA�R�c�R�c�����C�����𔖂ꂳ���Ă����Љ�݂̍�����������ɋ^��ł��B���~��蓊�����Ɛ��{�������Ă���̂��A�ˍK�S�����Ƃ܂ł͌����܂��A�����͓����ĉ҂����̂Ƃ������l�ς𔖂ꂳ����������ʂ����Ă���C�����܂��B����ȉ��l�ς�����ŐA���t���Ă����āA�C�O�J�W�m�͂�����Ⴞ�߂Ȃ�Č����āA�N�������Ə]���̂ł��傤���B�������ȎЉ�ł��A�Ƃ�����薳�ӔC�Ȑ��{�ł��B
![]()
��1016���i�Q�O�Q�T�D�Q�D�P�P�j���Z���Ɨ��������ւ̋^��
�@�ېV�̉���S�ɂȂ��āA�S���I�ɂ����Z���Ɨ������������邩�ǂ���������ŋc�_����Ă��܂��B���{�͂��łɓ������Ă��܂����A���͍��Z���Ɨ��̖������͔��ɋ^��ł��B���Z�܂ŋ`������ɂ���Ȃ疳�������ׂ��ł��傤�B�ł��A���Z�͋`������ł͂���܂���B�{���w�т����l�������i�w����Ƃ���ł��B�������A����قƂ�ǂ̐l���i�w���Ă�������I�ɋ`������I�ɂȂ��Ă���̂͂킩���Ă͂��܂����A���������ꂽ������C���o��̂ł��傤���H�ނ���A�����ŃR�X�g���Ă��Ȃ����ƂŐ^���ɉ����悤�Ƃ��Ȃ��Ȃ�l�̕��������Ȃ肻���ȋC�����܂��B
�@�܂��ł��A���܂莞��ɋt�炤�̂��Ȃ�ł�����A�����͏������܂��傤�B�����̃|�C���g�Ƃ��ẮA�������Z�̎��Ɨ��������܂łł��B�Ȃ��������Z�܂Ŗ���������̂ł��傤���B���ێ������Z�̖��������s���Ă�����{�ł��łɐ����Ă��܂����A�������Z������l���������āA�������Z����l�������Ă��܂��B�����A�����Ȃ�܂���ˁB�ǂ���������ōs����Ȃ�A���̂܂ܑ�w�ɍs����\������������A�������肵���w�������Ă��ꂽ�肷�鎄�����Z�ɐl�C���o��͓̂��R�ł��B����Ȑ��x�𑱂��Ă�����A���{�̌������Z�͍��ア�����ׂ�Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B
�@�������w�͖���������Ă��Ȃ��悤�ł�����A�������Z������������̂͂��������ł��B�������Z�̎��Ɨ��Ɠ����z�����������Z�ɒʂ����k�ɂ��o���Ă�����Εs�����͂Ȃ��͂��ł��B�����͂Ȃ�����ǁA���������Ǝv���l�͌������Z�ɍs����Ƃ������ƂɂȂ�A�������Z�S�̂̃��x���A�b�v�ɂ��Ȃ���ł��傤�B���̑��{�̐��x���Ǝ������Z�ɒʂ��ꍇ63���~�܂ŕ{���⏕���A������镪�͊w�Z�����S���Ȃ��Ƃ����Ȃ������ł��B�������Ȑ��x�ł��B���Ԃ�A�������Z�͎��Ɨ��ł͂Ȃ����ځ\�\���Ƃ��Ύ{�ݐݔ���Ƃ��\�\�̋��z���グ�āA�������e�ƒ�̕��S�ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������Ȗ��ڂ̔�ڂ��ׂ�ڂ��ɍ����ȂǂƂ�����Ȃ��Ƃ��N���Ă������ł��B
�@�j���[�X�����Ă��Ă��A���Z���Ɨ��������ɔ��̈ӌ����͂����茾���l���قƂ�ǂ��Ȃ��̂��s�v�c�ł��B�ꗥ�x���́A���݂̍��̐��x�\�\�N��910���~�����̐��т̎q�ɁA�����E�������킸118,000�~���x���A590���~�����Ŏ������Z�Ȃ�396,000�~���x���\�\�ŏ\�����Ǝv���܂��B�i���������A�q�ǂ��̐��ɂ�����̈Ⴂ�͂����Ă��������ȂƎv���܂����B�j����������P�p�������������W�Ȃ��S�������ɂ�����A�������Z�͖L���Ȑ��тłȂ��Ƃ������ōs����悤�ɂ��Ă����A�������@��ɂ���قǑ傫�ȕs�����͐��܂�Ȃ��͂��ł��B�ނ���w��Ƃ������ƂŌ����A��w�̎��Ɨ����������܂��B���ɍ��������̂Ɣ�ׂ�Ƃ��܂�ɍ����A������̕������Ή����ׂ��ł��B��������w�̎��Ƃ������ƈ�������Ƃ��A�w�ɖ{���Ɋ撣���Ă���w���ɂ͏��������Ȃ��ŋ��t�^���w������������o���悤�ɂ������������Ǝv���܂��B
![]()
��1015���i�Q�O�Q�T�D�Q�D�P�O�j�ł��グ�ē�������̂͒N�Ȃ̂��낤�H
�@�g�����v���哝�̂ɂȂ��Ă���A�����̂悤�Ɋł��グ��Ƃ������������X�Ƃ��āA��������ޗ��Ɏg����2���Ԍ���L���ɐi�߂悤�Ƃ��Ă��܂��B���ۂɃJ�i�_�����L�V�R�����������Ċł��������Ȃ��悤�ɂ����悤�ł����A�ł��オ�����獢��̂͗A�o�������Ȃ̂ł��傤���H�A�������i�����ŕ����������Ȃ�킯�ł���ˁB����̂́A�A�������i����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�����J�̍����Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ł́A�����̎Y�Ƃ���邽�߂ɗ��p����邱�Ƃ������Ǝv���܂����A�������g�����v�����ł���Ƃ�������̂Ɋł������Ă������ꍇ�A�A���ł��Ȃ��Ȃ����i�����A�����J�őS�����Y�ł���̂ł��傤���B�ԈႢ�Ȃ��ł��܂����ˁB����܂ň�������o���Ă������̂��ł̂����ō����Ȃ��Ă��܂�����A���Y������������݂�ȍ��邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���E�̌o�ς͕�������̎��������I��������A���R�Ȗf�Ղ��������s����悤�ɂȂ�A�����Ő��Y�ł��Ȃ����̂�A�����A�]�肷����̂�A�o���邱�ƂŁA���L���Ȑ������ł���悤�ɂȂ��Ă����͂��ł��B�g�����v�̊ł��ǂ�ǂ�グ�Ă����Ƃ��������́A���������̎���ɖ߂������̂��ƌ��������Ȃ�܂��B�A�����J�ɂ͂ł�������������̂ł͂Ȃ��A�H����Ǝ��̂�i�o������Ȃ�A��������Ȃ肵�āA�A�����J�̎Y�Ɣ��W�ɍv������Ƃ����`�ŕt�������Ƃ����̂��g�����v�̎咣�̂悤�ł����A������A�����J�̗̓y���L���Ƃ͌����Ă��A���ׂĂ̂��̂������ŗp�ӂ���͖̂����ł��B����ȃg�����v�����ł̓A�����J�������K���ɂȂ�Ȃ��Ǝv���̂ł����A�A�A
![]()
��1014���i�Q�O�Q�T�D�Q�D�R�j���[��A�A�A�t�̎v���o��148�~�I
�@�c��1�N������Ƃ̑�w���t�����ŁA���������Ȃ��Ȃ�̂ŁA���N�͒f�̗������Ă����Ȃ��Ƃ����܂���B���̑�1�e�Ƃ��Đt����ɏW�߂Ă���LP���R�[�h67�������Ǝ҂ɑ����܂����B��قǔ������z�̕]�����͂����̂ł����A�Ȃ�Ƒ��z148�~�ł����B����1��10�`20�~���炢�̕]���͂����čŒ�ł�1000�~���炢�͒�����̂ł͂Ǝv���Ă��܂������A�Â������ł��B�ł��A���������Ă��ꂽ���A�����������ł����̂ŁA�����������̂��l����Ƃ���ȍ���z�ɂȂ��Ă��d���Ȃ��̂�������܂���B�����J���̂悤�Ȗʓ|�Ȃ��Ƃ����C�̂Ȃ��l�Ԃł��̂ŁA����LP���R�[�h���������Ƃ��Ǝ̂Ă邵���Ȃ��̂��ȂƎv���Ă����̂ŁA148�~�ł���������Ă���āA�܂��N���������Ă����Ȃ�A�S�~�ɂȂ���͂�����Ǝv���āA������������܂����B���̌�A���ЂɊւ��Ă���������Ă����Ƃ���ɑ����Ă��������ȂƎv���Ă���̂ł����A����z�͂���Ȃ��̂Ȃ�ł��傤�ˁB�܂��ł��A�S�~�ɂȂ���́A�N�������p���Ă����Ȃ�悵�Ƃ��ď�������Ƃ�i�߂Ă��������Ǝv���܂��B�Ō�ɁA�v���o��LP�A���o���������Ɍf�ڂ��āA���̉i���̎v���o�ɂ������Ǝv���܂��B


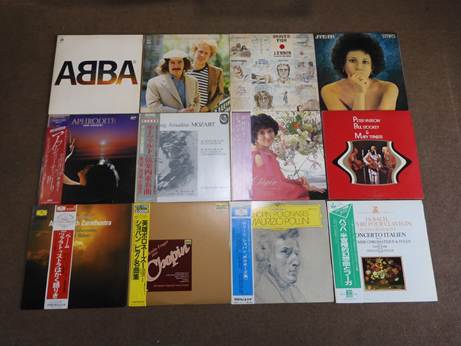



![]()
��1013���i�Q�O�Q�T�D�P�D�Q�P�j�u�펯�̊v���v
�@�g�����v���哝�̂ɖ߂��Ă��܂����B�匙���Ȑl���ŁA����Ȑl�Ԃ��卑�A�����J�𗦂���Ǝv���ƁA�����Ƃ��܂��B�������A�ނ�����̏A�C�����Ŏg�����u�펯�̊v���v�Ƃ������t�́A���킶��L����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���A�A�����J�����łȂ����E�Ŏ������S��`�I�ȕێ琨�͂������𑝂��Ă���̂́A���ǃ��x�����̋ɒ[�Ȏ咣���A�����̐l�����ݓI�ɂ͋^��Ɏv���Ă��邩��ł��B�ł��A���ʂ̐l�����͂�����I���Ɍ������ɂ���킯�ł����A�g�����v�̓^�e�}�G���Y�킲�ƂȂǑS���������Ĕ������܂��B�u���ʂ͒j�Ə��̂Q�����v�Ȃ�Ĕ����́A�{���͓�����O�ɑ����̐l���v���Ă��邱�Ƃł����A����̃^�e�}�G�ł͂����������ɍl���Ă͂Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B����������C���g�����v�̂悤�ȋ��d�ێ�h���x�������Ă��܂��̂ł��B
�@�������A����͍ň��ȏł��B�s���߂������x�����Ƃ��̔����Ƃ��Ă̋��d�ێ�̑Η��Ƃ����̂́A�Љ�ɕ��f�������܂��B�ߏ�ȃ��x�����̎咣��}����̂����d�ێ�ɂȂ��Ă��܂��̂͊댯�ł��B�o�����X�̎�ꂽ�����I���z���K�v�ł��B�g�����v�̎咣�͌����ď펯�ł͂Ȃ����̂���������܂����A�m���ɑ����̐l�ɂƂ��ăz���l�ɋ߂��咣������̂ŁA���ꂱ���펯���ƌ�����ƁA�������Ǝv���Ă��܂��l�������������ł��B�������A�z���l�����܂�Ɍy������̂��悭�Ȃ��Ǝv���܂����A�����őS���F�߂�̂��悭�Ȃ��͂��ł��B�l���~�]�i�z���l�j�̂܂܂ɐ�������A�Љ�̒����͐��藧���܂���B�K�ɗ~�]���R���g�[�����ď��߂ĎЉ�̒����͐��藧�̂ł��B�^�e�}�G�𐳂����Ǝv���߂����A���ƌ����Ă��ׂăz���l�ł����̂��Ƃ��v�킸�A�K�Ȓ��f�I���z�����x�������ׂ��ł��B
�펯�͊v���ŕ��y��������̂ł͂Ȃ��ł��B�������Ԃ������āA�e�Љ���o���Ă������̂ł��B�Љ�w�ł́u�펯���^���Ă݂悤�v�Ƃ������z�����߂܂����A����́u�펯��ے肵�Đ����Ȃ����v�ƌ����Ă���킯�ł͂���܂���B�Ȃ�����펯������Љ�ŏ펯�Ƃ��Ēʗp���Ă���̂����l���邽�߂ɁA��x�펯���^���Ă݂悤�ƌ����Ă���̂ł��B�e�Љ�͑����̏펯�������Ă���A������O��Ƃ��ē����Ă��܂��B���ɁA����100�N�Ԃɋߑ㎑�{��`�Љ�Ō`����Ă����펯������20�N�قǂ̊Ԃɂ��Ȃ�^�⎋����ے肳��Ă��Ă����܂��B�������A�����������̂́u�v���v�I�Ȃ����ł͂Ȃ��A������ƍl���āA�Љ������Ɖ���Ă������߂ɂ́A�ǂ̏펯���c��ׂ��Ȃ̂����l�������ʂł���ׂ��ł��B���������A�ߏ�Ƀ��x�����ᔻ�����邾���ł͕��f�����������ł��B���x�����̎咣������������ŁA�����ׂ����̂Ǝ����ׂ��łȂ����̂J�ɋ�ʂ���ׂ��ł��B�u�Â��ȏ펯�̕����v�͂Ȃ����ׂ����Ǝv���܂����A�u�펯�̊v���v�͊댯�ȏL�����������܂��B�~�j�E�g�����v�݂����ȑ��݂����������Ɍ���Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɂ��A�u�Â��ȏ펯�̕����v���߂����ׂ����Ǝv���܂��B
![]()
��1012���i�Q�O�Q�T�D�P�D�P�T�j���ǂ��̐��l��
����[�~���������獡�ǂ��̐��l���i��20�̏W���j�ɂ��Ă̘b���A�����܂����B���ɋ��������Ƃ����ƁA���ǂ��̐��l���́A�����̎�Â̎����I�������ɏ��������͐U������h���X�ɒ��ւ��āA�z�e���ȂǂŒ��w�Z���Ƃɍs���铯����ɂ������ĎQ������Ƃ������Ƃł��B���l����ɓ�������s���Ƃ����̂͐̂��炻��Ȃ�ɍs���Ă����Ǝv���܂����A���̗ǂ��l�����𒆐S�ɍs������̂��قƂ�ǂŁA�w�Z�P�ʂōs���铯����Ƃ����̂͂Ȃ������悤�ȋC�����܂��B�i���w�Z��1�����Ƃ����������Ȏ����̂ł́A���̂܂ܓ�����ɂȂ�Ƃ������Ƃ͂�������������܂��B�j�����̖�������2011�N�ɐ��l�����s���܂������A���̎��ɂ͂���������K�͂ȓ�����ɂ͏o�����Ă��Ȃ������悤�Ɏv���܂��B��̂����炱��Ȋ��K���ł����낤���ƋC�ɂȂ��đ��Ɛ������𒆐S�ɏ����b���Ă݂܂����B���̌��ʁA�ȉ��̂悤�Ȃ��Ƃ��킩��܂����B
90�N��ɐ��l�����}���������q�����͐��l���ɏo����͂��Ɖ��U���āA���̗ǂ��l�����ƏW�܂��Ĉ��ނƂ����悤�Ȏ��͂��Ă����悤�ł����A�w�Z�P�ʂŏW�܂��Ă����Ƃ����b�͏o�ė��܂���ł����B1�ԑ����w�Z�P�ʂŏW�܂��Ă����Ƃ������Ă��ꂽ�̂�2006�N�ɐ��l�����}�����l�ł����B�����ŁA2012�N�ɐ��l�����}�����l�ł�����Ȋw�Z�P�ʂ̓�����͂Ȃ������Ƃ�����������܂����B2013�N�ȍ~�ɐ��l�����}�����l�����ł͂��Ȃ葽���̐l���w�Z�P�ʂ̓�����������ƋL�������Ă��܂����B���������̒��S�ɂȂ��Ă��郁���o�[���A���l�����s�ψ��̂悤�Ȃ������肵���l�̏ꍇ�ɂ͑����̐l���Q�������悤�ł����A���Ȑl�����S�ɂȂ��Ă�Ƃ�����ۂ�����ƁA�Ⴂ����ł��Q�����Ȃ������Ƃ����l�����Ȃ肢���悤�ł��B���̌����[�~�������ɘb�������ɂ́A�����ɋ����������w�𑲋Ƃ���15�l�̂���14�l�̒n��ł͊w�Z�P�ʂ̓�������J����A1�l�������Ă͑S�������̓�����ɎQ�������ƌ����Ă��܂����̂ŁA�������s���ɋ߂��Ȃ��Ă���̂ł��傤�B
���̕ω��̔w�i�ɂ�SNS�ƃX�}�z�̕��y���傫���e�����Ă���ƍl�����܂��B���{�̑�w���̊ԂŃX�}�z����C�ɕ��y���Ă����̂�2011�N���̂��Ƃł��BSNS�͂���ȑO���~�N�V�B�Ȃǂ𒆐S�ɂ�����x�̓K���P�[�ł��g���Ă��܂������A��͂�X�}�z�̓o��ɂ����SNS�͂��{�i�������Ǝv���܂��BLINE�Ȃǂ�ʂ��ĘA�������ɂ��₷���Ȃ�A�l���W�߂�̂��e�ՂɂȂ����悤�ł��B�ȑO���̂��ʐM�ŎႢ�l�����̊Ԃœ�����ǂ�ǂ�Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ə����܂����i��1004���@�������N���X��͏����Ă����̂����A�A�A�i�Q�O�Q�S�D�P�P�D�Q�R�j�j���A���l���͓��������������ɂ݂�Ȃ��m���ɂ��̓��ɏW�܂邱�Ƃ��ł���̂ŁA�������ݒ肵�₷���̂ł��傤�B���N���l�����}������������������q���瓾��ꂽ�b�ł́A���̖�����̏ꍇ�A1����̓����160�l�A2���110�l�A3���60�l�����������ł��B�������l���ł��B
�e���r�̃j���[�X�ł͐��ꒅ�𒅂�������������������f��A���ǂ��̐��l���͂���Ȋ������Ǝv���Ă��܂������A���̌�ɂ���ȃp�[�e�B�̂悤�ȓ���������Ă���̂̓j���[�X�ł͎��グ�Ă���Ȃ��̂Œm��܂���ł����B���l�������̂܂ɂ��������ς���Ă���悤�ł��B�ǂ�ȕω������Ă��Ă���̂��A�����ƒm�肽���̂ŁA�����ǂ�ŋ��������������́A���Ў����̎��̐��l���͂���Ȃ������Ƃ������������������B�y���݂ɂ��Ă��܂��B
![]()
��1011���i�Q�O�Q�T�D�P�D�R�j���a100�N
�@���N�͏��a�������Ă����Ƃ�����A���a100�N�ɂ�����Ƃ������Ƃ����傭���傭���f�B�A�Ō���Ă��܂��B�N���ɂ��A���a�����99�N��U��Ԃ�ԑg�����{������Ă��܂������A�����ƍ�������������ԑg����������邱�Ƃł��傤�BNHK�������J�n���炿�傤��100�N�Ƃ������ƂȂ̂ŁA���낢�뗍�߂ĕ����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�ӂƎv�����̂ł����A2011�N�͑吳100�N�ɓ�����܂������A����Ȍ����͂܂������Ȃ������ł��ˁB3��11���ȍ~�͓����{��k�Ђƕ�����1�����̖��ł���ǂ���ł͂Ȃ������ł��傤���A����ȑO��1,2���ɂ��u�吳100�N�v�Ȃ�ĒN�������Ă��Ȃ������ł��B�ł��A1967�N�̖���100�N�̎��͌��\�����Ă��܂����B���͏��w�Z6�N�ł������A�w�Z�ł��搶���u���N�͖����Ő�������100�N�ɓ�����v�Ƙb���Ă����̂��o���Ă��܂��B���̋L���ł͏j�����������悤�ȋC�������̂ł����A���ׂ��疾��100�N�̋L�O���T�͗��N��1968�N�ɂ���Ă���A�j���ɂ͂��Ȃ������悤�ł��B���������Ȃ��Ƃ���ɒ��ׂĂ݂���A1�N�O��1966�N����2��11�����u�����L�O�̓��v�Ƃ��ďj���ɂȂ��Ă��܂��B��قǂ̐搶�̘b���A���̌����L�O���̐���ɗ��߂Ęb���ꂽ�悤�ȋC�����܂��B������ɂ���A���̂�����̋L���������Ⴒ����ɂȂ��āA����100�N�̋L�O�ŏj�����������Ɗo���邱�ƂɂȂ����̂��낤�Ǝv���܂��B
�܂��ł��A�����͑O�ߑ�Љ��ߑ�Љ�ɁA���{���ς��������I�ȓ]�����ł�����A���ꂩ��100�N�ƍl����̂ɂ͒P�Ȃ鐔���ȏ�̈Ӗ����������Ǝv���܂��B���a����100�N�͂ǂ��ł��傤�ˁB�ނ���A����̓]���_�Ƃ��ẮA��2�����E���̏I��������a20�N�̕����d�v���Ƃ����̂͏O�ڂ̈�v����Ƃ���ł��傤�B���̎��ɁA���a�V�c���ވʂ��A����c���V�c�ɂȂ��Ă�����A���̎��_�Ō����͕ς��A�������琔����ƁA���N��80�N�Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B������u���80�N�v�ł��B
�ŋ߂͂��낢��ȏo��������Z�N�Ƃ����̂��悭�����܂��B1�N�A2�N�͎v���o����₷���ł����A���炭�o��10�N���݂��炢�ŏœ_�Ă邱�Ƃ������ł��B�����āA���N�͂��܂��܂ł����A�����������̂��������ȔN�ł��B�u���80�N�v�u�����}���}70�N�v�u�j���ٗp�@��ϓ��@40�N�v�u��_�W�H��k��30�N�v�ȂǁA�ς��Ǝv�������̂ł����낢��o�Ă��܂��B�����u���a70�N�v�ŁA�����}�Ɠ����N�ł��i�j�����܂����B�܂����̂��Ƃ͂Ƃ������A�Љ�̕��͑��v�ł��傤���B10�N�ȏ�O�Ɂu��431���@�������{�Љ�N�̍���i�Q�O�P�Q�D�R�D�T�j�v�Ƃ������͂��A���́u���ʐM�v�ɏ����܂������A�������炳���13�N�̔N��������܂����B���̎��_�ł��łɎЉ�̍�����Ƃ��Ċ뜜���Ă������Ƃ́A�������{�I�ɂ͐�������Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B�u���a�v�N�͂����������s���Ă��܂����A�u���Љ�v�N�͂���ɍ�������܂ܐ��������Ă���悤�Ɏv���܂��B���Ă��āu���a100�N�����80�N�v�́A�ǂ��1�N�ɂȂ�̂ł��傤���B
![]()